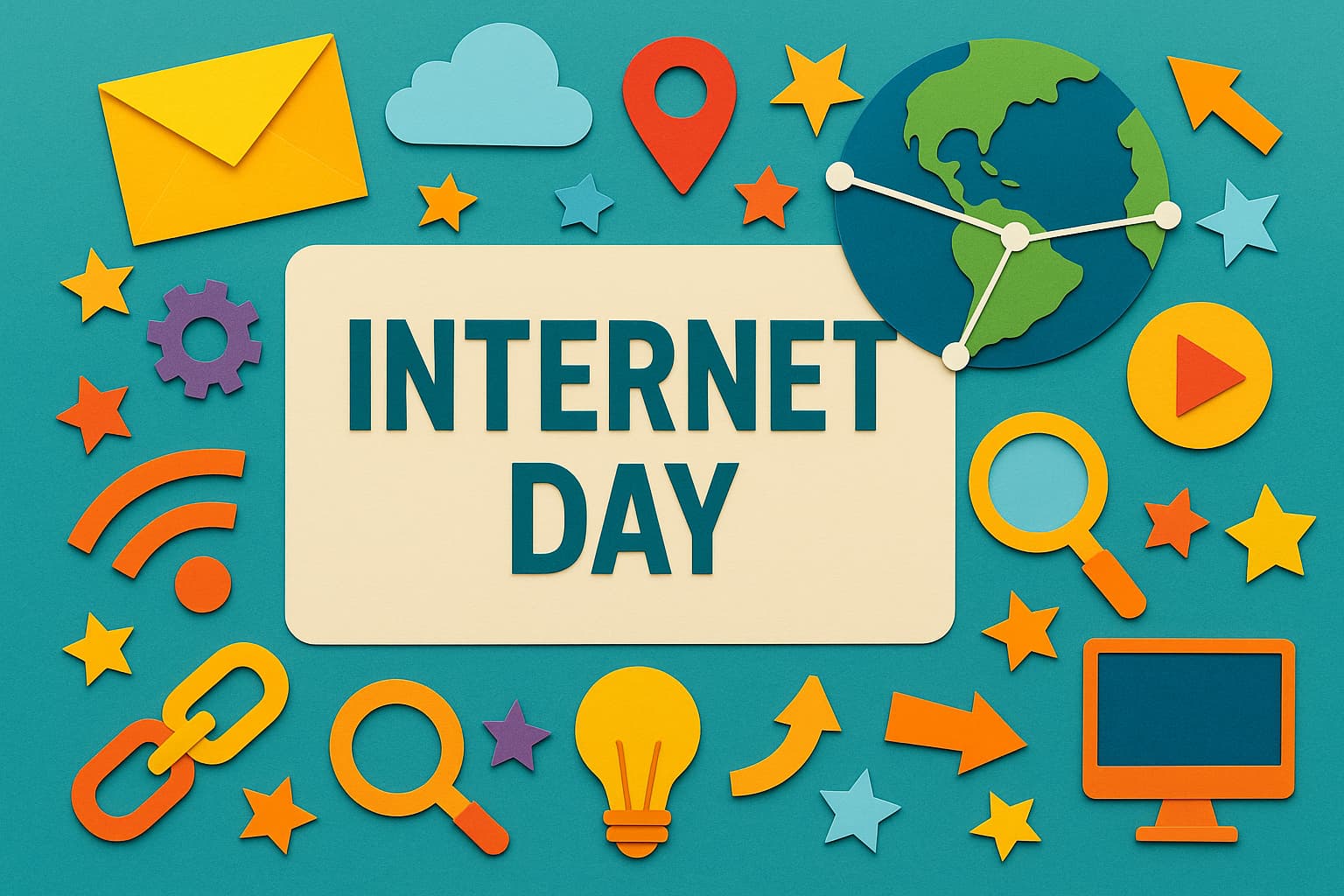インターネット記念日(11月21日)はどんな日?
✅ 1969年11月21日にARPAネットの4拠点接続による実験が行われ、インターネットの基礎が築かれた日。
✅ 「インターネット誕生日(10月29日)」とは別に、複数拠点の本格接続が開始された重要な節目として位置づけられている。
✅ 米国防総省のARPAと、カリフォルニア大学やユタ大学などの研究機関が深く関わっている。
革命は静かに始まった。インターネット記念日という名の“未来の起点”
目の前のスマホ。ほんの数秒で調べ物ができて、遠くの誰かと話せて、商品まで買えてしまう。
そんな「当たり前」になった生活の根っこには、ある日行われた、たった4つの拠点をつなぐ小さな実験があることをご存じでしょうか。
それが「インターネット記念日」の由来となった、1969年11月21日。
アメリカの研究機関4か所が、初めて同時にコンピュータでつながったこの日こそ、人類の情報革命の原点だったのです。
今回ご紹介するのは、その歴史的な「インターネット記念日(11月21日)」。
どんな背景で誕生し、なぜ今この記念日を知ることが意味を持つのか。
この記事を読み終えたとき、あなたは「インターネット」という言葉を、ちょっと特別な目で見つめ直しているかもしれません。
インターネット記念日の由来|4拠点接続で“世界”が広がった日
1969年11月21日。この日は、世界初の多地点同時接続ネットワーク「ARPAネット(Advanced Research Projects Agency Network)」が稼働した記念すべき日です。
このネットワークを設計・指導していたのは、アメリカ国防総省の先進研究計画局「ARPA」。
彼らの目的は、軍事的な有事の際にも、情報が分断されることなくやりとりできる「分散型通信ネットワーク」を構築することでした。
特に冷戦下では、通信インフラが一カ所に集中していると、攻撃された瞬間に情報が絶たれるというリスクがありました。
その解決策として浮かび上がったのが、パケット通信技術を用いた分散型ネットワーク。
そしてこの技術を、次の4拠点に設置されたコンピュータを通じて実験的に稼働させたのが、この11月21日だったのです。
- カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)
- スタンフォード研究所(SRI)
- カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)
- ユタ大学
この接続成功は、情報という見えない糸が、国や場所に縛られずに世界をつなげられることを証明しました。
それはまさに、今日のインターネットの「原型」と言える瞬間でした。
10月29日との違いとは?インターネット記念日と誕生日の違い
インターネットに関する記念日として、よく「10月29日」と混同されることがあります。
実は、これにはちゃんとした区別があるのです。
1969年10月29日、UCLAとSRIの2拠点間で、初めてパケット通信によるメッセージの送信が成功しました。
その最初の言葉は「LOGIN」。
……のはずが、実際に届いたのは「LO」。
3文字目でシステムがクラッシュしてしまったのです。
けれど、この“失敗とも言える成功”こそが、世界初のインターネット通信だったのです。
一方の11月21日は、通信技術の「単発成功」から「本格実用」へと移行した日。
複数拠点を結ぶことで、ネットワークが単なる2地点間通信ではなく、「多地点・多方向型」へと発展したという点で、より今日のインターネットに近い構造が生まれた日でした。
だからこそ、11月21日は「記念日」、10月29日は「誕生日」と、それぞれ異なる意味で語り継がれているのです。
インターネット記念日に関わる人物・組織|影のヒーローたち
インターネット記念日を語るうえで欠かせないのが、実際にこの技術を形にした人物や組織の存在です。
まずは開発を主導した「ARPA(Advanced Research Projects Agency)」。
現在は「DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)」として知られ、数々の軍事技術や基礎科学の研究を行っています。
その中でARPAネットの構築を推進した人物が、ローレンス・ロバーツ(Lawrence G. Roberts)です。
彼は「ネットワークを使って、コンピュータ同士がリアルタイムで情報を交換できるようにする」というアイデアを実現しました。
さらに忘れてはならないのが、レナード・クラインロック(Leonard Kleinrock)。
彼はパケット通信の理論的基盤を築いた研究者であり、最初のARPAネット接続が行われたUCLAで中心的な役割を果たしました。
この2人の尽力、そして技術を現場で支えた多くの学生や技術者たちによって、インターネットの「基礎」は築かれたのです。
インターネット記念日で知っておきたい豆知識
意外と知られていないのが、ARPAネットが最初に使われた目的です。
「軍事通信」や「大学の研究発表」では?と思うかもしれませんが、実は研究者同士の雑談もよく交わされていました。
しかも、時にはプログラムのバグについてボヤいたり、冗談を言い合ったり。
この“人間らしさ”が、後のチャット文化やSNSに通じていると考えると、インターネットの本質が少し見えてきます。
また、現在「インターネット」と聞くと、世界中が瞬時につながるイメージですが、ARPAネットの段階では通信速度も遅く、しかも接続に専門知識が必要でした。
ところが1970年代〜80年代にかけてTCP/IPの導入やUNIXベースのネットワーク技術の発展により、今のような柔軟で開かれた通信網へと成長していきます。
そして1990年代には、一般家庭でも使えるようになり、インターネットは一気に「市民権」を得ることになりました。
つまり、11月21日の記念日は、私たちが今使っているすべてのネットサービスの“ご先祖さま”が動き出した日ともいえるのです。
インターネット記念日に関するよくある質問
Q1. どうして11月21日がインターネット記念日になったの?
A1. この日はARPAネットが初めて4拠点を同時接続して動作した、インターネットの「実用化」への第一歩を記した重要な日だからです。
Q2. 日本で最初にインターネットが使われたのはいつ?
A2. 日本では1984年ごろに大学間ネットワーク「JUNET」が誕生し、1992年以降に商用サービスとして広まりました。
Q3. インターネット記念日には何をすればいい?
A3. インターネットの歴史やセキュリティについて学ぶきっかけにするのがおすすめです。また、SNSでこの記念日を広めるのも一つの方法です。
インターネット記念日をきっかけに、つながる未来へ思いを馳せよう
インターネットは、今この瞬間も、世界中の誰かと誰かをつなぎ続けています。
そしてその始まりには、名もなき研究者たちの熱意と、たった4つのコンピュータの通信実験がありました。
記念日は単なる「日付」ではありません。
それは、何かが始まった瞬間に、人々が意味を込めて名づけた“記憶”なのです。
だからこそ、「インターネット記念日」を知るということは、自分たちが暮らすこの社会を、少しだけ深く理解することに繋がります。
この記念日をきっかけに、ネットに感謝し、未来への好奇心を少しでも持てたら——。
それが、今日、この記事を読んでくれたあなたにとっての「つながる」第一歩になるのかもしれません。