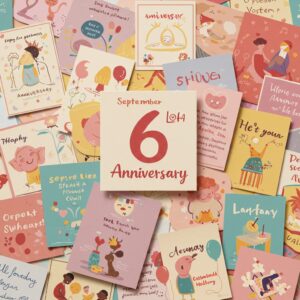「黒霧島の日」(9月6日)はどんな日?
✅ 本格芋焼酎「黒霧島」の魅力を広く伝えるために制定された記念日。
✅ 「く(9)ろ(6)きりしま」の語呂合わせが由来。
✅ 宮崎県都城市の霧島酒造と、日本記念日協会が深く関係している。
黒霧島の日は、焼酎が文化になる日。
「焼酎が好きですか?」
この問いに、胸を張って「黒霧島」と答える人は少なくないはずです。
“黒霧島の日”とは、そんな日本中の焼酎ファンにとって特別な1日。
毎年9月6日、「く(9)ろ(6)きりしま」の語呂にちなんで制定されたこの記念日は、霧島酒造が誇る代表銘柄「黒霧島」の魅力を広く届けるために作られました。
宮崎県都城市に本社を構える霧島酒造。
その地で育まれた素材と、代々受け継がれてきた焼酎づくりの技術が出会い、1998年に誕生したのが「黒霧島」です。
トロッとした甘みと、後味のキリッとした切れ味は、まさに“食と響き合う”焼酎。
和洋中、どんな料理にも寄り添い、食卓をより豊かに彩ってくれます。
この記事では、「黒霧島の日」が生まれた背景や、黒霧島という焼酎の深い魅力、楽しみ方、豆知識まで――たっぷりと掘り下げて紹介します。
「ただの記念日」と侮るなかれ。
読めばきっと、あなたも今日、1杯飲みたくなる。
「黒霧島の日」の由来とは?数字に込めたユーモアと誇り
「黒霧島の日」は、2021年(令和3年)に正式に認定された記念日です。
制定したのは、霧島酒造株式会社。
本格芋焼酎「黒霧島」を、より多くの人に知ってもらい、味わってもらうために作られました。
なぜ9月6日なのか?
それは、「く(9)ろ(6)きりしま」という語呂合わせに由来します。
少し遊び心のあるこのネーミングには、企業の柔らかさと親しみやすさも表れています。
けれど、単なるダジャレで済ませないのが霧島酒造のすごいところ。
この日は、製品への強い誇りと品質の高さ、そして焼酎文化を広めていきたいという真摯な思いが込められた記念日でもあるのです。
さらにこの記念日は、一般社団法人・日本記念日協会によって認定・登録されており、企業の広報戦略としても非常に成功しています。
焼酎文化を未来に残す一歩。
それが「黒霧島の日」の真の意味です。
黒霧島の日に知っておきたい焼酎の豆知識
「黒霧島」とは、単なる芋焼酎ではありません。
一度でも口にしたことがある人なら、その“トロッとした甘み”と“キレのある後味”に、驚きを覚えたはずです。
その秘密は、大正5年(1916年)の創業当初から受け継がれてきた黒麹仕込みにあります。
黒麹とは、発酵時にクエン酸を多く出す麹のこと。
これが焼酎に豊かな香りとコクを与え、雑菌の繁殖を抑える効果もあります。
そして、「黒霧島」の主な原料となるのが、**九州産のさつまいも「黄金千貫(こがねせんがん)」**です。
この品種はでんぷん質が豊富で、焼酎に最適。
焼酎らしい甘みを引き出すことができます。
さらに、仕込みに使われる水は「霧島裂罅水(きりしまれっかすい)」と呼ばれる地下水。
これは、霧島連山の火山活動によって作られた大地の割れ目に、長い年月をかけて蓄えられた清冽な天然水です。
地元・宮崎県都城市の自然が、まさに黒霧島の味を支えているのです。
このように、「黒霧島」は、ただの酒ではありません。
原料、製法、水、すべてにおいて、“南九州の風土”と“技術”が凝縮された、こだわりの一品なのです。
「黒霧島の日」に欠かせない!霧島酒造の人々と魂の技術
「黒霧島」の魅力の裏には、職人たちの情熱があります。
霧島酒造は、100年以上の歴史を持つ老舗蔵元です。
創業者・江夏順吉(えなつ じゅんきち)氏が、地元・都城の恵みを活かし、焼酎を通じて地域を元気にしたいという想いで立ち上げた企業です。
その信念は、現在も脈々と受け継がれています。
霧島酒造では、「麹づくり」から「蒸留」「熟成」「ブレンド」まで、全ての工程を丁寧に手作業で行っています。
特に「黒霧島」では、創業時の黒麹仕込みの技術を現代に蘇らせるため、長年の研究と試行錯誤が重ねられました。
その結果、1998年に誕生した「黒霧島」は、たちまち焼酎業界に革命をもたらします。
発売初年度から爆発的な人気を誇り、今や日本全国、どの居酒屋でも見かける“定番中の定番”となりました。
霧島酒造の理念は「焼酎の価値を、もっと高く」。
この言葉の通り、彼らは単なるアルコールではなく、“文化としての焼酎”を創り出しているのです。
また、同社は社会貢献にも積極的で、地元農家と契約し、さつまいもの栽培から一体となって焼酎づくりに取り組んでいます。
「黒霧島の日」は、そんな彼らの努力と誇りを称える日でもあるのです。
黒霧島の日に関するよくある質問
Q1:黒霧島って、なぜそんなに人気があるの?
答えはシンプル。
「美味しい」からです。
それも、ただ美味しいだけではありません。
黒麹由来のコクと甘み、霧島裂罅水によるやわらかさ、そして料理を選ばない万能な風味――。
飲みやすくて奥深い。
だから初心者にも通にも愛されるのです。
しかもリーズナブル。
味、価格、品質の三拍子がそろっている焼酎、それが黒霧島です。
Q2:黒霧島はどうやって飲むのが一番おいしい?
定番は「ロック」または「お湯割り」です。
ロックで飲むと、冷たさが香りを引き締めてくれます。
お湯割りにすれば、芋の甘みがふわっと立ち上り、香りと味の奥行きが感じられます。
夏は炭酸で割って「黒霧ハイボール」も爽やかでおすすめ。
食中酒としても万能で、和食はもちろん、焼肉、中華、イタリアンにも合います。
Q3:「黒霧島の日」はどう過ごせばいい?
まずは、黒霧島を用意しましょう。
おつまみは、焼き鳥、刺身、麻婆豆腐、揚げ物、何でもOK。
友人と一緒に楽しむもよし、ひとりでゆっくり味わうのも良し。
SNSで「#黒霧島の日」をつけて、お気に入りの飲み方や料理とのペアリングを投稿するのも楽しいですね。
また、父の日や敬老の日の贈り物として黒霧島を選ぶ人も多く、この日をきっかけにプレゼント需要も高まっています。
黒霧島の日をもっと楽しむために
実は、霧島酒造ではこの「黒霧島の日」以外にも、焼酎にまつわる記念日を制定しています。
その一つが、「KIRISHIMA No.8の日」。
これは、焼酎の原料となるさつまいもの育種番号「No.8」にちなんで、8月8日に設定されています。
こちらは、霧島酒造の“さつまいも愛”を感じる記念日。
このように、霧島酒造は単なる酒造メーカーではなく、焼酎文化を未来に残そうとしているブランドだと言えます。
黒霧島の日のまとめ
「黒霧島の日」(9月6日)は、焼酎を愛する人々にとっての“年に一度の祭り”。
九州の風土が育てた素材。
100年以上続く蔵元の技術。
黒麹のコクと、霧島裂罅水のまろやかさ。
すべてが一体となって生まれた「黒霧島」は、日本が誇る“本格芋焼酎”です。
そしてこの記念日は、そんな「黒霧島」をもっと多くの人に知ってもらい、楽しんでもらうための日。
一杯の焼酎には、土地の恵みと、人の技と、文化が詰まっています。
だからこそ、“今日は特別”という気持ちでグラスを傾けてみてください。
その一杯が、あなたの夜を、少しだけ豊かにしてくれるはずです。
今日は何の日(9月6日は何の日)
妹の日 | クロスワードの日 | まがたまの日(6月9日・9月6日) | 黒の日(黒染め) | 黒の日・クロイサの日 | 鹿児島黒牛・黒豚の日 | 黒豆の日 | キョロちゃんの日(森永チョコボールの日) | ソフティモ・黒パックの日 | 黒酢の日 | クレームの日 | 黒い真珠 三次ピオーネの日 | クロレラの日 | シェリーの日 | 甲斐の銘菓「くろ玉」の日 | スマートストックの日(3月6日・9月6日) | 黒あめの日 | 9696(クログロ)の日 | 松崎しげるの日 | カラスの日 | 浅田飴の日 | 生クリームの日 | 黒にんにくの日 | クルージングの日 | クロレッツの日 | MBSラジオの日 | スポーツボランティアの日 | 回転レストランの日 | 飴の日 | Dcollection・黒スキニーの日 | のどぐろ感謝の日 | スライドシャフトの日 | クロコくんの日 | クロモジの日 | 黒霧島の日 | へべすの日 | ブラックウルフ・黒髪の日 | 黒舞茸の日 | 岩室温泉・黒湯の日 | ぐるぐるグルコサミンの日 | ブラックサンダーの日 | X-BLEND CURRYの日 | ピカールのクロワッサンの日 | モノマネを楽しむ日 | 手巻きロールケーキの日(毎月6日) | メロンの日(毎月6日) | 歯ヂカラ探究月間(9月1日~30日)