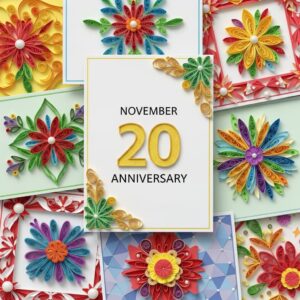毛皮の日(11月20日)はどんな日?
✅ 「毛皮の日」は、1989年に一般社団法人「日本毛皮協会(JFA)」が制定した、毛皮(fur)という素材・文化に着目した記念日です。
✅ 日付は「いい(11)フ(2)ァー(輪=0)」という語呂合わせから“11月20日”に定められ、毛皮の需要促進・素材理解を目的としています。
✅ 関わる団体は「日本毛皮協会(JFA)」で、毛皮産業の調査研究・情報提供・ファーデザインコンテスト・毛皮鑑定などを通じて、素材としての毛皮文化を支えています。
11月20日――この日を耳にしたとき、ふと「毛皮?」と首を傾げる人も多いかもしれません。
けれどもこの「毛皮の日」は、ただの語呂合わせ記念日ではありません。防寒具としてだけではなく、素材として、ファッションとして、そして文化・産業としての視点から“毛皮”という存在を改めて見直すために設けられた日です。
厚手のコートに身を包んだ昔の映画スターのイメージや、寒冷地で必需だった毛皮の活用……そんな背景を知ると、毛皮は単なる贅沢品ではなく、人間の営みと密接に関わってきた“素材の物語”であることが見えてきます。
いま一度、11月20日を機に「毛皮って何だろう?」「どんな歴史を持っているんだろう?」と気軽に眺めてみるのも、興味深い時間になるでしょう。
この記事では、「毛皮の日」の由来を丁寧に解説したうえで、毛皮にまつわる歴史・豆知識・関係者紹介・よくある疑問といった構成でお届けします。
素材好きな方、ファッションに少し関心のある方、あるいは「ちょっと調べてみようかな」と思った方にも、“なるほど”“話したくなる”そんな発見を含めてお伝えします。
では、早速その世界へ一歩足を踏み入れてみましょう。
「毛皮の日(11月20日)」の由来と背景
「毛皮の日」がなぜ11月20日に、そしてなぜ制定されたのか。そこには素材への思いと、産業界の戦略が交差しています。
1989年(昭和64年/平成元年)に、東京都中央区日本橋兜町に事務局を置く一般社団法人「日本毛皮協会(JFA)」がこの日を制定しました。会員には毛皮専業者が名を連ね、毛皮産業の活性化を目的としています。
日付が“11月20日”になったのは、「いい(11)フ(2)ァー(輪=0)」という語呂合わせが決め手でした。英語で「fur(ファー)」=毛皮。つまり「いいファー(いい毛皮)」「輪=0」で「11‑2‑0」という風に。そこに親しみと覚えやすさを込めたわけです。
また、11月という時期にも意味があります。秋の深まりとともに気温が下がり、防寒具として毛皮の需要が高まる季節の“入り口”であるからこそ、毛皮という素材を改めて注目させるには好タイミングだったと言えます。
さらに、この記念日の制定には「素材そのものを知ってほしい」「毛皮という文化的資源を大切にしてほしい」という協会の思いも込められています。
つまり、“ただ売る記念日”ではなく、“知るきっかけ”として機能する日。それが毛皮の日の裏側にあるモチベーションです。
このように、記念日という枠を超えて、素材・産業・文化をつなぐ役割を果たしているのが「毛皮の日」の由来と言えます。
「毛皮の日(11月20日)」にまつわる豆知識
毛皮という言葉を聞くと、暖かそう/贅沢そうというイメージが浮かびがちですが、実はその裏には長い時間をかけた人類と素材の関わりや、社会・文化・環境の変化が隠れています。ここでは、毛皮にまつわる興味深いトピックスをいくつかご紹介します。
まず、毛皮とは何か。専門的には「体毛がついたままの獣皮」を指します。本物の動物の毛皮を「リアルファー(real fur)」と呼び、動物の毛皮を使わずに繊維・合成素材で“毛皮のように見せたもの”を「フェイクファー(fake fur)」や「エコファー(eco‑fur)」といいます。
人類が毛皮を活用し始めたのは旧石器時代、狩猟を行い、動物を食用とし、その毛皮を衣服・防寒具として使っていたと考えられています。日本でも旧石器時代の遺跡から毛皮の痕跡が発見されており、素材としての毛皮は“人間が寒さと戦うための道具”でもありました。
また、毛皮は単なる“暖を取る素材”だけでなく、地域・時代・社会的地位を映す“シンボル”にもなりました。たとえばヨーロッパ中世では、高級な毛皮、特にテンやセーブルなどを貴族や王族が身に着けることがステータスでした。身分の低い者が一定の毛皮を着ることを禁じられたという法律もあったほどです。
さらに面白いエピソードとして、童話のシンデレラのお話があります。一般に「ガラスの靴」として語られていますが、原話では“毛皮の靴”だったという説もあります。「verre(毛皮)」が「verre(ガラス)」と誤訳されたという伝承があり、もしそれが事実なら、かつて毛皮が身近で特別な素材だったことを象徴しています。
現代に目を向けると、毛皮に対する見方も変化しています。動物愛護・環境保護・倫理の観点から、毛皮の使用を控える動きが広がり、代替素材としてフェイクファーやリサイクルファー、さらには動物を使わない毛皮調素材が注目されています。また、毛皮用動物養殖の問題や流通の透明性確保なども議論の対象です。
こうした流れをふまえて、毛皮の日というのは「昔はこうだった」「今はこう動いている」という“時間軸”を感じながら、自分の視点で毛皮を見直す機会にもなります。
素材を知ることで、ファッション・文化・産業に新たな視点が生まれ、話題になること間違いなしです。
「毛皮の日(11月20日)」と関わる人物・団体・産業
この記念日に深くかかわるのは、まず前述の一般社団法人「日本毛皮協会(JFA)」です。所在地は東京都中央区日本橋兜町。JFAは会員として毛皮専業者を抱え、毛皮産業全体の調査研究、情報収集・提供、素材価値の向上を目的に活動しています。
具体的には、“毛皮とは何か”“どうやって流通してきたか”“今どんな技術・デザインが出てきているか”というテーマを扱い、毛皮の鑑定、そして「ファーデザインコンテスト」の開催なども行っています。こうした活動を通じて、毛皮という素材を認知・理解・評価する仕組みを設けているのです。
産業という観点から見ると、毛皮は卸業・縫製業・流通業・デザイン業など多岐にわたる産業と繋がっています。日本国内では、昭和・平成時代にかけて女性用毛皮コートや襟巻き・ショールなどが人気を博し、冬のファッションアイテムとして定着していました。例えば、皇室・王室の儀礼的行事などで、ミンクのストールなどが注目された時代もあります。
加えて、素材という面では、ヒグマ・キツネ・テン・イタチ・ヒツジ・イヌ・ネコ・トナカイ・ミンク・ムササビ・チンチラ・アザラシ・ラッコ・カワウソ・ビーバーなどが、毛皮として人類に使われてきた動物の代表例として列挙されます。
ただし、近年は“素材のあり方”“動物との関係”という倫理・環境的な視点も加わっており、毛皮産業においても「リサイクル毛皮」「フェイクファー」「サステナブル素材」などを模索する動きが活発です。
つまり、毛皮の日は単に“毛皮を売り出す”日ではなく、協会を中心に「素材を理解する」「産業を知る」「文化として捉える」ための1日となっているのです。そして、読者自身が「この素材ってどんな価値を持っているんだろう?」と考えるきっかけとなるように設計された日とも言えます。
「毛皮の日(11月20日)」に関するよくある質問
Q1:この記念日は誰が、なぜ制定したのですか?
A1:この日は、毛皮という素材や産業を広く知ってもらうため、1989年に一般社団法人「日本毛皮協会(JFA)」が制定しました。日付の由来は語呂合わせ「いい(11)フ(2)ァー(輪=0)」=11月20日です。制定の
背景には、毛皮産業の振興・素材の価値向上・消費者理解の促進という目的がありました。つまり、「今まで素材として気にしたことがない」という人にも、毛皮という存在を“知る”機会にしようという思いがあります。
また、この時期(11月)は冬に向けて防寒具への関心が高まる季節でもあり、毛皮の出番が近づくタイミングとしても適していました。
このように、“目的=素材理解”“タイミング=需要の向上”という2つの視点で制定された記念日です。
Q2:毛皮とフェイクファー、どちらが良いの?あるいは今はどう考えるべき?
A2:まず、リアルファー(動物の毛皮)とフェイクファー(合成素材等)は、それぞれに特徴があります。リアルファーは、その動物の体毛・皮をそのまま活かした素材で、暖かさ・質感・希少性などにおいて伝統的な価値を持ちます。
方、フェイクファーは動物を使わずに作られるため、動物福祉・環境・価格という視点から支持が広まっています。
ただし「どちらが良いか」は一概には言えません。時代や価値観が変化しており、たとえば「動物由来素材をできるだけ避けたい」「サステナブルな素材を選びたい」と考える人にはフェイクファーが適しています。
一方で、「リアルファーという素材の歴史・手仕事・希少性を味わいたい」という人にはリアルファーの魅力があります。
重要なのは、「素材について自分がどう考えるか」を持つことです。毛皮の日を機に、「この素材を私はどう捉えるのか」という問いを立てること自体が、大切な第一歩となります。
Q3:毛皮の日をどう活用したら良い?家族・友人・自分自身で楽しむには?
A3:毛皮の日を活用する方法は意外と多様です。例えば、冬物コートを探している人なら「毛皮を使ったデザイン」「フェイクファーを使った代替素材」の違いを比べてみるのも楽しいです。また、ファッションに興味のある人なら「毛皮がどのように取り入れられてきたか」「素材が持つ意味」について会話材料にできます。
家族や友人との話題にしたいなら、「このコート、実は素材が毛皮なんだよ」「フェイクファーでも最近質が上がってるんだって」といった軽い会話から入ると抵抗が少ないです。子どもと一緒なら「昔はどんな防寒具を使ってたのかな?毛皮ってどんな素材だろう?」とクイズ形式で話すのも盛り上がります。
さらに、毛皮にまつわる展示や資料を探して、地域や美術館・博物館で“素材の変遷”を観る機会を作るのもおすすめです。記念日にちなんで「素材を知る1日」にしてみると、日常に少し豊かさが加わります。
「毛皮の日(11月20日)」まとめ
「毛皮の日(11月20日)」は、「いい(11)フ(2)ァー(輪=0)」という語呂合わせから、1989年に一般社団法人「日本毛皮協会(JFA)」が制定した記念日です。毛皮という素材を、“防寒具”としてだけではなく、“文化・素材・産業”という視点から再び見直すきっかけとして位置づけられています。
人類が旧石器時代から毛皮を活用してきた歴史や、ヨーロッパの貴族文化における毛皮の位置づけ、そして現代において動物福祉・環境・代替素材という観点から毛皮の価値観が変わってきているという流れ――こうした流れを知ることで、素材をただ消費するだけではなく、意味を理解して選ぶことができます。
“素材を知る楽しさ”をこの記念日は教えてくれます。友人との会話のきっかけにも、「あ、11月20日は毛皮の日なんだよ」と使ってみてください。素材にちょっと詳しくなると、冬のファッションも、ちょっと違った視点から楽しめるはずです。
あなたもこの11月20日を、「毛皮」というひとつの素材を通じて、過去・現在・未来を少し旅する1日にしてみませんか?それでは、良き毛皮の日を。