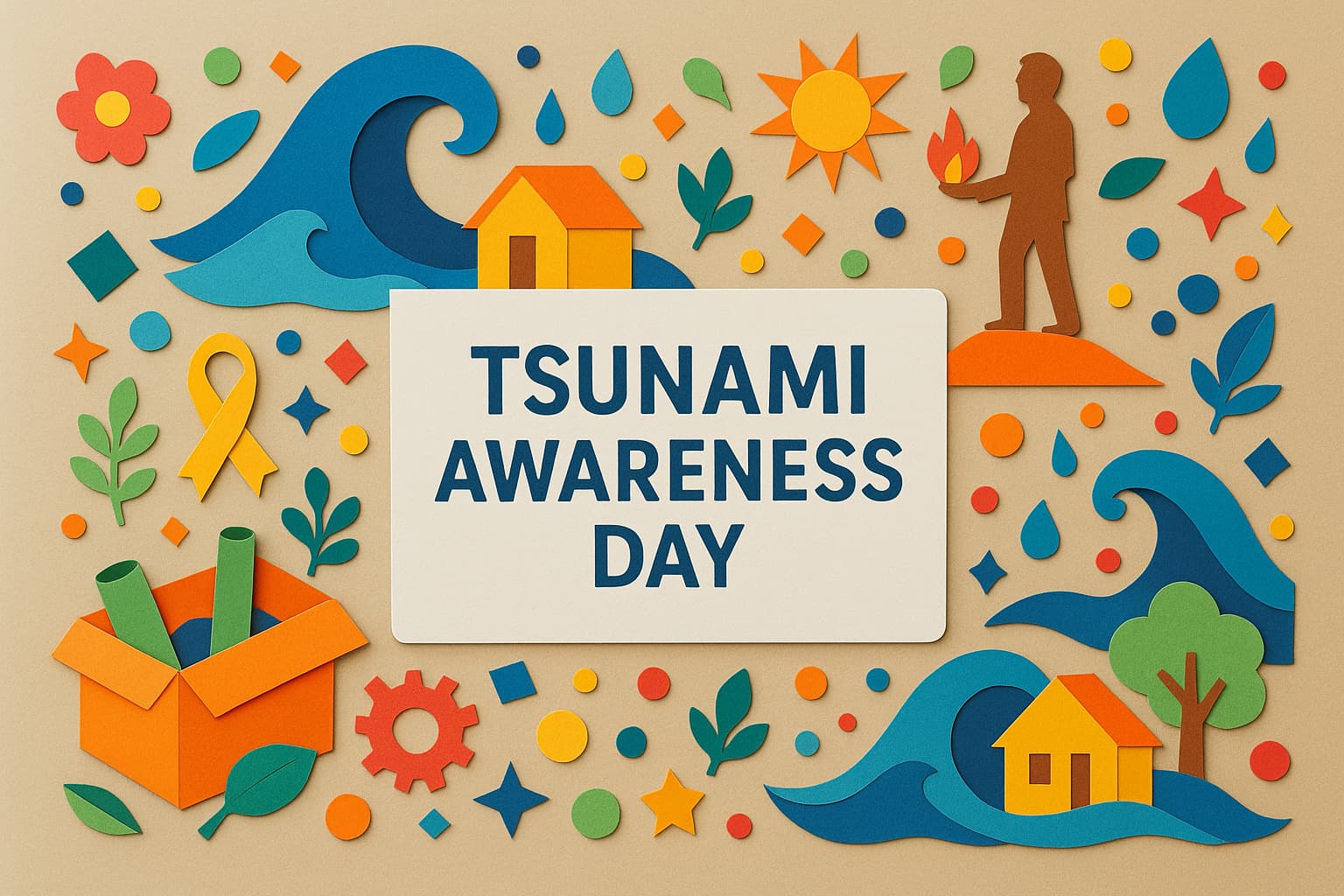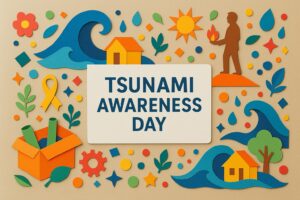津波防災の日(11月5日 記念日)はどんな日?
✅ 「稲むらの火」の逸話に基づき、津波から命を守る意識を高めるための日。
✅ 安政南海地震と濱口梧陵の防災行動に由来し、津波避難の重要性を伝えている。
✅ 濱口梧陵と一般社団法人・日本記念日協会、国連が関わっている。
命を守る知恵をつなぐ記念日「津波防災の日」
「津波防災の日(11月5日)」は、単なる記念日ではありません。
それは、過去の悲劇と勇気を未来につなぐための「教訓の日」です。
2011年3月11日に発生した東日本大震災は、我が国に深い爪痕を残しました。
そしてそのわずか3ヶ月後、私たちは未来の命を守るための新しい一歩を踏み出しました。
それが、「津波防災の日」の制定です。
震災の記憶が生々しい中で、この記念日は過去のもう一つの大津波——1854年の安政南海地震に立ち返ることで誕生しました。
暗闇の中、収穫したばかりの稲むらに火を灯し、命を守った男の話をご存じでしょうか?
その名も、濱口梧陵。彼の行動は今も語り継がれ、「稲むらの火」として人々に防災の大切さを教えています。
この記念日は、毎年11月5日に設定され、学校や地域で防災訓練が行われるなど、命を守る行動のきっかけとなっています。
私たちの未来の命は、今日の「備え」にかかっています。
ここでは、「津波防災の日」の意味や由来、そして私たちが学ぶべきことを詳しく解説していきます。
津波防災の日の由来は「稲むらの火」と安政南海地震
「津波防災の日」が11月5日に制定された背景には、歴史的な大地震と、それに立ち向かった人々の姿があります。
それは、1854年11月5日(旧暦嘉永7年)、紀伊半島を中心に発生した「安政南海地震」。
この地震により、和歌山県の広村(現在の広川町)をはじめ、四国や近畿一帯が壊滅的な津波の被害を受けました。
この未曽有の災害の中、村人たちの命を救った一人の人物がいます。
彼の名は、庄屋・濱口梧陵。
地震発生後の夜、津波が襲来し逃げ遅れる村人たちがいたことに気づいた彼は、なんと自分の田んぼに積まれた「稲むら(稲わらの束)」に火をつけます。
暗闇の中で輝くその炎を目印に、村人たちは高台へと避難し、命を救われたのです。
この勇敢な行動は「稲むらの火」として伝説となり、今も防災教育の重要な教材となっています。
津波防災の日が3月11日ではなく、11月5日になったのは、東日本大震災の被災者への配慮からです。
震災直後に記念日を設けることは心情的に重く、多くの議論を経て「稲むらの火」にちなむこの日が選ばれました。
つまり、津波防災の日は単なる記念日ではなく、「過去の知恵を未来につなぐ」ための象徴なのです。
津波防災の日に学ぶ防災の豆知識と意義
津波防災の日には、毎年全国で防災訓練や避難訓練、講演会、防災教育のイベントが開催されます。
その目的は明確です。
「津波による被害から国民の生命・身体・財産を保護すること」
そして、「津波防災の意識を社会全体で高めること」です。
特に教育現場では、「稲むらの火」の物語を題材とした紙芝居やマンガが活用され、小中学校でも積極的に取り入れられています。
この物語を通じて、子どもたちは「自ら考え、判断し、行動する力」を養うことができるのです。
また、「津波警報」が出たときにどう動くべきか、避難のタイミングやルートの確認、防災グッズの準備など、家庭での意識改革にもつながります。
さらに、この日は国連が定める「世界津波の日(World Tsunami Awareness Day)」とも重なっています。
日本の提案により2015年に国連総会で採択されたこの国際デーは、津波による犠牲者を世界規模で減らすための啓発活動が目的です。
つまり、11月5日は日本だけでなく、世界中が「津波から命を守る」ことを考える日でもあるのです。
津波防災の日にゆかりのある人物・団体とは?
「津波防災の日」に欠かせない人物といえば、何といっても濱口梧陵です。
彼は単なる庄屋ではなく、後に実業家、そして教育者としても活躍し、社会に大きな貢献を果たしました。
津波の後、彼は村の復興に尽力し、堤防を築き、雇用を生み出すなど、地域全体の再生を支えました。
まさに現代で言う「防災と共助のリーダー」といえる存在です。
また、この記念日は「日本記念日協会」により正式に認定・登録されており、行政や教育機関とも連携して全国で普及活動が行われています。
さらに、国連が定めた「世界津波の日」としての側面も持ち、国際連合やUNESCO、国際防災戦略事務局(UNDRR)などの国際機関もこの日を重視しています。
つまり、津波防災の日は、地域社会、教育界、政府、そして国際社会が一体となって「命を守る知恵」を共有する重要な機会なのです。
津波防災の日に関するよくある質問
Q1:津波防災の日には何が行われるの?
A:全国各地で避難訓練、防災講演、防災教育のイベントなどが実施されます。学校や自治体が中心となって計画され、命を守る行動の確認が行われます。
Q2:「稲むらの火」の物語はどこで読めるの?
A:多くの学校の教科書に掲載されているほか、防災館や図書館、市販の絵本、紙芝居、マンガでも紹介されています。
Q3:なぜ11月5日が選ばれたの?
A:東日本大震災の被災者への配慮から、1854年の安政南海地震にちなむ日として「稲むらの火」の逸話があった11月5日が選ばれました。
津波防災の日は命をつなぐ行動のスタートライン
「津波防災の日(11月5日)」は、単なる記念日ではなく、私たち一人ひとりが「命を守る行動」を見直す日です。
1854年の安政南海地震から、2011年の東日本大震災、そして未来へ。
防災の知恵と勇気は、時代を超えて受け継がれています。
もし今、あなたの地域で津波が起きたらどうしますか?
備えは十分でしょうか?家族で話し合ったことはありますか?
この記念日をきっかけに、「考えること」「行動すること」「伝えること」を始めてみてください。