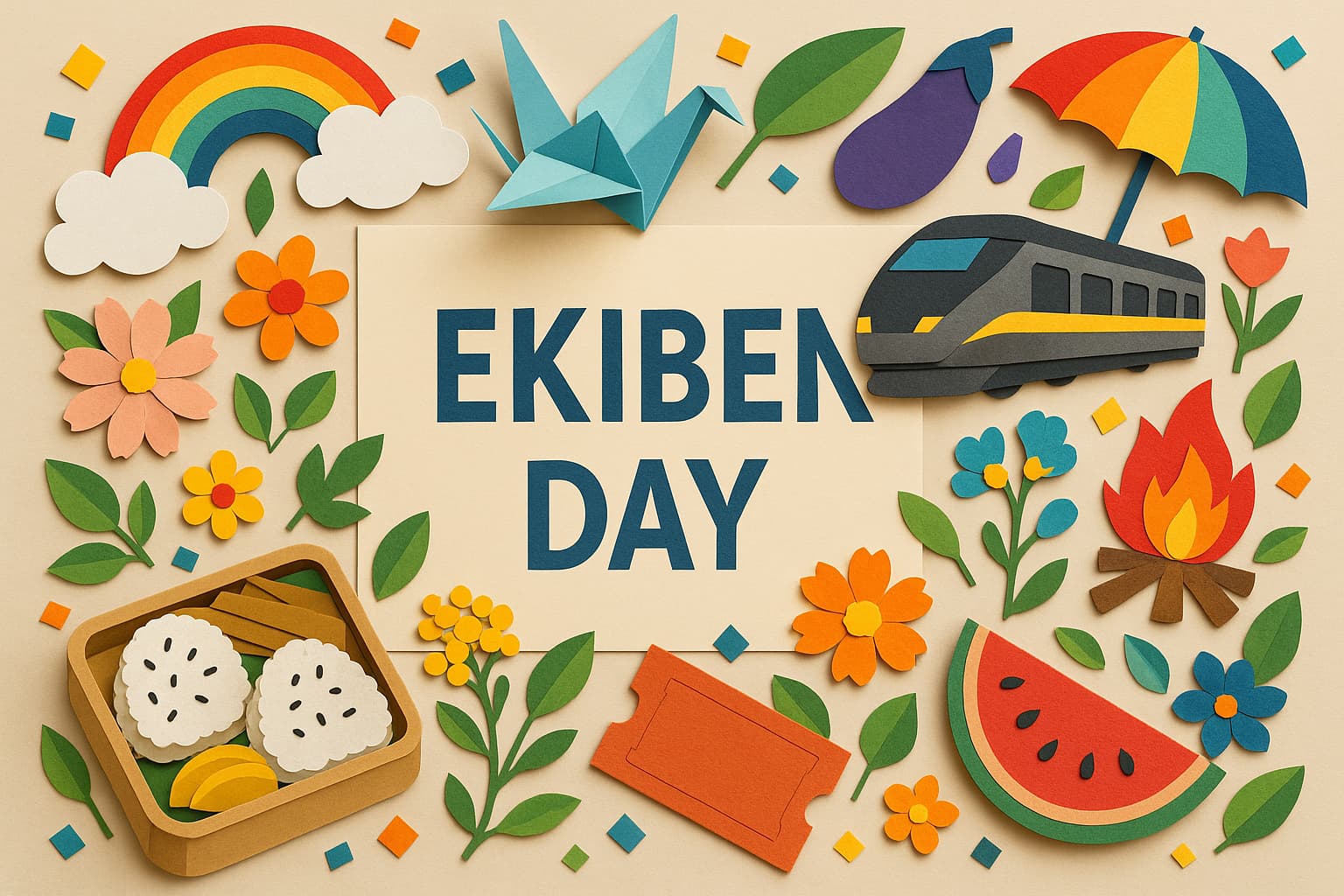旅の風景を包んだ一膳の物語――駅弁のルーツをたどる日
列車の窓から眺める流れる風景。
駅に着くたびに流れるアナウンスと、人のざわめき。
その瞬間、ふと食べたくなるのが「駅弁」ではないでしょうか。
誰もが一度は旅の途中に買ったあの一膳。
風景とともに記憶に残る、特別な味。
そんな「駅弁」が、初めて世に登場したとされるのが、1885年(明治18年)7月16日。
今から140年近く前、宇都宮駅で日本初の駅弁が売られたこの日は、「駅弁記念日」として制定されています。
この記事では、駅弁記念日の誕生の背景、駅弁のはじまりにまつわるストーリー、そしてちょっと得する豆知識や人物のドラマなど、あなたがつい誰かに話したくなる情報を、じっくり丁寧にご紹介します。
読み終わる頃には、次に駅で駅弁を買うとき、あなたの目がちょっと違って見えるはずです。
✅ 宇都宮駅で誕生した日本初の駅弁
✅ 発案者は旅館の主人・白木屋嘉平
✅ 素朴ながらも旅情をかき立てる握り飯
駅弁記念日はどんな日?〜その由来と背景〜
1885年7月16日。
この日は、日本鉄道東北線(現在のJR東北本線)の大宮駅〜宇都宮駅間が開通した記念すべき日です。
鉄道の発展は、物流や人の移動に革命をもたらしましたが、それと同時に“新しい食文化”も生まれました。
その代表格が「駅弁」です。
この日、宇都宮駅で販売されたのが、梅干し入りのおにぎり2個とたくあん2切れ。
それらを竹皮で包み、5銭という当時ではやや高めの価格で売られました。
これを考案・販売したのが、宇都宮市内で旅館「白木屋」を営んでいた白木屋嘉平(しらきや かへい)です。
当日、彼の宿に宿泊していた日本鉄道の重役から「旅人に弁当を出してみては?」と提案を受けたことがきっかけでした。
まさにその場の閃きと、嘉平の行動力が、のちの駅弁文化の礎となったのです。
宇都宮駅は「駅弁発祥の地」として名乗りをあげ、今では記念碑も建立されています。
ただし、厳密にはその前から弁当が販売されていた駅もあるとの記録も残っており、「日本初」の称号には諸説あります。
それでも、7月16日は「駅弁記念日」として正式に記念日として採用され、駅弁文化を讃える日となっています。
駅弁記念日の豆知識!「知ってると語れる」3つのトリビア
①竹皮に包む理由は?
現在のようなプラスチック容器がなかった時代、駅弁の包装には「竹の皮」が使われていました。
これは抗菌作用があり、夏場でも傷みにくく、通気性もあるという優れた自然素材です。
また、ほんのりと漂う竹の香りが食欲をそそる、という口コミも多く、今でも一部の駅弁であえて竹皮包装が使われています。
旅情を感じたい人には人気のアイテムです。
②「5銭」は現代でいくら?
当時の5銭は、現代の価値にして約1,000円前後とも言われています。
庶民が気軽に買える値段ではなかったことからも、初期の駅弁は「旅の贅沢品」という位置づけだったようです。
③ 駅弁記念日と駅弁の日の違い
7月16日は「駅弁記念日」ですが、4月10日は「駅弁の日」とされています。
この4月10日は、数字の「4(し)10(とう)」を「弁当(べんとう)」の語呂合わせで制定されたもので、全国駅弁大会などのイベントが行われる日です。
「記念日」は歴史的由来に基づいたもので、「駅弁の日」はプロモーション的な記念日、という違いがあります。
この後の章では、白木屋嘉平の人物像や、駅弁にまつわるエピソード、よくある質問、そしてその他の記念日も一緒に
駅弁記念日に登場するキーパーソンたちのドラマ
白木屋嘉平(しらきや かへい)――駅弁文化を創った男
駅弁記念日の象徴的な人物、それが白木屋嘉平です。
彼は明治時代、栃木県宇都宮市で旅館「白木屋」を営んでいました。
宿に泊まりに来たのは、たまたま鉄道会社の重役たち。
彼らが話す「駅で食べ物を売れたら便利なのに」という雑談を、嘉平は聞き逃しませんでした。
この一言にピンときた嘉平は、翌日には駅に出向き、旅人のための「弁当」を販売。
これが、駅弁のはじまりとされています。
重要なのは、彼が単に宿を経営するだけの人物ではなく、チャンスを見つけ、行動に移したその“実行力”と“柔軟な発想力”。
鉄道が旅を加速させる時代の流れを敏感に感じ取り、自らの商売に取り入れたその姿勢は、現代のビジネスにも通じる先見性を感じさせます。
宇都宮駅――鉄道文化と共に歩む発祥の地
白木屋嘉平が初めて駅弁を販売したのが、現在のJR宇都宮駅。
宇都宮駅では、「駅弁発祥の地」としての誇りを今も大切にしています。
駅前には記念碑が設置され、観光客にとっての「撮影スポット」となっているほか、地元で販売される駅弁は、そのルーツにちなんで竹皮に包まれているものもあります。
この“原点”を体感できるのは、やはり宇都宮ならでは。
鉄道と食の文化が交差する、貴重なスポットです。
駅弁記念日にまつわるよくある質問
Q. 駅弁ってどの駅が一番有名なの?
A. 一概には言えませんが、駅弁大会などで人気が高いのは以下の駅です:
- 新潟駅「えび千両ちらし」
- 米沢駅「牛肉どまん中」
- 小田原駅「鯛めし」
- 富山駅「ますのすし」
どれも地元の特産を生かした個性的な駅弁で、旅の目的にもなるほどです。
Q. 駅弁は車内販売がメイン?
A. 昔はホームで買うのが主流でしたが、現在は駅構内の売店やキオスクでの販売が中心です。
一部の新幹線ではワゴン販売も残っていますが、減少傾向にあります。
その分、駅構内の売店では地域色豊かな限定弁当が充実しています。
Q. 駅弁記念日にはイベントがあるの?
A. 大々的な全国イベントは少ないですが、宇都宮駅などでは記念販売やポスター掲示、特別パッケージの弁当が登場することもあります。
また、鉄道ファンの間では「記念日駅弁旅」を計画する人も多いです。
その他の記念日(7月16日)
後の薮入り
盆送り火
閻魔参り・閻魔賽日
国土交通Day
駅弁記念日
外国人力士の日
虹の日
からしの日
長瀞観光の日
ZEPPET STOREの日
夏を色どるネイルの日
トロの日
十六茶の日
いい色髪の日
駅弁記念日のまとめ|次の旅に、駅弁を
駅弁記念日――それは単なる「ごはん」の記念日ではありません。
旅の思い出を包み、誰かのアイデアと行動が生んだ、日本らしい文化の記念日です。
白木屋嘉平の行動力、鉄道開業の勢い、そして旅人たちの“ちょっとした空腹”が交差して誕生した駅弁。
今では当たり前となった駅弁文化ですが、その始まりを知ることで、旅の一瞬一瞬がもっと特別に感じられるはずです。
次に駅で駅弁を手にするとき、思い出してみてください。
140年前の宇都宮駅で、誰かがこの旅の「おいしい楽しみ方」を最初に見つけたことを。
そしてあなたも、その物語の続きに加わるのです。