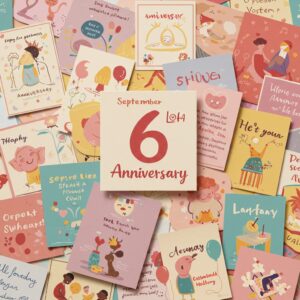【飴の日(9月6日 記念日)】とはどんな日?
✅ 飴の日(松本飴プロジェクト制定)は、古代の日本書紀に飴作りの記述があることから9月6日に制定された記念日。
✅ 飴の日の由来は、神武天皇の記述に基づき、飴がこの日に作られたと考えられる点から。
✅ 老舗飴屋「山屋御飴所」「新橋屋飴店」「飯田屋製菓」が結成した松本飴プロジェクトが制定し、日本記念日協会が認定した。
飴文化を未来へつなぐ記念日――飴の日(9月6日)
口に入れた瞬間、じんわりと広がる甘さ。
どこか懐かしくて、やさしくて、心が和む。
そんな飴に、実は「記念日」があるのをご存知でしょうか?
それが、「飴の日(9月6日)」です。
この記念日は、長野県松本市の老舗飴店三軒が結成した「松本飴プロジェクト」が、飴文化の継承と発展を願って制定しました。
背景には、日本最古の歴史書『日本書紀』に残る、飴作りの記述があります。
「飴の日」は、古代から続く日本の飴文化を再発見し、その魅力を次の世代へ伝えるための、大切な一日なのです。
飴の日(9月6日 記念日)の由来は“日本書紀”にあり
飴の日の起源は、なんと奈良時代に編纂された歴史書『日本書紀』にあります。
『日本書紀』の「神武天皇記」には、ある日、神武天皇が「飴」を口にしたとされる場面が描かれています。
この記述から、古代日本ではすでに飴のような甘味が存在していたと推察されています。
記述があるのは、現在の暦に換算して「9月6日」。
これが、「飴の日」の日付の由来となっています。
ただし、「飴」といっても、現代のキャンディのようなものではなく、当時はお米を発酵させて作る「米飴(こめあめ)」のような自然由来の甘味料でした。
こうした歴史的背景を持つことから、飴は単なるお菓子ではなく、日本の食文化に深く根ざした存在だといえるのです。
この記念日は、令和元年(2019年)に、日本記念日協会により正式に登録・認定されました。
飴の日(9月6日)と松本市の深い関係
飴の日を語る上で欠かせないのが、「飴の街」とも呼ばれる長野県松本市です。
松本市は、江戸時代から飴づくりが盛んな地域でした。
特に注目すべきは、松本の気候と自然環境です。
乾燥した気候、湧き出る清らかな水、そして安曇野で採れる良質なお米。
これらの条件が揃ったことで、米飴の生産に最適な土地として知られるようになりました。
この伝統を守り続けているのが、以下の三軒の老舗飴店です:
- 山屋御飴所(やまやおんあめどころ)
- 有限会社 新橋屋飴店(しんばしやあめてん)
- 有限会社 飯田屋製菓(いいだやせいか)
これら三軒が立ち上げたのが「松本飴プロジェクト」。
「飴文化を、次の100年へつなぐ。」
このスローガンのもと、地域とともに飴文化を広める活動を続けています。
飴作り体験イベント、観光客向けのワークショップ、地元学校とのコラボなど、活動の幅は広がっています。
米飴とは?――自然が生んだ、素朴で優しい甘さ
米飴とは、お米や麦芽などの穀物を原料として作られる、日本古来の天然甘味料です。
砂糖が普及する前の時代には、貴重な甘味料として重宝されていました。
特徴は、何といってもその優しい甘さ。
口に含んだときに広がる穏やかな味わいは、現代の甘味料にはない魅力があります。
松本の飴職人たちは、この米飴を今でも大切に使い続けています。
職人の手でじっくり煮詰め、素材の風味を生かした飴を作り出す。
その姿は、まるで工芸品を生み出すかのようなこだわりに満ちています。
そして、その味には“時代を超えて受け継がれる温もり”が込められているのです。
飴の歴史をひもとく――なぜ日本人は飴に惹かれるのか?
飴の歴史は非常に古く、『日本書紀』にその記述が見られるように、奈良時代にはすでに存在していたと考えられています。
平安・鎌倉時代には、仏教の影響で砂糖の代用品として使われ、江戸時代には庶民のお菓子として屋台などで普及しました。
特に江戸時代後期になると「金太郎飴」や「べっこう飴」「飴細工」などが登場し、娯楽と芸術の要素を含んだ飴文化が栄えました。
明治以降は、西洋のキャンディ文化が流入しながらも、日本の飴は独自の進化を遂げ、今も全国各地にさまざまな伝統飴が残っています。
全国の飴文化との比較――飴の魅力は松本だけじゃない!
松本の米飴は素朴で優しい味が特徴ですが、日本各地にも個性豊かな飴文化があります。
東京・浅草では「べっこう飴」や「飴細工」。
大阪では「金太郎飴」。
福岡では「黒糖飴」、北海道では「ハッカ飴」。
それぞれがその土地の気候・風土・食文化に根ざした飴であり、いずれも“職人の技”が活きています。
飴は、日本全国で愛されてきた“地域文化”の象徴でもあるのです。
飴と健康の関係――適量なら味方になる甘さ
「飴は体に悪い」というイメージがあるかもしれませんが、実は上手に取り入れることで、健康にも役立ちます。
特に米飴や黒糖飴のような自然由来の飴は、精製された白砂糖に比べて血糖値の上昇が緩やか。
登山やスポーツ時のエネルギー補給にも適しており、携帯性も抜群です。
また、喉の不調時にはハーブ入りの飴や、プロポリスを配合した「のど飴」が役立つなど、用途に応じた機能性飴も多く存在します。
“甘さ”を味方につけるためにも、選び方と食べ方に気を配りましょう。
飴の日をもっと楽しむ5つのアイデア
- 全国の飴を食べ比べてみる
松本の米飴、浅草のべっこう飴、大阪の金太郎飴などを揃えて“飴旅気分”。 - 飴作り体験に参加する
松本では予約制で体験可能な工房もあり、親子で楽しめます。 - SNSで「#飴の日」を発信
お気に入りの飴や思い出を投稿して飴文化を広めよう。 - おばあちゃんと飴の思い出を語る
世代を超えた飴の記憶は、意外な物語に満ちています。 - 飴をギフトにする
米飴の詰め合わせは、手土産やちょっとした贈り物にも最適。
飴の日(9月6日)に関するよくある質問
Q1:飴の日はいつできた?
A1:令和元年(2019年)に日本記念日協会により認定されました。
Q2:なぜ9月6日なの?
A2:『日本書紀』の神武天皇記にこの日に飴を作ったという記述があることに由来します。
Q3:どこで米飴を買えるの?
A3:松本市の山屋御飴所、新橋屋飴店、飯田屋製菓で購入可能。通販対応もあり。
Q4:飴の日には何をするの?
A4:飴作り体験、食べ比べ、SNS投稿などで飴文化を楽しむのがおすすめです。
Q5:飴の保存方法は?
A5:高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温保存がおすすめです。
飴の日(9月6日 記念日)のまとめ
飴は、ただの甘いお菓子ではありません。
それは、古代から現代まで続く「文化」であり、「人の想いが詰まった一粒」です。
松本の老舗飴屋たちが伝統を守り続け、飴の街として文化を広めようとしている姿勢。
『日本書紀』に記された飴の記憶が、現代に息づいている事実。
そして、飴が誰かの記憶をそっと呼び起こすその力。
飴の日をきっかけに、自分の中にある「甘い思い出」に触れてみてください。
きっとあなたの人生にも、飴のようにじんわりと温かい記憶が残っているはずです。
今日は何の日(9月6日は何の日)
妹の日 | クロスワードの日 | まがたまの日(6月9日・9月6日) | 黒の日(黒染め) | 黒の日・クロイサの日 | 鹿児島黒牛・黒豚の日 | 黒豆の日 | キョロちゃんの日(森永チョコボールの日) | ソフティモ・黒パックの日 | 黒酢の日 | クレームの日 | 黒い真珠 三次ピオーネの日 | クロレラの日 | シェリーの日 | 甲斐の銘菓「くろ玉」の日 | スマートストックの日(3月6日・9月6日) | 黒あめの日 | 9696(クログロ)の日 | 松崎しげるの日 | カラスの日 | 浅田飴の日 | 生クリームの日 | 黒にんにくの日 | クルージングの日 | クロレッツの日 | MBSラジオの日 | スポーツボランティアの日 | 回転レストランの日 | 飴の日 | Dcollection・黒スキニーの日 | のどぐろ感謝の日 | スライドシャフトの日 | クロコくんの日 | クロモジの日 | 黒霧島の日 | へべすの日 | ブラックウルフ・黒髪の日 | 黒舞茸の日 | 岩室温泉・黒湯の日 | ぐるぐるグルコサミンの日 | ブラックサンダーの日 | X-BLEND CURRYの日 | ピカールのクロワッサンの日 | モノマネを楽しむ日 | 手巻きロールケーキの日(毎月6日) | メロンの日(毎月6日) | 歯ヂカラ探究月間(9月1日~30日)