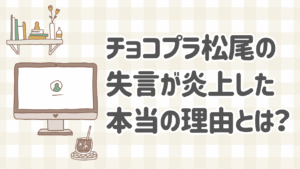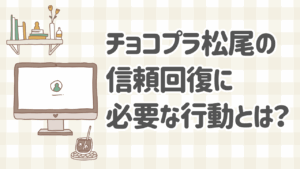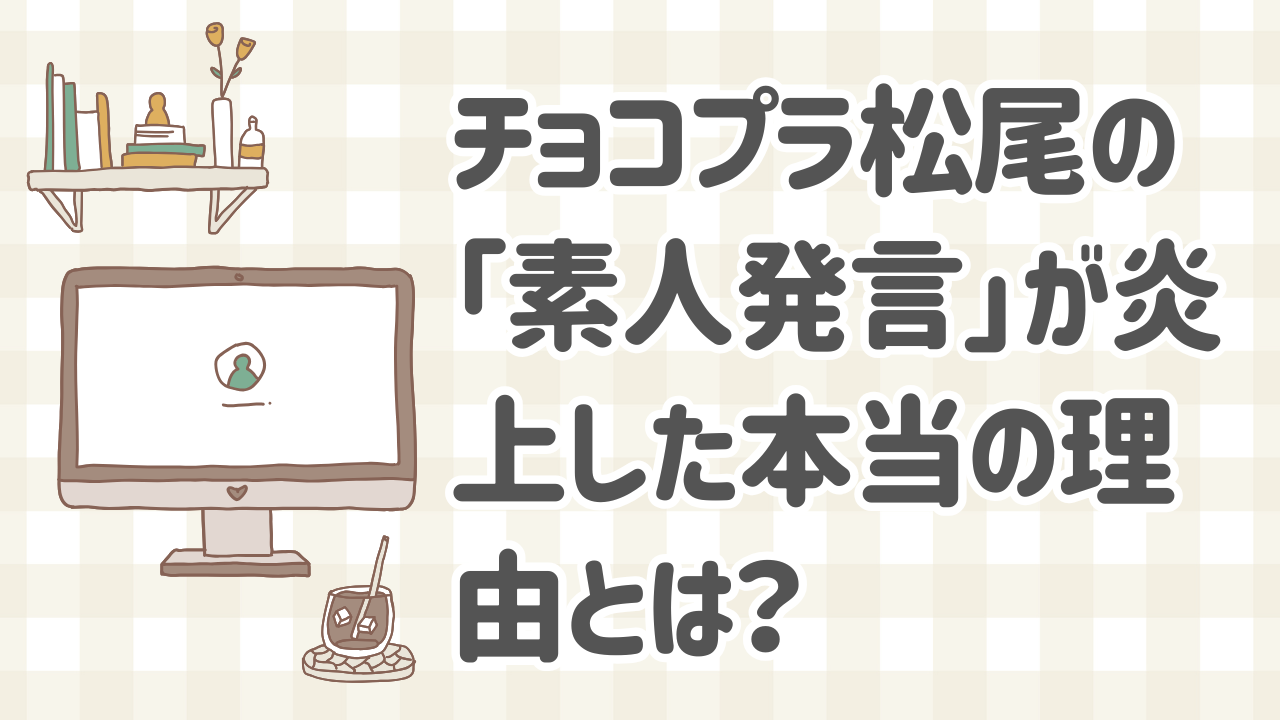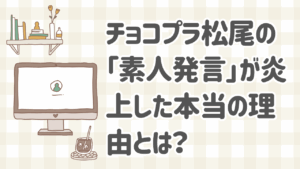ポイント概要
- 松尾駿の「素人はSNSをやるな」発言は、言葉そのもの以上に、発言者と受け手の価値観のズレを露呈したものだった。
- 選民意識と発言の自由、表現者としての責任という3つの焦点が今回の炎上を支えている。
- 身近なユーザーの実感、ファン心理、発信者の立場からの体験が、「一般人」の怒りを具体化した。
- 芸能人と一般人の境界線が曖昧になった今、過去の炎上との比較から、何が新しいのかを把握することが重要。
この炎上は“発信する時代の契約”を問うている
チョコプラ松尾駿さんの発言がこれほどまで大きな反発を招いたのは、ただの“失言”ではない。
それは「誰もが発信者になれる時代」における、発言の自由と表現の責任の新たな契約が、暗黙のうちに社会で成立しつつある証しである。
「発言の自由」は尊重されるべきだが、「発信の自由」が誰のものかを無条件に限定する発言は、契約の一方的な破棄のように受け止められる。
松尾さんの「素人はSNSをやるな」という言葉は、偶発的ではなく、その契約を破るように響いたため、多くの人の怒りと違和感を呼び起こしたのだ。
理由1:言葉の選び方に潜む選民意識と見下し
「素人」という言葉は、日常的には「プロではない人」「専門外の人」という意味で使われる。
だが、言葉の背後には「価値」「権利」「発言の正当性」を測る尺度が暗に存在する。
松尾さんの発言は、発信する人を「芸能人/アスリート」と「それ以外」に分け、後者を制限すべき“素人”と見なすものであった。
この区分が、見下しや上下関係を暗示するものとして受け取られた。
多くの人が、「自分の思いも経験も発信する価値がある」と感じている時代に、その価値を否定されるような言葉は鋭く心に刺さる。
理由2:SNSが築いた「発信の価値観」の変化
SNSはかつて「趣味や交流」の場だったが、今や「自己表現・情報発信・共感の創出」の場である。
普通の人が日常の思いを投稿し、共感を得て、影響を持つことができる。
私が見たある投稿では、数百人のフォロワーしかいない人が、自分の子育ての苦悩や些細な喜びを語ったところ、同じ境遇の人から「わかる」「ありがとう」という反応が数多くついていた。
その投稿者は「プロ」ではないが、その言葉が誰かを励ましたのである。
こうした体験を持つユーザーは、自分を“発信者”として受け止めてもらいたいと願っている。
だから、「素人だから黙っていろ」と言われることは、その尊厳を奪われたように感じるのだ。
理由3:期待とのギャップとファンの裏切られ感
ファンは、好きな芸人に対して「共感」「癒やし」「身近さ」を求める。
チョコレートプラネットは、テレビやネット番組での軽妙なやりとりや、視聴者に寄り添ったネタで「芸能人だけど近い存在」「笑いの中の共通点を持つ存在」と感じられてきた。
私自身も、彼らがYouTubeで「何でもない日常」を笑いに変える場面を見て、「ああ、この人たちも私たちと同じ目線なんだ」と思ったことがある。
だからこそ、その期待があるからこそ、「私たちを“素人”と一括りにして発言する」という行動は、ファンにとって“裏切り”のように映った。
炎上の発展過程
発言されたその日から、炎上は静かに、だが確実に広がっていった。
まず、YouTube配信の中で松尾さんが「一般の人はSNSをやるな」などの文言を口にする。相方との会話の中でもその立場を譲らず、発言がカットされず流れた。
配信後、視聴者の録画や切り抜きがSNS上にアップされる。短い一文が切り取られて拡散され、「芸能人が一般人を見下している」という印象が一気に広がる。
その後、私もTwitterで「普通の人の発言まで否定するならSNSに意味がなくなる」といった投稿を目にした。フォロワーが少ない人たちが賛同を集め、「この発言は人を傷つける」という声が徐々に増えていった。
数日経つと、発言の全文や文脈を求める声が上がる。動画が非公開になるとの情報が流れ、それが「責任逃れではないか」という疑念を呼ぶ。
さらにテレビ番組への出演など、松尾さんが通常通り活動している姿が見られ、「何もなかったように見せようとしている」という批判がファンからも出るようになった。
過去の“発信者 vs 一般人”争点
かつて、他の芸能人が「SNSは批判される可能性があるから使わない方がいい」「一般人の発言には責任が伴う」という主張をしたことがあった。
その時も、「言いたいことはわかるが、“一般人は黙れ”と言われるようで怖い」と感じるユーザーが多く、批判が集まった。
また、インフルエンサーが誤情報やデマを理由に「内容を考えて発信すべきだ」という発言をした際に、「じゃあどこまで“普通の人の自由”を否定するのか」と議論になった。
今回の松尾の発言は、過去のそうした論点を乗り越えて、「発言の権利のあり方」「影響力のある人の責任」「言葉の公平性」が同時に問われた点で、新しいフェーズの炎上である。
発言者が直面する責任と届けられる声
言葉を発するということには、“見られる”“切り取られる”“拡散される”という前提がついて回る。
特に影響力のある人物は、軽いノリでもその言葉が他人の感情を深く傷つける場合がある。
また、「全文を見てほしい」「言葉の背景を知ってほしい」という願いがあるなら、発言後の対応として誠実な説明が必要になる。
私自身、ある芸能人の言葉に傷ついた経験がある。「ただの日常の発言だろう」と思っていた言い回しが、自分の存在や思いを軽んじていると感じたことがある。
そういう経験を持つ人は多いから、炎上は単なる“ネットのノイズ”ではない。
社会的構造の変化:発信・共感・尊厳
この件で浮き彫りになったのは、次のような構造変化である。
- 誰もが発信力を持つ時代になった
- 視聴者・フォロワーという“受け手”の感覚が鋭くなってきた
- 言葉が持つ“温度”がこれまで以上に重視されるようになった
- 発言の自由とともに「発信される言葉の届き方・受け手の尊厳」が等しく重視されるようになった
この変化は、芸能人も含め、発言するすべての人に新しい期待を課している。
読者の体験としての共感の声
ある日、自分がSNSで「ちょっとした意見」を書きこむ。
その意見に、「それって素人の意見だよね」というリプライがついた。
フォロワーはわずか十数人。それでも、その「素人」という言葉が胸に突き刺さった。
「私は何もかも無価値なのか?」と、一瞬、思った。
その経験は、多くの人が抱えていて、今回の炎上を自分のこととして捉えさせる橋渡しになった。
新たな発信の時代には“共感と責任”の両輪が必要
松尾さんの発言は、多くの人の期待や価値観の“線”を踏み越えてしまった。
しかし、それは同時に、「誰もが発言者になれる社会」が持つ成熟への問いでもある。
発言の自由は守られるべきだ。
だが、発信する者は、その言葉がどこまで届き、どんな影響を与えるかを想像する責任もまた背負う。
「素人」という言葉が持つ重さを忘れないでほしい。