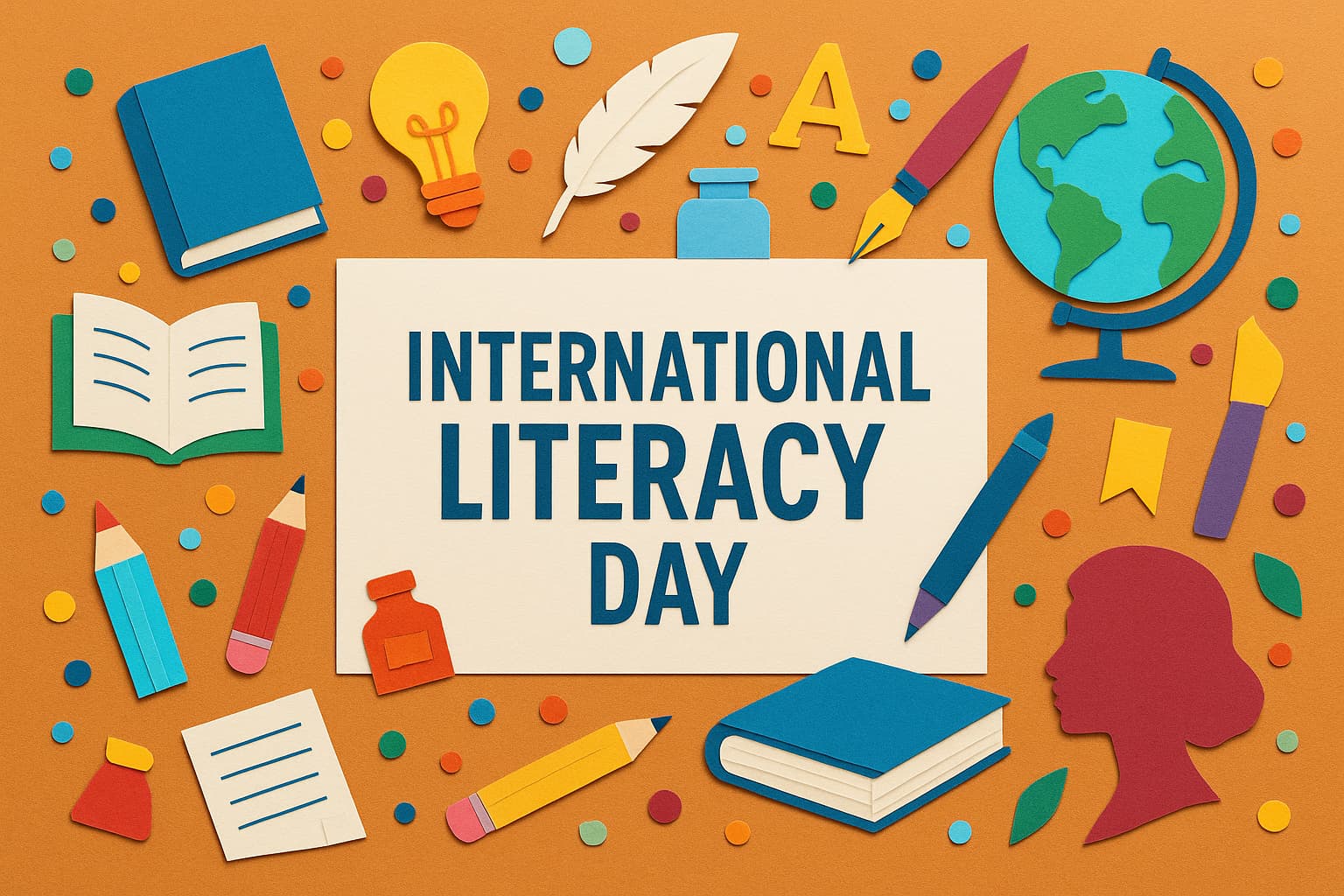国際識字デー(9月8日 記念日)はどんな日?
✅ 国際識字デーの由来は、1965年にイランのテヘランで開催された世界文相会議におけるパーレビ国王の識字支援提案に基づく。
✅ 世界中の読み書きできない人々の現状を知り、識字の重要性を広めるために国際的に制定された記念日。
✅ 国連教育科学文化機関(ユネスコ)が主導し、SDGsや世界の教育支援と密接に関わっている。
「もしあなたが文字を読めなかったら?」
スマートフォンでニュースをチェックすることも、仕事のメールに返信することも、薬の用法を確認することさえもできない――。
想像してみてください。
普段何気なくしている「読む」「書く」という行為ができない世界を。
それはまさに、情報から遮断された世界。
自由も、仕事も、夢も、そこにはありません。
そんな“文字が読めない現実”と向き合うために、世界で毎年9月8日に制定されている記念日――それが「国際識字デー(International Literacy Day)」です。
この記事では、この国際デーがなぜ生まれ、何を目的としているのか。
そして、日本と世界の識字の現状、今私たちにできることをわかりやすくお伝えします。
読んだ後には、家族や友人と話したくなるような内容に仕上げていますので、どうぞ最後までご覧ください。
国際識字デー(9月8日 記念日)の由来は?
国際識字デーの始まりは、1965年(昭和40年)にイランの首都テヘランで開催された「世界文相会議(World Conference of Ministers of Education on the Eradication of Illiteracy)」にあります。
この会議は、世界の教育問題、特に識字教育の遅れについて各国の教育大臣が話し合う重要な国際会議でした。
その場で、当時のイラン国王モハンマド・レザー・パーレビが驚くべき提案を行いました。
「軍事費の一部を、国民の識字教育に回すべきだ」
この発言は、冷戦下で軍拡が進んでいた当時の世界情勢の中で、極めて革新的なものでした。
パーレビ国王のこの一言は、教育が国家の未来を支える最も重要な投資であるという認識を、世界中の国々に植え付けたのです。
この歴史的な提案を受け、国連教育科学文化機関(ユネスコ:UNESCO)は1966年に、9月8日を「国際識字デー(International Literacy Day)」と正式に制定しました。
この日は、すべての人々が「読み・書き・理解する力」を持てる世界を目指し、識字の重要性を広める国際デーとして位置づけられたのです。
国際識字デー(9月8日 記念日)に関する豆知識
「識字(literacy)」とは、単に“文字を読んで書く”ことにとどまりません。
その内容を“理解し、活用できる”能力を含んだ、総合的な「生きるための知識の力」です。
ユネスコはこれを「Functional Literacy(機能的識字)」と呼び、社会生活に必要な読み書き能力と定義しています。
しかし、世界にはまだ約8億人もの人々が、基本的な読み書きができないまま暮らしています。
そのうちの約3分の2は女性です。
この数字が示すのは、単なる教育格差だけではなく、ジェンダー不平等、貧困、差別など、複数の社会課題が絡み合っているという現実です。
教育を受けることができないことで、女性たちは労働市場から排除され、自己決定権を奪われ、医療や法律、子育てといったあらゆる場面で困難に直面します。
また、識字率の低い国の多くはアフリカや南アジアの開発途上国に集中しています。
例えば、ニジェールでは女性の識字率は20%未満、バングラデシュの農村部でも30%台という厳しい状況が続いています。
一方、識字率が向上することで、子どもの死亡率が減少し、国の経済成長率も上昇するという明確なデータもあります。
つまり、識字教育は単なる“教育問題”ではなく、命と未来をつなぐライフラインなのです。
国際識字デー(9月8日 記念日)と日本の関係
驚くべきことに、日本の識字率は現在ほぼ100%です。
これは世界でも類を見ない高さであり、日本人の教育への熱意の表れとも言えます。
では、なぜ日本はこれほどまでに識字率が高いのでしょうか?
その秘密は、江戸時代の「寺子屋文化」にあります。
庶民の子どもたちが通った寺子屋では、読み書きそろばんといった実用的な知識が教えられました。
そして当時の江戸の町では、なんと識字率が70%以上に達していたとも言われています。
これは18〜19世紀のヨーロッパの都市部の識字率をはるかに上回る数値で、日本は当時から「教育先進国」だったのです。
また、江戸時代には貸本屋や浮世絵、瓦版(かわらばん)といった出版文化も発展しており、「読む文化」「書く文化」が庶民の間に広がっていました。
こうした文化的背景が、明治以降の義務教育制度と相まって、現在の高識字率に結びついているのです。
国際識字デー(9月8日 記念日)に関わる人物・団体
まず欠かせないのは、制定主体であるユネスコ(UNESCO)です。
ユネスコは、「教育、科学、文化を通じた平和の構築」を使命に掲げる国連の専門機関です。
国際識字デーの他にも、世界遺産保護、気候変動への教育的アプローチなど、幅広い分野で活躍しています。
識字問題においては、SDGs(持続可能な開発目標)の「目標4:すべての人に質の高い教育を」と直結しています。
また、識字教育を実施しているNGOやNPOも多く存在し、たとえば以下のような団体が活動を展開しています。
- ユニセフ(UNICEF):子どもの教育環境を整備
- JICA(国際協力機構):開発途上国への教育支援
- Room to Read:アジアやアフリカで図書館・学校設立
- 世界寺子屋運動(公益社団法人シャンティ):カンボジアやラオスなどで識字教育支援
こうした団体に支えられ、国際識字デーの活動は世界規模で広がっています。
国際識字デー(9月8日 記念日)に関するよくある質問
Q1. 国際識字デーでは何が行われているの?
ユネスコ主催の国際会議や、各国政府・NGOによる識字教育キャンペーン、読み書きワークショップ、ドキュメンタリー上映会などが開催されています。
Q2. 識字率ってどこで調べられるの?
ユネスコや世界銀行、国連開発計画(UNDP)などのデータベースから、国別の識字率を見ることができます。
Q3. 私たちができる支援はあるの?
寄付やボランティアはもちろん、SNSでの情報拡散や署名活動の参加も立派な支援です。国際識字デーをきっかけに行動してみましょう。
国際識字デー(9月8日 記念日)のまとめ
「文字を読めること」は、単なるスキルではありません。
それは、「未来を選べる力」です。
9月8日の国際識字デーは、そんな力を世界中の人々に届けようとする希望の日。
この日を制定したユネスコ、そして世界中で教育を広めるすべての人々の思いが、識字というシンプルで力強い行為に込められています。
日本の私たちは、当たり前のように読み、書き、考える生活を送っています。
けれど、それが「当たり前ではない人たち」が世界にはたくさんいるのです。
ぜひ、この国際識字デーに一度立ち止まり、文字を「読めること」のありがたさと、それを「届けること」の尊さに思いを馳せてみてください。