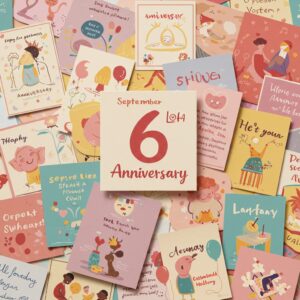✅ 鹿児島黒牛・黒豚の日(9月6日)はどんな日?
✅ 語呂「く(9)ろ(6)」で「黒」と読む九月六日に、黒牛・黒豚の魅力を祝う日
✅ 1998年に鹿児島黒豚銘柄販売促進協議会が制定し、日本記念日協会に認定・登録された日
✅ PRキャラバン・店頭フェアだけでなく、学校給食や出前授業で地域にも根づいた取り組み
あなたも知らずに過ぎてしまった“食の小さな祭日”、「鹿児島黒牛・黒豚の日」。
でも、その背後には、地元の農家さんの熱意や、子どもたちへの食育の想いがぎゅっと詰まっているのです。
一口食べれば、なぜこの日が特別なのか、きっとあなたも納得。
このブログでは、「なんだか気になる記念日」を、読み終わるころには「いつか訪れたい・誰かに話したくなる」くらい魅力的にお伝えします。
鹿児島黒牛・黒豚の日の由来と背景
「く(9)ろ(6)」=「黒」という語呂合わせ。
ちょっとした語呂の楽しさが、記念日の入り口になっています。
でも、この日は単なる覚えやすさのための言葉遊びではありません。
1998年(平成10年)に、鹿児島黒豚銘柄販売促進協議会が設立し、9月6日を「鹿児島黒牛・黒豚の日」と定めました。
ブランドの確立と消費の拡大を目的に、地元農家・流通・自治体が一丸となって動き始めたのです。
さらに、一般社団法人・日本記念日協会にも認定・登録され、信頼性と注目度が高められました。
そこからは毎年、キャラバン隊が全国を駆け回り、販売店ではフェアが展開され、まさに“食の祭典”として定着していきました。
「鹿児島黒牛」の輝く歩み
鹿児島黒牛は、和牛の名産地として知られる鹿児島で、昭和61年にブランド名としての「鹿児島黒牛」が定着した歴史があります。
その後も改良・肥育方法を磨き続け、2017年に開催された第11回全国和牛能力共進会では、4部門で最優秀枝肉賞(農林水産大臣賞含む)を獲得する快挙を果たしました。
まさに、伝統と革新が融合した“ブランド牛”としての地位を確かなものにしています。
「かごしま黒豚」の血統と品質証明
かごしま黒豚は、バークシャー種(イギリス原産)と薩摩の土着豚の改良によって確立された品種で、「六白」(毛色が黒・四脚先、鼻先、尾先が白)の特徴があります。
その肉質は、筋繊維が細かく、しまりと歯切れがよく、脂の溶ける温度が高いため“さっぱりした甘み”が感じられる逸品です。
さらに、品質への信頼を守るために、1992年から「かごしま黒豚証明制度」も導入。
証明書には桜島と黒豚の写真、出荷年月日、生産者名などを記載し、トレーサビリティを徹底しています。
品質のばらつきを抑え、消費者の安心につながるこの仕組みは、他地域にも先駆けた取り組みと言えます。
地域と子どもたちをつなぐ取り組み
「鹿児島黒牛・黒豚の日」を中心に、地域に根ざした活動も進行中。
ナンチクグループでは2007年から、9月6日を“黒の日”として、県内51校の小中学校に黒豚350kg(約7頭分)を無償提供。約6,700食分の給食として振舞われています。
生徒たちからは「やわらかくておいしかった」「楽しみにしていた」といった声も届いています。
さらに2019年からは、社員が講師となり、出前授業も実施。実際に肉の食べ比べや工場装具の体験を通して、食と地元への理解を深める学びの場を提供しています。
心に響く描写:育てる現場と味わうひととき
早朝、朝霧に包まれた放牧地。
鹿児島黒牛がのんびりと草を口に運び、その透明な空気の中に、農家さんの呼吸と土の匂いが混ざります。
その姿には、日々の丹精と誇りがにじんでいます。
そして、食卓に登場した鹿児島黒牛のステーキ。
口に含んだ瞬間、しなやかな霜降りがとろけ、豊かなコクとまろやかな余韻が口いっぱいに広がります。
それはまさに、「大地からの贈り物」と呼びたくなる味わいです。
かごしま黒豚のしゃぶしゃぶも、箸で持ち上げればほどけるような柔らかさ。
ほんのり甘い脂と、さっぱりとした後味が重なって、もう「豚肉って、こんなに奥深かったんだ」と感じさせられます。
鹿児島黒牛・黒豚の日に関するよくある質問
Q1:なぜ9月6日なの?
「く(9)ろ(6)」=「黒」の語呂合わせから、誰でも覚えやすく、親しみやすい日になりました。
Q2:誰が決めたの?
1998年に鹿児島黒豚銘柄販売促進協議会が制定し、以後日本記念日協会に認定・登録された記念日です。
Q3:どんな活動があるの?
- キャラバン隊が県外でPR活動を展開
- 小売店でフェアや試食イベント
- 学校給食提供や出前授業など地域教育との連携
- ふるさと納税に合わせた特別返礼品も注目。南九州市では“黒豚1頭分(55kg)”が届くお礼品も登場しています。
鹿児島黒牛・黒豚の日:まとめ
“鹿児島の誇り”、“味のごちそう”、“地域の絆”──
この「鹿児島黒牛・黒豚の日」は、まさにその三つが凝縮された特別な日です。
語呂合わせによる親しみの裏には、厳格な品質管理、地元農家の情熱、教育への想いが隠れています。
ステーキの脂の輝きに、豚肉の甘みと香りに、ぜひあなた自身の五感で触れてほしい。
そして、誰かに「知っている?」と話したくなる、ちょっと自慢したくなる一日になるはずです。
今日は何の日(9月6日は何の日)
妹の日 | クロスワードの日 | まがたまの日(6月9日・9月6日) | 黒の日(黒染め) | 黒の日・クロイサの日 | 鹿児島黒牛・黒豚の日 | 黒豆の日 | キョロちゃんの日(森永チョコボールの日) | ソフティモ・黒パックの日 | 黒酢の日 | クレームの日 | 黒い真珠 三次ピオーネの日 | クロレラの日 | シェリーの日 | 甲斐の銘菓「くろ玉」の日 | スマートストックの日(3月6日・9月6日) | 黒あめの日 | 9696(クログロ)の日 | 松崎しげるの日 | カラスの日 | 浅田飴の日 | 生クリームの日 | 黒にんにくの日 | クルージングの日 | クロレッツの日 | MBSラジオの日 | スポーツボランティアの日 | 回転レストランの日 | 飴の日 | Dcollection・黒スキニーの日 | のどぐろ感謝の日 | スライドシャフトの日 | クロコくんの日 | クロモジの日 | 黒霧島の日 | へべすの日 | ブラックウルフ・黒髪の日 | 黒舞茸の日 | 岩室温泉・黒湯の日 | ぐるぐるグルコサミンの日 | ブラックサンダーの日 | X-BLEND CURRYの日 | ピカールのクロワッサンの日 | モノマネを楽しむ日 | 手巻きロールケーキの日(毎月6日) | メロンの日(毎月6日) | 歯ヂカラ探究月間(9月1日~30日)