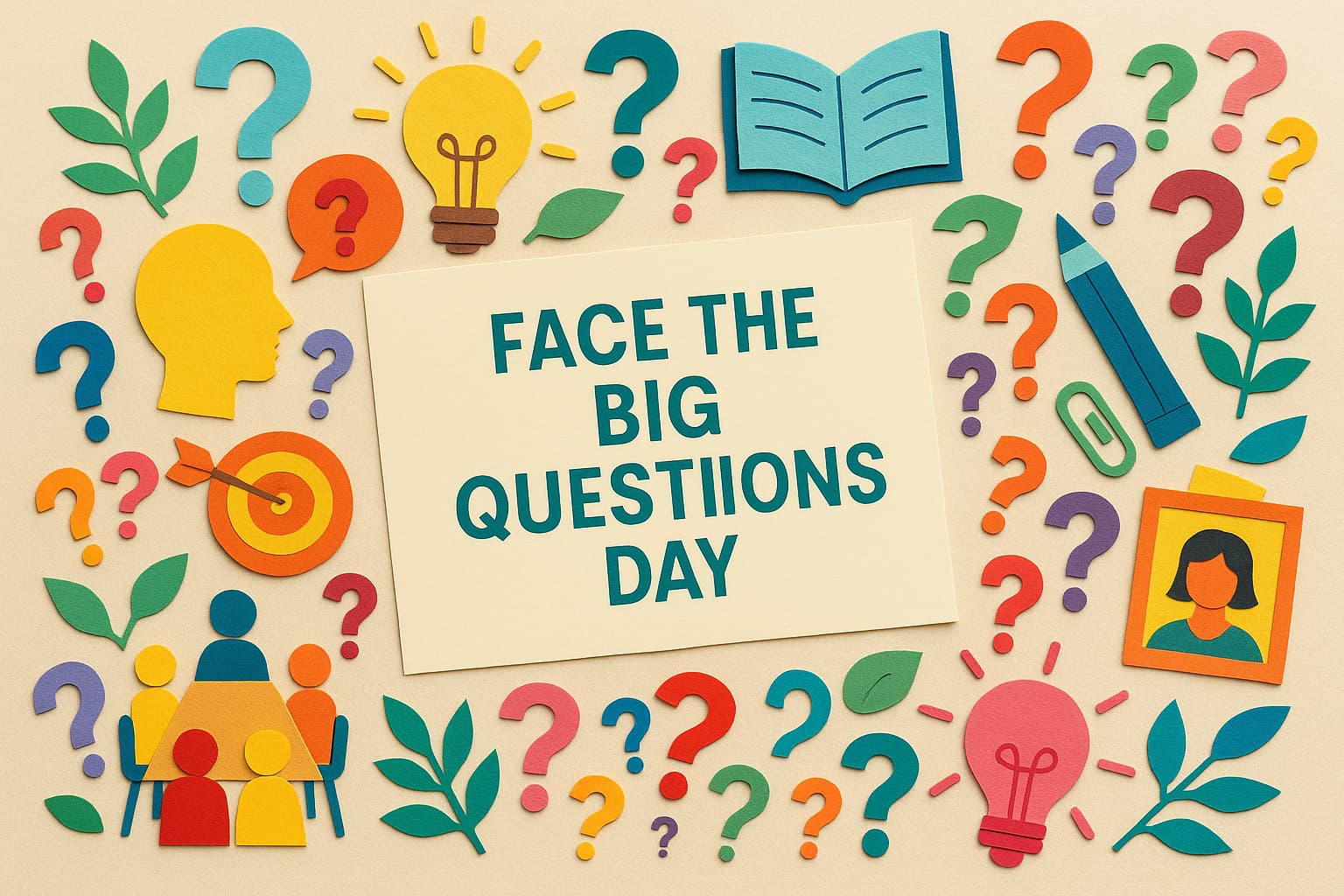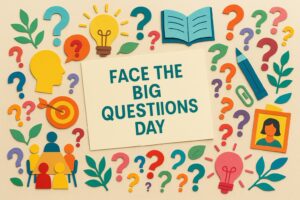大切な問いに向き合う日はどんな日?
✅ 「大切な問いに向き合う日」の由来は、「10=と」「1=い」で「とい(問い)」と読む語呂合わせから。
✅ 豆知識として、「問い」を立てることを通じて創造的な対話や価値探究を促すという目的がある。
✅ 制定したのは 株式会社MIMIGURI(東京都文京区本郷)、認定は 一般社団法人日本記念日協会により2021年に登録された。
問いからはじまる、ちょっと特別な時間
自分自身に「どうして?」と問いかける瞬間があると、世界の見え方が少しだけ変わります。たとえば、仕事帰りの夕暮れに「なんで今日はこの道を選んだのかな?」とか、家族でテレビを見ながら「このシーンって、誰の視点で描かれてるのだろう?」など。
そんな「問い」は、小さくてもいつもの時間を丁寧に、ちょっとだけ豊かにしてくれます。そして、その問いが、家族や友人との会話やチームのミーティングを、ただの報告・連絡・相談から、探究・対話・創造へと変える力を持っているのです。
だからこそ、毎年10月1日を「問い」に向き合う日として訪れたとき、私たちは「問いを立てる・問いを耕す・問いを活かす」という3つのステップを思い出すいい機会になります。
この記念日がなぜ生まれたのか、どう活用できるのか、誰がこの動きを支えているのか――この記事では、丁寧にひも解いていきます。問いを通じて成長したい人、家族の会話をもっと深めたい人、チームで未来をつくりたい人、ぜひ読み進めてみてください。
「大切な問いに向き合う日」の由来と背景
「大切な問いに向き合う日」は、2021年に株式会社MIMIGURIが申請・登録し、毎年10月1日を記念日として定めたものです。日付の理由は「10(と)」「1(い)=問い」という語呂合わせにあります。
なぜ「問い」だったのか?それは、現代社会が「答えがすぐに出る問い」よりも「答えが決まっていない問い」に直面しているからです。
多様化する価値観、急速に変化する技術や働き方のなかで、ただ与えられた解を探すのではなく、「何を問いかけるか」「どう問いを立てるか」が成長や創造の鍵となってきています。
株式会社MIMIGURIは、人材育成・組織開発・制度設計・ブランド開発・事業開発などを融合させたコンサルティングやメディア運営・研究開発を手がける会社です。設立日は2021年3月1日、本社は東京都文京区本郷にあります。
そのなかで同社は、「問い」を「あらゆる分野において複雑な問題の本質を捉え、創造的な課題解決に導く方法論」と位置づけ、問いを立て・問いを深め・問いを活かす対話や探究を促す活動を行ってきました。
こうした背景を受けて、「問いという技術」を社会的に広げたいという思いのもと、10月1日という覚えやすい語呂で記念日を制定。一般社団法人日本記念日協会にも登録され、公式に認定されました。
この日を通じて「問いの重要性」をより多くの人が意識し、問いかけに熟達する人が社会で増えていくことが願われています。こうしたコンセプトは、家庭・学校・職場・地域などさまざまな場面で「問いを起点にする対話」を促しています。
「大切な問いに向き合う日」にまつわる豆知識
この記念日には、ただ語呂合わせで終わる以上の面白さがあります。ここでは知っておくと「問いの日」がもっと身近に感じられる豆知識をご紹介します。
まず、問いと質問の違い。問いは「答えが誰にも決まっていない」ことを前提にしています。一方、質問はいわば「解くべき問題」が見えていて、答えを探しに行く行為に近いと言われています。つまり問いを立てるには、答えを探す前に「問いをつくる」作業が必要というわけです。
次に、この記念日を活用した活動が広がっています。例えば、10月1日当日には、オンラインで「問いをデザインするワークショップ」や「問いを起点にした対話イベント」が開催されることがあります。問いをテーマにした書籍・記事もこの時期に注目を集めています。
さらに、問いを「育てる」概念もあります。問いを立てた後、時間をかけて問いに向き合ったり、問いを友人・家族・同僚と共有したりすることで、問い自体が深まっていくというものです。問いが熟してくると、問いから次の問いが生まれ、探究のスパイラルが始まります。
また、問いを立てる場面として、「なぜこの習慣を続けているのか?」「本当にこれでいいのか?」「このチームにとっての問いとは何か?」といった問いかけは、個人やチームの成長を促す入り口として機能します。
このように、「問いの日」はただの日付ではなく、「問いを育てる時間」を設けるという意識づけとしても活用できます。
最後に、問いにまつわるちょっとした視点。たとえば、日常の簡単なシーンで「この道を選んだのはなぜだろう?」と問いを投げかけるだけでも、見慣れた風景が少し違って見えることがあります。
問いを立てると、物事は受動的に受け入れるものから、能動的に探究するものに変わります。つまりこの記念日は「問いを受け身から能動へ転換するスイッチ」でもあるのです。
「大切な問いに向き合う日」と関わる人物・団体
この記念日を支えるのは、株式会社MIMIGURIという会社、そしてその代表者をはじめとする問いを探究する人々です。
株式会社MIMIGURI(本社:東京都文京区本郷2‑17‑12 THE HILLS HONGO 4階)は、2021年3月1日に創業され、人材育成・組織開発・制度設計・事業開発・ブランド開発を有機的に組み合わせたコンサルティング、さらにメディア運営・研究開発を行う会社です。
代表取締役Co‑CEOの 安斎勇樹 氏(東京大学大学院 情報学環 特任助教)は、著書 『問いのデザイン:創造的対話のファシリテーション』(学芸出版社 2020年6月4日)を共著しており、問いを立てる・問いをデザインするという考え方を理論と実践の両面から追究しています。
安斎氏は「問いは対話の媒体であり、問いに向き合うことで人と人、チームと社会が編み直される」という視点を提唱しています。また、問いを立て・探究し・対話する場づくりや研修・ワークショップを組織向けに設計しており、まさに「問いの社会化」を推進する旗手のひとりです。
こうした背景が、問いを軸にした記念日の立ち上げに深く関わっています。記念日を通じて、この問いを探究する文化・問いを立てる習慣・問いを共有する場が少しずつ社会に広がってきているのです。
つまり、「問いの日」は個人の問題意識を引き出すだけでなく、問いを媒介にして組織や社会の対話の質を高めるというネットワーク的価値も持っていると言えます。
このように、問いという一見抽象的なテーマを、具体的な実践や仕組みに落とし込んできた組織・人物がいるからこそ、この記念日は形になり、私たちの身近な時間に問いを立てるきっかけとして機能しているわけです。
「大切な問いに向き合う日」に関するよくある質問
Q1:問いを立てるって、どうやって始めたらいいの?
問いを立てる第一歩は、自分や周囲に「なぜ?」と問いかけることです。
例えば、朝起きて「今日はなぜこの服を選んだのか?」「出勤途中、何を思ったのか?」というような、ちょっとした問いが入り口になります。重要なのは「答えを急がない」こと。
問いを立てるとき、すぐに答えを求めず、問い自体を眺める時間を持つことで、問いが育ちます。問いを家族や友人、チームと共有することで、問いが深まると同時に、対話が生まれます。
この記念日は、その「問いを立てる・問いを共有する」という習慣を少し意識するための機会です。問いを習慣化すると、日常の中に新たな発見や対話の種が増えていきます。
Q2:家庭や職場で「問いの日」をどう活用できる?
家庭では、夕食後に「今日、誰かに問いを投げかけた?」という切り口で会話を始めてみると、普段の会話が少し深まります。
例えば、「今日、仕事で一番気になった問いは何だった?」と聞いてみると、子どもやパートナーの思考が見えてくるかもしれません。
職場では、ミーティングの冒頭に「このプロジェクトで私たちはどんな問いを立てられるか?」という問いを全員に投げかけることで、目的や視点を共有でき、議論が活性化します。
また、10月1日を機に「問いを立てる時間」を10分だけ設ける、問いかけカードを作る、問いをテーマにしたポスターを貼るなど、小さな仕掛けをするのもおすすめです。問いを「行動」に紐づけることで、記念日としての意味が深まります。
Q3:この記念日は誰にとって特におすすめ?
問いを起点に思考したい人、成長意欲を持っている人、チームや家族ともっと深い対話をしたい人におすすめです。
特に、教育現場・研修・チーム運営・マネジメントに関わる人にとっては、「問いを設計する」という視点がキャリアや組織の質を変えるきっかけになります。
さらに、日常の忙しさに流されがちな人にも、この記念日は「立ち止まって問いかける習慣」をリセットするよい機会となります。問いを立てることで、いつものルーティンが少しずつ「探究モード」に切り替わるのです。
まとめ:「大切な問いに向き合う日」をどう活かすか
「大切な問いに向き合う日」は、10月1日という語呂とともに、「問いを立てる・問いと向き合う・問いから対話が生まれる」という流れを社会に提案する記念日です。
問いをただ「持つ」だけでなく、問いを立て、「問いを育て」、「問いを活かす」ことが、私たちの思考や関係、組織のあり方を少し変えてくれます。
この日をきっかけに、家族や友人、職場で「問いを共有する時間」をつくってみてください。
例えば、10月1日の夕食時に「今年、私が投げかけたい問いは?」と一言共有するだけでも、会話が変わります。
問いから始まる、軽やかで豊かな対話を少しずつ育てていきましょう。
問いを大切にすることで、答えを求める旅が少しだけ自由で、少しだけクリエイティブになります。10月1日、「問いの日」をあなたなりのスタイルで迎えてみましょう。