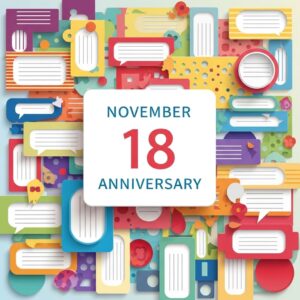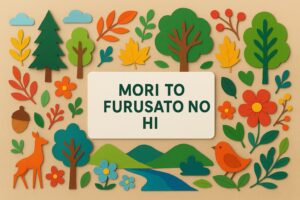もりとふるさとの日はどんな日?
✅ 国土保全奨励制度全国研究協議会の設立日を記念した日。
✅ 森林保全やふるさとの自然環境を守る重要性を再認識する日。
✅ 国土保全奨励制度全国研究協議会が記念日の制定に深く関与。
あなたの心の奥にある「ふるさと」を、覚えていますか?
山の緑、川のせせらぎ、田んぼに映る夕日。
子どものころに遊んだ森の中や、おじいちゃんの畑の匂い。
そんな、心の奥に残る「ふるさとの風景」には、自然と人の絆がしっかりと刻まれています。
11月18日は、「もりとふるさとの日」。
この記念日は、国土保全奨励制度全国研究協議会が設立された1994年(平成6年)11月18日を記念して制定されました。
単なる設立記念日ではなく、私たち一人ひとりがふるさとや自然とどう向き合うかを見つめ直す、きっかけの日です。
この記念日の背景には、森を守ること、ふるさとを未来につなげることの大切さがあります。
本記事では、「もりとふるさとの日」の由来や、知っておきたい豆知識、そして関係する団体や活動について、じっくり深掘りしていきます。
自然にふれると、どこか心がほっとする。
そんな気持ちを、再発見できる内容になっています。
「もりとふるさとの日」の由来とは?未来へと受け継ぐ自然と地域の絆
1994年(平成6年)11月18日。
この日、全国の地域活動団体や自治体が連携し、自然環境を守るための知見と経験を共有する組織「国土保全奨励制度全国研究協議会」が設立されました。
この協議会は、名前のとおり「国土の保全」をテーマに、森林、農地、水源などを守るためのさまざまな活動を推進しています。
協議会の設立には、大きな社会的背景がありました。
昭和から平成初期にかけて、日本各地で山林の荒廃や農村の過疎化が進行し、自然災害のリスクも高まっていました。
地域の人々が「自分たちのふるさとを守りたい」と自主的に始めた活動を、国全体で支援・連携していくために設けられたのが、この研究協議会です。
そして、設立日である11月18日を「もりとふるさとの日」と定めたのは、ただの記念日ではなく、「自然とふるさとを想う心」を全国に広げるため。
ふだんは意識しない“当たり前の風景”が、じつは多くの人の努力によって守られているという事実を、再認識するための日なのです。
この日は、「自然に感謝し、地域に目を向ける一日」として、じわじわと注目を集めています。
「もりとふるさとの日」の豆知識:知っていると誰かに話したくなる!
記念日は、ただの「日付」ではありません。
そこには、その日を選んだ理由や込められた想いがあります。
「もりとふるさとの日」には、自然と人、社会と心をつなぐヒントがたくさん詰まっています。
ここでは、ちょっとした会話のネタにもなる豆知識をご紹介します。
🌲 森林率が7割を超える日本ならではの記念日
日本の国土のうち、約67%が森林で覆われています。
これは先進国の中でもトップクラスの数字。
だからこそ、森林保全は「山奥の話」ではなく、私たち全員に関係するテーマなのです。
「もりとふるさとの日」は、そんな日本の姿を再確認する絶好の機会です。
🏞 「ふるさと」は、懐かしむだけでなく「守る」存在
「ふるさと」という言葉には、どこかノスタルジックな響きがあります。
でも、もりとふるさとの日は、ふるさとを「過去の思い出」ではなく、「未来に残したい場所」として考え直す日です。
今、私たちが守らなければ、次の世代には残せない。
そんな危機感が込められています。
👧 子どもたちの教育にもつながる自然とのふれあい
この記念日をきっかけに、地域では「森の教室」や「親子で参加する自然観察イベント」が開催されることもあります。
子どもたちにとって、自然の中で過ごす体験は、単なる遊びではなく「生きる力」を育む貴重な学び。
もりとふるさとの日は、次世代教育の場としても大きな意味を持っています。
「もりとふるさとの日」に関わる団体:つながる力が未来をつくる
「もりとふるさとの日」を制定したのは、「国土保全奨励制度全国研究協議会」という団体です。
この組織は、地域に根ざした保全活動を支援し、それらの情報を全国に広めるハブ的な役割を果たしています。
具体的には、次のような取り組みを行っています。
🧩 地域の知恵を集める「研究・共有」活動
各地域の保全活動には、その土地ならではの知恵や文化が詰まっています。
それらを研究・分析し、他地域にも活かせるようにするのがこの協議会の大きなミッションのひとつです。
🔗 行政・企業・教育機関との連携
地域活動は、ボランティアだけで成り立つものではありません。
協議会では、自治体や企業、学校と連携することで、より広く・長期的に活動を支える体制づくりを進めています。
📣 情報発信で意識を変える
年に一度の「もりとふるさとの日」には、講演会やシンポジウム、活動報告なども行われています。
それは、地道な活動を見える化し、全国の人たちの関心を呼び起こすための大切な手段です。
このように、「もりとふるさとの日」は、現場の努力と知恵をつなげ、未来に向かうネットワークの中で生まれた記念日です。
「もりとふるさとの日」に関するよくある質問
Q1:どうやって参加できるの?
特別なイベントに参加しなくても大丈夫です。
自宅の庭の手入れや、公園のゴミ拾い、近所の森を歩いて自然にふれるだけでも、立派な参加になります。
Q2:「もりとふるさとの日」に何を意識すれば良い?
「自分のふるさとって何だろう?」と考えることから始めてみてください。
ふるさとは、生まれた場所だけでなく「心が落ち着く場所」でもあります。
Q3:この記念日をきっかけに、どんな行動ができる?
例えば、自然保護団体のSNSをフォローする、地元のイベントに足を運ぶ、子どもと一緒に自然を観察する——。
小さな一歩でも、思いを持って行動することが未来を変えるきっかけになります。
まとめ:もりとふるさとの日が教えてくれる、小さな原点と大きな未来
「もりとふるさとの日」(11月18日)は、私たちがふだん意識しない「自然と地域のつながり」に光を当てる記念日です。
国土保全奨励制度全国研究協議会の設立日という事実の裏側には、地域を守り、未来を見据えるたくさんの想いが込められています。
この日をきっかけに、ふるさとを思い出してみてください。
森のにおい、土のぬくもり、人とのつながり——。
それらを守っていくことが、私たち自身の未来を守ることにつながります。
自然は、ただの風景ではありません。
そこには、心のやすらぎと、生きる力があります。
もりとふるさとの日。
あなたにとっての「ふるさと」とは、どんな場所ですか?