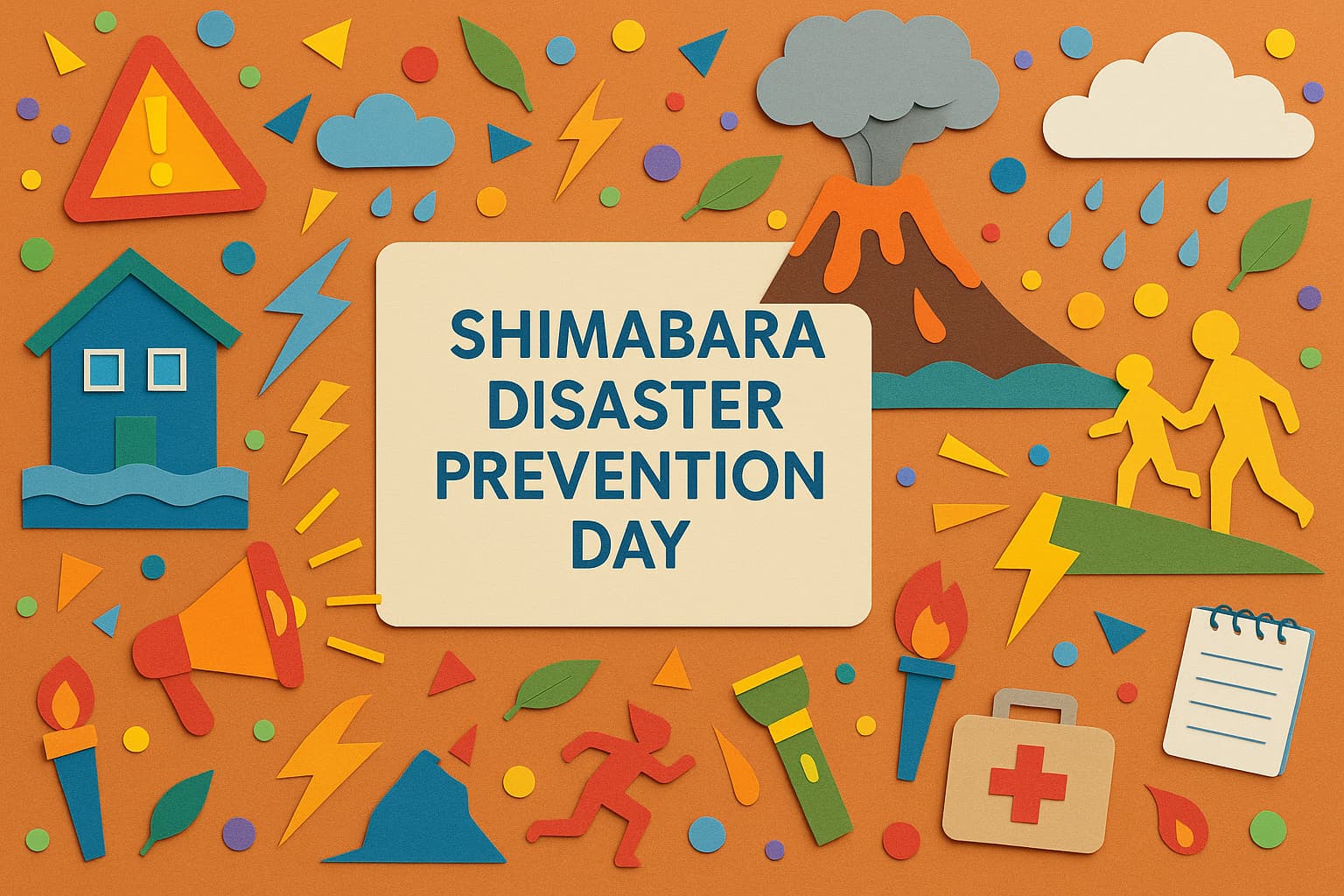島原防災の日はどんな日?
✅ 島原防災の日の由来は、1990年11月17日に始まった 雲仙普賢岳の噴火を教訓とし、長崎県 島原市が制定した防災意識を高める日です。
✅ 豆知識として、噴火とその後の火砕流・避難・復興という一連の流れが、 「防災」だけでなく「地域の絆」を育んだ契機でもあります。
✅ 島原市および 雲仙普賢岳を監視・教育する 雲仙岳災害記念館(がまだすドーム)など防災・教育機関が深く関わっています。
火山と暮らす町だからこそ「守ること」を考える日
長崎県島原半島、その中央部にそびえる雲仙普賢岳。
その山は、昔から静けさの中に温泉と風景美を秘めつつも、私たちに“自然の逆襲”を忘れさせない存在です。
1990年11月17日、この山が約200年ぶりに動き出しました。
その日に生きていた人々にとって、それは「見えていた風景がある日突然変わる」瞬間でした。
そして今日、島原市ではその日を「島原防災の日」として、単なる過去の出来事ではなく、「命をどう守るか」を考える記念日として大切にしています。
このブログでは、その背景、知っておきたい豆知識、関わる人々のストーリー、そして「自分ごととして備える」ためのヒントまで。
読むだけで、家族や友人との会話に「そういえば、島原ってあの日がきっかけで…」と話せる内容を目指しました。
どうぞ、一緒に“火山の記憶”から学び、日常を守る力を育てましょう。
「島原防災の日」が誕生した理由:雲仙普賢岳噴火を忘れないために
長崎県島原市が「島原防災の日」を11月17日に定めたのは、1990年11月17日という日付に深い意味があるからです。
この日、山が動いた。雲仙普賢岳において、静かな時の流れが急変し、防災の意識が地域に根付くきっかけになりました。
噴火の始まり
1989年から島原半島周辺では群発地震が発生していました。
そして1990年11月17日、普賢岳の火山活動が再び始まり、水蒸気爆発というかたちで山が揺れました。
この時、地域住民の多くは“まさかこの山が”という想いだったと伝えられています。
その後、1991年5月から溶岩ドームが確認され、5月24日に火砕流が初めて流下。 転機は1991年6月3日、大規模な火砕流が島原市北上小屋地区へ流れ込み、43人の尊い命が失われました。
この一連の噴火活動は1990年11月から1995年まで、約4年3ヶ月にわたって続きました。
被害は家屋・農地・交通に及び、地域は長期の避難生活を余儀なくされたのです。
記念日としての意味
このような大規模な災害を経験した島原市では、噴火からの復興とともに「備える力」「学び合う力」「地域で支え合う力」を育てる場が必要とされました。
「島原防災の日」は、ただ悲しみを振り返る日ではなく、未来の命を守るために、地域住民ひとりひとりが防災意識を“自分ごと”として捉えるための記念日です。
この日を機に、防災訓練、地域住民の集まり、学校教育、防災ワークショップなどが毎年行われています。
そうした「学びの礎」として、11月17日は地域に根付きました。
島原防災の日に知っておきたい火山・防災のポイント
少し専門的な用語も交えながら、火山災害や防災に関して「なるほど」と思える豆知識をご紹介します。親しみやすい言葉でお届けします。
火砕流って?
火砕流とは、高温・高速で降り注ぐ火山ガスや岩石・灰の混合物の流れのこと。噴火から数分のうちに、数キロ離れた場所に到達することもあり、避難が間に合わないほどの速度を持っています。
雲仙普賢岳の噴火では、この火砕流が1991年6月3日に4 km以上流れ下ったとも報告されています。
溶岩ドームの崩壊という現象
噴火から数年経って、溶岩が火口付近に厚くたまり、いわゆる「ドーム」を形成します。
これは流れにくい粘性の高い溶岩が積み上がったもので、やがて自重や地形変化により崩落してしまうことがあります。崩落した溶岩ドームは、火砕流を生む原因となるのです。
実際、1990〜95年の雲仙普賢岳の噴火では、ドームの崩壊が頻繁に起き、火砕流・土石流を引き起こしました。
「備え」の3つの視点
- 情報を知る/逃げる場所を知る
火山の異常な音・群発地震・怪しい煙など“前兆”を知ることは第一歩です。地域のハザードマップや避難場所も必ず確認しておきたいです。 - 日用品を整える
懐中電灯・マスク・ヘルメット・ラジオなど、火山灰にも対応できる備品を揃えておくと安心です。 - “何となく”を無くす
「まさか自分の町が」という油断をなくすため、家族・友人と防災の話をすることが鍵です。島原市では、毎年この記念日に地域全体で「自分の命は自分で守る」という意識を高めています。
「島原防災の日」にちなんだ豆エピソード
例えば、島原半島では噴火後、地元住民が「町を守るために何ができるか」を話し合う「防災講演会」を11月17日に開いています。
また、学校ではこの日に「防災カルタ」を使った授業をするところもあり、子どもたちが防災を楽しく、でも真剣に学ぶきっかけになっています。
こうした地域の工夫も、単なる“記念日”以上の意味を持っているのです。
島原防災の日と深く関わる人々・団体・町のストーリー
「島原防災の日」には、記憶の淵に沈む“人や町の物語”があります。ここでは、代表的な人物・団体・地域にフォーカスしてご紹介します。
島原市の地域住民と町
島原半島は、温泉や海の景色が豊かで、観光地としても知られていました。
しかし、1990年11月17日から始まった噴火活動により、その日常が一変しました。
地域住民の多くが避難を余儀なくされ、住まいや仕事を失った人もいます。
ある住民は「噴火の音が夜空に響くと、子どもが泣いて怖がった」「避難所に集まった時に隣の人が『私たち、助け合おうね』と言った」と当時を語ります。
記念日となった今も、町の防災訓練には「あの時に助けてもらった隣人」の顔があり、地域の絆が防災の原動力になっています。
災害を伝える拠点:雲仙岳災害記念館(がまだすドーム)
この記念館は、雲仙普賢岳の噴火災害と復興の歴史を伝える施設です。
展示では、噴火前の地震の映像、火砕流の実寸模型、地域住民の証言などが紹介されており、訪れる人は「もし自分だったら」と考えさせられます。
また、防災研修・学校授業も行われており、「島原防災の日」の啓発拠点として重要な役割を担っています。
行政・自治体・防災関係者
島原市や長崎県、防災専門機関、気象機関などが連携して、噴火以降の体制を強化してきました。
例えば、噴火当時の島原市長であった 鐘ヶ江 管一 氏は、噴火後の避難指揮に奔走し、その姿が地域に強い印象を残しました。
また、防災情報をいかに迅速に住民に届けるか、教育・訓練にどう落とし込むかといった課題に取り組んできた防災専門家・行政職員たちの地道な活動の積み重ねが、「島原防災の日」の制度化・定着を可能にしました。
島原防災の日に関するよくある質問
Q1. 島原防災の日には何をしたらいいの?
A. 11月17日を機に、まず家庭で「もし火山が噴火したらどうするか」家族で話し合ってみましょう。
地域で防災訓練が行われることも多く、参加して実際に避難経路を確認するのもおすすめです。
さらに、火山灰への備えとしてマスク・ヘルメット・ラジオなどの点検もしておくと安心です。
Q2. 雲仙普賢岳の噴火ではどれくらいの被害があったの?
A. 1990年11月17日から始まった噴火活動は、1995年頃まで4年余りにわたりました。
1991年6月3日の大規模な火砕流では43名の死者・行方不明者が出ており、家屋・交通・農地にも甚大な被害が及びました。
地域住民の避難生活も長期化し、観光や産業にも深い傷跡を残しました。
Q3. なぜ「11月17日」が記念日になったの?
A. 噴火活動が1990年11月17日に再開されたことがきっかけです。
その日は地域に「火山災害は他人事ではない」という強い警鐘をもたらしました。
島原市では、この日を「防災を考える日」と定め、毎年訓練・教育を行うことにしたのです。
まとめ:島原防災の日に、私たちができること
島原防災の日とは、雲仙普賢岳の噴火という過去の“衝撃”を忘れずに、未来の命を守るために地域とともに備える日です。
ただ振り返るだけではなく、毎日の暮らしの中で「もしもの時も大切な人と助け合える」「自らの命を守る備えがある」という安心を育む日でもあります。
火山とともに暮らす島原市のように、私たちが住む町にも自然のリスクは存在します。
防災グッズの点検、家族での会話、地域の訓練への参加――それらはすべて「島原防災の日」が私たちに投げかける問いかけです。
あなたも、11月17日を「ただの記念日」ではなく、「家族で命をつなぐ会話」のきっかけとして活用してみませんか。
そして、地域・学校・職場で「この町ならではの防災の備え」を一緒に話してみてください。
小さな一歩が、大きな安心につながります。
この島原防災の日という日を通じて、命の大切さ、防災の大切さ、そして“あなたが誰かの命を守る存在”であるという誇りを感じていただけたら幸いです。
今日は何の日(11月17日は何の日)
国際学生の日 | 島原防災の日 | 将棋の日 | 肺がん撲滅デー | レンコンの日 | ドラフト記念日 | 日本製肌着の日 | 暴君ハバネロの日 | 国産なす消費拡大の日(毎月17日) | いなりの日(毎月17日) | 減塩の日(毎月17日) | ダブルソフトでワンダブル月間(11月1日~30日)