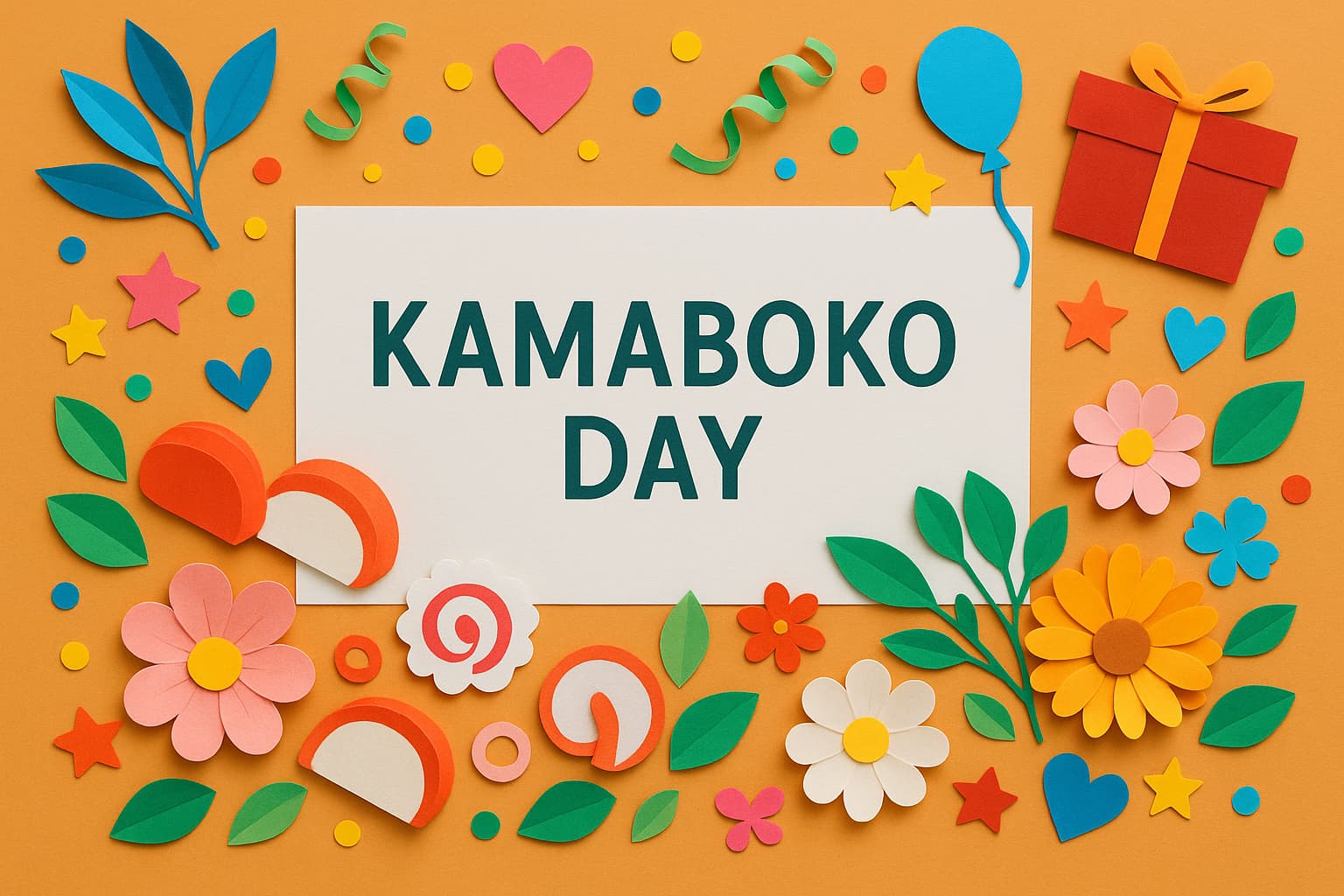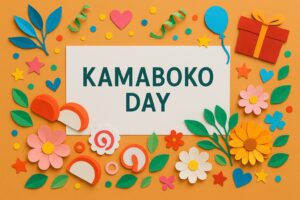かまぼこの日(11月15日 記念日)はどんな日?
✅ 1115年に文献に初登場したかまぼこの歴史を記念する日です。
✅ 七五三祝いで使われた紅白かまぼこの伝統にちなんでいます。
✅ 日本かまぼこ協会(旧・全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会)が制定しました。
魚のいのちが、祝いの形になった。
それが「かまぼこ」です。
食卓に静かに並ぶ紅白のかまぼこ。
何気ないように見えて、その一切れには、日本の風土と、家族の想いと、職人の技と、そして千年を超える歴史が込められています。
11月15日、「かまぼこの日」。
その日が、ただの記念日ではないことを、あなたは知っていますか?
この記事では、「かまぼこの日」に込められた物語を丁寧にひも解きながら、なぜこの日なのか、どんな背景があるのか、そして、かまぼこが持つ深い魅力について、たっぷりとご紹介します。
食べ物の記念日、と聞くと軽く感じるかもしれません。
でも、読み終えたときにはきっと、あなたもかまぼこが食べたくなり、誰かと語りたくなるはずです。
かまぼこの日(11月15日 記念日)の由来とは?
かまぼこの日が11月15日に定められたのは、偶然でも語呂合わせでもありません。
そこには、千年の歴史と、子どもを思う日本の親心が宿っています。
かまぼこの名前が文献に初めて登場したのは、なんと今から900年以上前のこと。
西暦1115年、永久3年に催された祝宴の膳の図に、「かまぼこ」と思われる料理が描かれていたのです。
この「1115」という数字。
これが「11月15日」という記念日にそのまま結びついたのです。
さらに、この日は日本では古くから「七五三」として知られています。
七五三は、子どもの成長を祝い、無事を祈る大切な節目。
そのお祝いの食卓に並ぶ定番が、紅白のかまぼこです。
鮮やかな紅と白。
それは、喜びと祈りの色。
古くから日本では、紅白は「ハレの日」に使われる特別な配色であり、祝いの席に欠かせない存在でした。
なぜ紅白のかまぼこなのか。
それは、ただ目出度いからだけではありません。
魚の身を練って作るこの食品は、「すり身」のように口当たりがやさしく、子どもでも食べやすい。
さらに、高タンパクで栄養価も高く、健康を願う親の想いとも重なります。
つまり、かまぼこは「愛情のかたち」なのです。
そうした理由から、11月15日は「かまぼこの日」として1983年(昭和58年)に制定されました。
決めたのは、当時の「全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会」。
今では「一般社団法人 日本かまぼこ協会」と名前を変え、水産練り製品の普及と文化の発信に尽力しています。
かまぼこの日(11月15日 記念日)に知っておきたい、かまぼこの豆知識
かまぼこは、ただの「おかず」ではありません。
それは、魚の命を、職人がその手で、新しい形に生まれ変わらせた芸術品です。
そのルーツは古く、はじめてその姿が記録に現れたのは1115年。
けれど、かまぼこが生きているのは、文献の中だけではありません。
現代の私たちの暮らしの中でも、しっかりと息づいています。
まず、かまぼこの語源をご存知でしょうか?
実は「蒲鉾」という言葉は、かつてのかまぼこの形に由来しています。
昔のかまぼこは、竹の棒に魚のすり身を巻きつけて焼いて作られていました。
その姿が「蒲(がま)の穂」に似ていたことから、「蒲鉾(かまぼこ)」という名がついたといわれています。
やわらかくて、しなやかで、でも芯があって。
どこか、子どもを思う親の心のようでもあります。
また、かまぼこは栄養価が高く、タンパク質を豊富に含んでいます。
魚を主原料としながら、骨がなく、小さな子どもでも安心して食べられる。
「骨なしシーフード」とも言われるほど、食べやすく、ヘルシーで、調理も不要。
そのまま切って、お皿に盛るだけで、食卓が華やぎます。
特に、紅白かまぼこは縁起物としても重宝され、年末年始や慶事の食事に欠かせない存在です。
紅は魔除け、白は清浄。
そこには、見た目の美しさ以上に、「願い」が込められているのです。
食べることが、誰かを想うことにつながる。
かまぼこには、そんな優しさが詰まっています。
かまぼこの日(11月15日 記念日)と深く関わる団体と人々の想い
「かまぼこの日」を単なる記念日に終わらせないように。
そんな強い想いを持って活動しているのが、「一般社団法人 日本かまぼこ協会」です。
この協会は、もともと1940年(昭和15年)に「全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会」として設立されました。
現在は、東京都千代田区に本部を構え、全国の水産練り製品業者とともに、かまぼこの普及、品質向上、文化継承のための活動を行っています。
協会の掲げるキーワードは、「フィッシュ・プロテイン」と「骨なしシーフード」。
それは、ただ栄養価の高い食品を作るだけでなく、安心・安全で、誰でも食べやすい製品を届けたいという想いの表れです。
活動内容は多岐に渡ります。
・全国蒲鉾品評会の開催
・職人向けの技術研修会
・子どもたちへの食育活動
・海外への日本食文化の発信
・「かまぼこの日」を通じた消費者への啓発キャンペーン
これらの活動の根底にあるのは、「かまぼこを未来に伝えたい」という想いです。
魚を愛し、技を継承し、日本の味を守ってきた職人たち。
その背中には、かまぼこへの誇りと情熱があります。
また、協会の活動によって、「かまぼこの日」には全国でイベントが開かれたり、各地のご当地かまぼこが紹介されたりと、少しずつ関心が広がっています。
かまぼこは、工場で大量に作られるだけの食品ではありません。
そこには、人の手の温もりと、地域の誇りと、長く紡がれてきた文化が息づいているのです。
全国に広がる「ご当地かまぼこ」の魅力〜かまぼこの日(11月15日 記念日)を彩る名産品たち〜
「かまぼこ」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、紅白の板かまぼこかもしれません。
けれど、その世界は想像以上に奥深く、地域ごとに個性豊かな「ご当地かまぼこ」が存在します。
それぞれの土地の風土や文化、漁場の特性が味に現れているのが特徴です。
ここでは、「かまぼこの日」にちなんで、全国各地の名産かまぼこをいくつかご紹介します。
宮城県の「笹かまぼこ」
笹の葉の形を模した、柔らかくてぷりっとした食感が特徴。戦後の復興期に生まれたとされ、今や宮城を代表する名産です。
シンプルな塩味から、チーズ入りや牛タン風味など、進化系も多彩です。
和歌山県の「なんば焼」
棒に巻き付けて焼く、伝統的なかまぼこのスタイルを継承。
焼き目の香ばしさと、ぎゅっと詰まった旨味がクセになります。
大阪府の「梅やき」
関西特有の甘めの味付けで、しっとりやわらかな食感。
名前に「梅」とありますが、梅の味がするわけではなく、形が梅の花に似ていることから名付けられました。
静岡県焼津市の「黒はんぺん」
一般的な白いはんぺんとは異なり、イワシなどの青魚を原料とするため色はグレー。
噛むほどに魚の旨味が広がり、フライにして食べるのが定番です。
徳島県の「なると巻」
ラーメンのトッピングでもおなじみ。渦巻き模様が特徴的で、縁起の良さから祝いの席にもよく登場します。
こうした地域のかまぼこは、土地の人々にとっては、ただの「おかず」ではなく、「ふるさとの味」です。
かまぼこの日をきっかけに、ぜひご当地の味にも触れてみてください。
かまぼこの日(11月15日 記念日)に関するよくある質問
Q1. かまぼこの賞味期限はどのくらいですか?
商品によって異なりますが、未開封で冷蔵保存なら約1週間〜10日ほどが一般的です。開封後は早めに食べ切るようにしましょう。
Q2. かまぼこは冷凍できますか?
できますが、食感が落ちやすいため、冷凍はあまり推奨されていません。どうしても保存したい場合は、なるべく空気を抜いて密封し、早めに使い切りましょう。
Q3. かまぼこはどうやって作られているのですか?
主に白身魚(タラ、イトヨリ、ベラなど)をすり身にして、塩や砂糖、でん粉などを加えた後、成形して蒸したり焼いたりして作ります。地域によっては揚げる製法もあります。
かまぼこの日(11月15日 記念日)まとめ〜祝いの気持ちを形にする、やさしい食文化〜
11月15日は、「かまぼこ」の記念日。
そこには、900年以上も前から日本人に親しまれてきた食文化の誇りと、子どもを想う優しい気持ちが詰まっています。
紅白の色に込められた願い。
骨がなく、やわらかくて、小さな子でも食べやすい形。
それは、祝いの場にふさわしい、思いやりの形です。
かまぼこは、古くから食卓の「縁起物」として、節目に寄り添ってきました。
七五三、正月、結婚式、長寿祝い…。
人生のあらゆる「おめでとう」の場面に、そっと彩りを添えてくれる存在です。
そして、ただの保存食でも、高級品でもなく、誰もが手に取れる価格で、誰かを想う気持ちを形にできる。
そんなかまぼこを、あらためて味わってみませんか?
今日の夕飯に、紅白の一切れを。
そして、それを食べる誰かの笑顔を思い浮かべてみてください。
かまぼこの日。
それは、食べ物に宿る「やさしさ」を思い出させてくれる、ちょっと特別な記念日です。