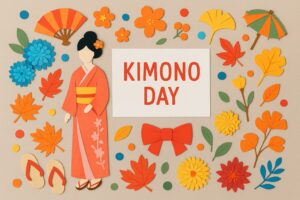きものの日はどんな日?
✅ きものの日の由来は、七五三に合わせて家族で着物を楽しむ文化を広めるため。
✅ きものの日の豆知識は、「着物」「呉服」の意味や、関連記念日の存在も含めた文化背景。
✅ きものの日と関わりの深い団体・企業は、全日本きもの振興会と日本きもの連盟。
和服を着ることで、家族の時間がもっと豊かになる
普段着慣れた洋服ではなく、少し背筋を伸ばして「着物」を着る日。そんな日が毎年11月15日、記念として「きものの日」として定められています。
ひとたび着物に袖を通すと、素材のひんやりした手触りや帯の結び目に、なんとも言えぬ“日常を超えた特別感”が生まれます。
この日をきっかけに、家族そろって着物で出かける時間が生まれれば、きっと会話も笑顔も、少し違って感じられるはずです。
この記念日を知れば、着物は難しいもの・格式ばったものという枠を超えて、「家族で楽しむ和装ライフ」の扉が開きます。
ここでは、きものの日の由来・豆知識・関係団体・よくある質問・そして“いま”すぐ実践できる楽しみ方まで、わかりやすくお伝えします。
「きものの日(11月15日 記念日)」の由来:七五三から着物文化を祝う日へ
1966年(昭和41年)に、和服文化の振興を願って、全国の着物関連団体が中心となって「きものの日」が制定されました。
具体的には、着物文化の普及を目的とする全日本きもの振興会の設立にあたり制定され、さらに全国約2000店の呉服店が加盟する日本きもの連盟も同日に制定しました。
この記念日が11月15日となったのは、まさに日本の伝統行事である七五三の日に重なっているからです。
七五三とは、3歳・5歳・7歳という子どもの成長を祝う節目の行事で、家族がそろって神社へ参拝し、晴れ着姿で写真を撮る姿が浮かびます。
この日に「家族そろってきものを着て出かけてほしい」「きもの姿が似合う子どもたちの成長を祝いたい」という願いが込められて、11月15日が「きものの日」として制定されたのです。
着物を通じて、和の文化・親から子への想い・家族の絆という三つのテーマが、この日には込められています。
制定当初から、きものの日には和装の魅力を知ってもらい、もっと日常に取り入れてもらおうという運動が各地で行われています。たとえば、着付け体験会、着物ファッションショー、和装で街歩きといったイベントが企画されています。
このように、11月15日はただの記念日ではなく、着物文化を「楽しむ」「体験する」「受け継ぐ」ための日なのです。
「きものの日(11月15日 記念日)」の豆知識:着物・呉服・そして楽しみ方
着物・呉服の言葉の意味
まず「着物(きもの)」という言葉ですが、元々は「着るもの=衣服全般」を表していました。
つまり、洋服・和服を問わず“体を覆うもの”が「きもの」でした。現代では一般に「和服」の意味で使われ、特に日本の伝統衣装を指します。
一方「呉服(ごふく)」という言葉は、もともと絹織物を指す語として使われてきました。古くは、中国の「呉」の国から伝わった高級織物を「呉服」と呼んだとされ、綿や麻などの「太物(ふともの)」と区別されていました。
現在では、「呉服屋」というと和服用の織物・着物・帯・小物を扱う専門店を指す言葉として広く使われています。
こうした用語を知っておくと、呉服店で聞く“プロの言葉”も理解しやすくなります。
他の記念日との関係
きもの文化を祝う日は他にもあります。例えば:
- 2月10日:太物の日(「ふ=2」「と=10」の語呂合わせ)
- 5月29日:呉服の日(「ご=5」「ふ=2」「く=9」の語呂合わせ)
これらの記念日を併せて知ると、年間を通じて「和装文化を楽しむ季節感」が見えてきます。
着物を着ることのメリット
- 素材感や帯の締め心地により、背筋が自然と伸び、所作が整うように感じます。
- 普段とは違う装いによって、写真を撮りたくなったり、家族でのお出かけが特別な思い出になることが多いです。
- 着物姿を見た子どもたちが「お母さん、きれいだね」と言ってくれたり、祖母から「私も若いころにこうだったのよ」と昔話が飛び出したり、会話が弾みやすくなります。
つまり、着物は「ただ和服を着る」以上に、「伝統を感じる」「親子・家族で時間を共有する」「記念として残せる」そんな価値があるのです。
普段着としての着物のヒント
- 初めてならレンタルがおすすめ。帯や小物のセットでプロに着付けてもらえます。
- 色・柄は季節に合わせて選ぶと楽しい。紅葉の時期なら落ち着いた深い色合いが似合います。
- 和装でお出かけするなら、足元(草履)や裾の動きに注意して、安全に楽しみましょう。
これらの豆知識を頭に置けば、11月15日のきものの日がぐっと身近になります。
「きものの日(11月15日 記念日)」に関わる団体と人物:文化を支える裏舞台
着物文化の振興を支えているのが、いくつかの団体そして専門店です。
全日本きもの振興会(AJKF)
この団体は、着物文化の普及を目的に1966年に設立され、同時に「きものの日」を制定しました。全国で和装イベントを企画・運営し、伝統と新しい和装スタイルの橋渡し役を果たしています。
例えば、「街歩ききものDAY」「着物ファッションショー」「ママ・キッズ着物体験」など、年齢問わず楽しめるプログラムを提案しています。
日本きもの連盟
全国約2000店の呉服店が加盟する大きな組織です。地域の呉服店と連携し、11月15日に向けてキャンペーンを展開したり、着物をもっと気軽に着られるような施策を行っています。
呉服店での相談会や着付け講座など、実践的なサポートも提供しています。
家族・地域のきもの文化を支える人々
着物文化は“店だけ・団体だけ”では成り立ちません。母や祖母、親戚など、“着物を身にまとう世代”の存在が、次世代に「着物っていいね」と思わせてくれる原動力になります。
着付けを教えてくれた母、草履を揃えてくれた祖母、その一挙手一投足が文化の継承です。
さらに、子どもたちが七五三で着物を着たときの笑顔を見て、「また家族で着物で出かけようね」という言葉が自然と生まれます。それこそが、きものの日が目指す“文化の輪”なのです。
行政・観光・文化施設の協力
地方自治体や観光協会、文化施設もこの日を機に和装イベントを後押ししています。着物で入館料が割引になる博物館や、和装者限定のスタンプラリーなど、地域の魅力と和装を結びつけた企画が増えています。
このように、「きものの日」は団体・店舗・家族・地域が手をつなぎ、和装文化を楽しむ場をつくっています。
「きものの日(11月15日 記念日)」に関するよくある質問
Q1. 『きものの日』って何をしたらいいの?
この日は、家族や友人と一緒に着物を着て出かけるのがベストです。例えば、神社や公園、美術館など“少し格式や風情のある場所”を選ぶことで、和装姿が映えます。
レンタル着物+着付けサービスを活用すれば手軽に参加できます。さらに、呉服店や文化施設では特別キャンペーンやワークショップも開催されているので事前に情報チェックしてみると良いでしょう。
Q2. 着物を持っていないけど、やっぱり参加できる?
もちろん大丈夫です。近年では、レンタル着物・小物付きプラン・家族向けセットなどが充実しており、初心者にも安心です。
どうしてもハードルが高く感じる方は「半襟・帯・草履だけレンタル」など部分的な参加も可能です。さらに、「帯だけ変えてみる」「羽織だけ着てみる」など“和装風アレンジ”から始めるのもおすすめです。
Q3. 子どもと一緒に着物を楽しめる?
はい、ぜひ楽しめます。もともとこの日の起点となったのが「七五三」であるため、子どもの成長を祝う意味が深く含まれています。
子ども用の着物レンタル・写真撮影会・きもの体験イベントも各地で行われています。
保護者の方も一緒に和装で参加すれば、家族写真の思い出が一段と深まります。ゆったり帯を結び、草履の音を聞きながらの散策も、大人にとっては新鮮な体験です。
Q4. 着物を着るときに気をつけた方がいいことは?
着物を着ると“所作”にも自然と意識が向きます。歩幅を少し小さめに、裾・帯・草履の位置を意識することで、装いがより美しく映えます。
そして、着物は素材によって季節感が出るため、11月15日のような秋深まる時期には、少し落ち着いた色・柄、小物に季節のモチーフ(紅葉、菊、銀杏など)を取り入れるのもおすすめです。
さらに、着付けの締め付けや帯の硬さによって長時間着ると疲れやすくなるので、事前にリハーサルしておくと安心です。
きものの日(11月15日 記念日)をもっと楽しむためのアイデア
家族での着物コーデをプラン
11月15日は家族そろって、きものを着てお出かけしてみましょう。例えば、朝は祖母・母・娘の三世代で着物姿。帯を結ぶ姿を見て、小学生の娘が「私もこの帯に挑戦してみたい」と言い出す。
そんな風景が自然に生まれます。記念写真も、リビングでスマートフォン撮影でも十分。秋の柔らかな光の中、紅葉を背景に歩くとそれだけで絵になります。
レンタル&着付け体験で気軽にトライ
着物はハードルが高いと思われがちですが、レンタル+プロの着付けサービスが普及しています。
呉服店や観光地では“一日きもの体験”プランが豊富です。帯や小物を選ぶ時間も楽しい時間。時間に余裕をもって予約して、着付け後にカフェや街散策に出かけるのがおすすめです。
きもので街歩き・撮影会を楽しむ
着物で外に出ると、歩くだけで視線を集める存在になりますが、それが「今日」の特別感を演出します。
街の風景、歴史ある建物、紅葉の並木道など、フォトジェニックな場所を探して、家族や友人と撮影会をしてみましょう。スマホでも十分魅力的に撮れます。
「帯の柄を背景に収める」「足元の草履と石畳を入れる」など、少しだけアングルを工夫すると写真に深みが出ます。
着物好きの仲間・地域イベントに参加
きものの日には、地域の文化施設・呉服店・観光協会がイベントを行うことが多いです。例えば、和菓子屋さんとコラボして「きもので和菓子セット」を楽しむ企画や、着物姿で入館無料/割引になる博物館など。
「きもの姿の人だけ得する日」として活用するのも一案です。仲間を誘って、いつもと少し違う1日を演出しましょう。
着物を着た後にも「振り返り」を
着物を着た1日の終わりには、家族で写真を見ながら「今日はどうだった?」と振り返る時間を持つと、記憶が深まります。
「帯がきれいに結べたね」「草履の音がいいね」「また来年も着ようね」そんな言葉が交わされることで、きものの日は“年に一度の文化イベント”から“家族の思い出の一部”へと昇華します。
まとめ:きものの日(11月15日 記念日)を、今日から身近な楽しみに
11月15日のきものの日は、和服文化を「特別」なものではなく「家族で楽しむもの」へと変えるチャンスです。
着物を通じて、親から子へ、祖母から孫へと“伝える思い”が自然に広がります。着物姿には、素材や色柄の美しさだけでなく、背筋が伸びる凛とした所作、笑顔を誘う家族の気持ち、そして写真に残る記憶が詰まっています。
今年の11月15日、ほんの少し着物を着て出かけてみませんか。レンタルでも、帯だけ挑戦でも、羽織だけでも。
まずは“一歩”を踏み出すことが大切です。和装を身近に感じて、いつもと違う時間を過ごしたら、きっと「ああ、私たちにも似合うね」「また来年も着ようね」といった会話が生まれます。
その小さな“きものタイム”こそが、家族の絆を深め、日常に彩りを添えるきっかけになります。きものの日をきっかけに、和の装いを、暮らしの中にもっと自然に取り入れてみてください。
――和装の喜びを、家族の笑顔とともに。
今年の11月15日が、あなたと大切な人たちにとって、少し特別な“和の時間”となりますように。