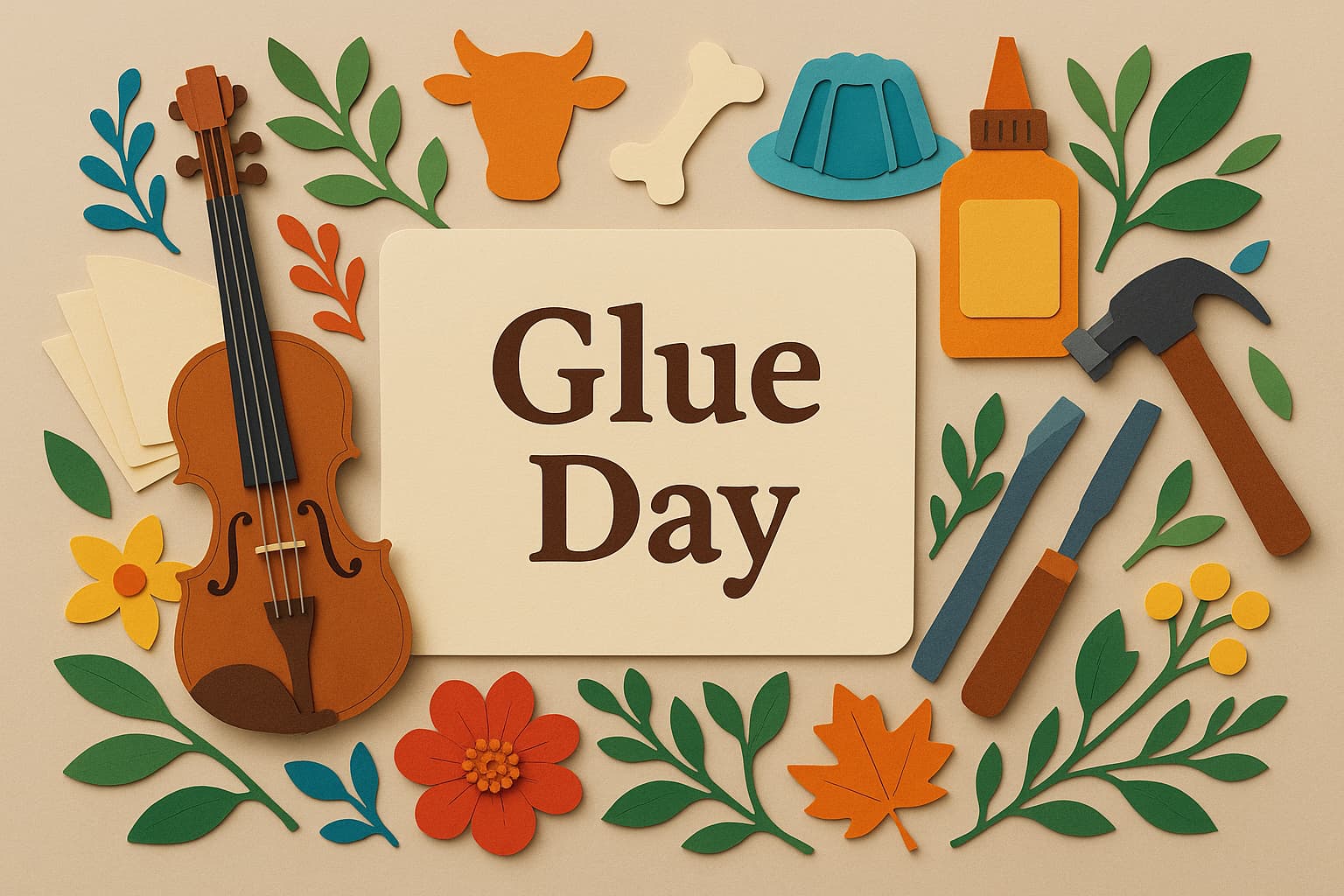にかわの日はどんな日?
✅ にかわの日の由来は、1963年11月7日に 日本にかわ・ゼラチン工業組合 の創立総会が行われたことによる。
✅ にかわの日の豆知識として、「にかわ(膠)」は動物の皮や骨を原料とする天然の接着剤で、その成分がゼラチンであり、環境に優しい素材とされている。
✅ にかわの日と深い関わりがあるのは、 日本ゼラチン・コラーゲンペプチド工業組合(およびその前身「日本にかわ・ゼラチン工業組合」)であり、この団体が記念日を制定・普及している。
「にかわ」という言葉を聞いたことがありますか?弦楽器の接着、美術工芸の修復、さらには動物由来のゼラチン素材へとつながる、この「にかわ(膠)」は、実は長い時間をかけて人々の文化や産業を支えてきた天然接着剤です。
11月7日には、その歴史と価値を見直す記念日「にかわの日」があります。
1963年(昭和38年)に日本にかわ・ゼラチン工業組合の創立総会が開かれたこの日に制定され、環境への配慮や伝統技術の継承、そして素材としての魅力を発信することが目的となっています。
伝統素材の「にかわ」がいかにして現代に活きているのか、その背景とともに、知っているとちょっと自慢できる豆知識をご紹介します。
にかわの日の由来 ~伝統素材を見つめ直す日~
「にかわの日」が11月7日に定められた理由は、現在の団体の前身である「日本にかわ・ゼラチン工業組合」が1963年11月7日に大阪会館で創立総会を開催し、本格的な活動を始めたことに由来します。
この組合はその後、現代の 日本ゼラチン・コラーゲンペプチド工業組合 に引き継がれ、動物由来素材(ゼラチン・コラーゲン・膠=にかわ)を扱う産業の中心的な役割を担っています。
「にかわ」という言葉は漢字で「膠(こう/にかわ)」と書かれ、動物の皮・骨・腱などからコラーゲンを抽出・煮溶かし、乾燥・粉末化して接着剤として用いた天然素材です。
この素材は、化学接着剤が一般化する以前から、美術工芸・建築・弦楽器製作などの分野で活躍してきました。
古代エジプトの調度品やピラミッド出土品からもにかわの残留物が確認されており、人類の歴史とともに歩んできた素材とも言えるのです。
こうした歴史的背景と、素材としての価値を改めて示す機会として、11月7日「にかわの日」は制定されました。天然素材としての優しさ、伝統技術の継承、そして環境への配慮という視点も含まれています。
にかわの日の豆知識 ~素材と文化のつながり~
まず、にかわの成分には「ゼラチン」と同じくコラーゲンが含まれており、食品用途で使われるゼラチンの「原点」とも言える素材です。
次に、にかわが持つ特性として「温めると柔らかく、冷やすと固まる」という性質があり、この熱可逆的な挙動が、木材や楽器、和紙といった伝統素材と相性が良いのです。
木材の接着に用いると、湿度や気温の変化に伴う伸縮にも対応しやすいというメリットがあります。
そのため、弦楽器(例えばヴァイオリンやチェロなど)の製作・修復には、いまもにかわが用いられることがあります。古くは美術工芸品や建築物、文化財修復の現場でも活用されてきました。
さらに、現代においては化学接着剤や合成接着剤に含まれる化学物質への懸念(例えばシックハウス症候群、化学物質過敏症)がある中、天然由来のにかわ素材が「環境に優しい」「人体への負担が少ない」手法として再評価されています。
そして面白い点として、「にかわ」は工芸・文化保存・楽器・皮革という一見異なる分野をつなぐ素材でもあります。
皮革製造から出る副産物を活用することで「廃棄物を減らす」「資源を循環させる」といった観点もあり、持続可能な社会を考える上での素材としても注目されます。
にかわの日に関わる組織・素材 ~背景にいる団体と素材そのもの~
まず、この記念日を制定したのは、現在の日本ゼラチン・コラーゲンペプチド工業組合であり、前身の日本にかわ・ゼラチン工業組合が1963年11月7日に創立総会を実施し、その日を「にかわの日」として定めました。
この組織は、ゼラチン・コラーゲン・にかわの原料・加工・用途に関する産業団体として、素材の安全性・普及・情報発信・業界の連携を行っています。
食品・医薬・工芸・建築・皮革など多岐にわたる分野を扱っており、「にかわ」が持つ可能性を幅広く示しています。
一方、「にかわ(膠)」という素材そのものは、動物の皮・骨・腱などのコラーゲン含有部位を水で煮溶かし、純化・濃縮・乾燥したものからできており、用途としては接着剤・画材・楽器製作・文化財修復などに使われてきました。
例えば、木材同士を貼り合わせる際、自然の伸縮性に追随できるにかわは、合成接着剤とはまた違った「修復時に剥がしやすい」「再接着が可能」などの利点もあります。これは、文化財修復の分野では非常に重要なポイントです。
こうした背景から、「にかわの日」は素材そのものへの理解を深め、いかに私たちの生活・文化・産業に根ざしてきたかを再認識する日と言えます。
にかわの日に関するよくある質問
Q1. 「にかわ(膠)」と「ゼラチン」はどう違うの?
A. どちらも動物由来のコラーゲンが原料ですが、用途・精製度が異なります。一般に「ゼラチン」は食品・医薬品用途として高い純度・安全性が求められるもので、「にかわ(膠)」は接着剤や工芸・楽器用途に用いられてきたものです。
また、「にかわ」は加熱すれば溶け、冷やせば固まる性質を生かして、楽器や修復用途で「取り外し・再接着」が可能な役割も担ってきました。
Q2. なぜ「動物の皮や骨」から作るの?現代では合成素材じゃないの?
A. にかわが誕生したのは化学合成接着剤が発展する前の時代であり、動物の皮や骨、腱などの「コラーゲン」が自然に持つ接着力・機械的特性を利用してきたためです。
現代でも、修復・楽器・文化財など「時代を経ても長持ちさせたい」「素材を傷めたくない」といった用途では、合成素材よりも自然素材の特性が評価されています。環境配慮・健康配慮という観点から再び注目されているという背景もあります。
Q3. 「にかわの日」をどう過ごせばいい?何かできることは?
A. まずは「にかわ」について少し学んでみることがオススメです。例えば、弦楽器(ヴァイオリンなど)の製作・修復ににかわが使われていることを調べてみると、新しい視点が開けます。
また、文化財修復、美術工芸、伝統技術といった分野に興味を持つきっかけになるかもしれません。
「素材そのもの」に目を向けることで、私たちの暮らしや文化がどれだけ“縁の下の力持ち”に支えられてきたかを知ることができます。
SNSで「#にかわの日」とタグ付けして豆知識を発信するのも、小さな楽しみ方のひとつです。
「にかわの日」のまとめ
11月7日の「にかわの日」は、伝統的な天然接着剤「にかわ(膠)」にスポットを当て、その歴史・素材としての価値・そして現代での可能性を見つめ直す記念日です。
1963年11月7日に日本にかわ・ゼラチン工業組合が創立総会を開いたことを契機に、現在の日本ゼラチン・コラーゲンペプチド工業組合が制定しました。
にかわは、動物由来の皮や骨から抽出されるコラーゲンを活用し、楽器や工芸、建築、文化財修復など多岐にわたる用途で活用されてきた素材です。
現代では「環境に優しい」「天然素材」という観点でも再評価されており、私たちの暮らしや文化を支えてきた“縁の下の力持ち”としての存在に気づくきっかけになります。
「素材を知ることで文化を知る。文化を知ることで未来を考える。」というUSP(独自の価値)を心に留め、11月7日にはにかわという素材の背景に想いを馳せてみてはいかがでしょうか。
今日は何の日(11月7日は何の日)
立冬(11月7日頃) | 紀州・山の日 | ロシア革命記念日 | 鍋の日 | もつ鍋の日 | 知恵の日 | 釧路ししゃもの日 | いい女の日 | 鍋と燗の日(11月7日頃) | にかわの日 | ソースの日 | いいおなかの日 | 立冬はとんかつの日(11月7日頃) | 夜なきうどんの日(11月7日頃) | 腸温活の日 | ココアの日(立冬 11月7日頃) | マルちゃん正麺の日 | HEALTHYA・日本製腹巻の日 | 湯たんぽの日(立冬 11月7日頃) | いいレナウンの日 | なまえで未来をつくる日 | いい学びの日 | あられ・おせんべいの日(立冬 11月7日頃) | 感染症に備える日(立冬 11月7日頃) | FPの日(11月6日・7日) | 生パスタの日(7月8日、毎月7日・8日) | Doleバナ活の日(毎月7日) | 読書週間(10月27日~11月9日) | 海と灯台ウィーク(11月1日~8日) | レントゲン週間(11月1日~8日) | 低GI週間(11月1日~7日) | 年金週間(11月6日~12日) | ダブルソフトでワンダブル月間(11月1日~30日)