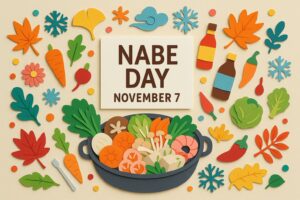鍋の日(11月7日 記念日)はどんな日?
✅ 鍋の日の由来は「立冬」と鍋料理のシーズン到来を結びつけたことにある。
✅ 鍋料理には「鍋奉行」や「アク代官」などユニークな文化が存在する。
✅ 記念日を制定したのは、だしで有名なヤマキ株式会社である。
鍋の日(11月7日 記念日)家族の絆を深める美味しい記念日
寒さがじわじわと増してくる11月初旬。
そんな季節にぴったりの記念日が「鍋の日(11月7日)」です。
鍋料理は、体を温めるだけでなく、家族や仲間との距離を縮める魔法の食卓。
「今日は鍋にしようか?」という一言で、食卓には笑顔が広がり、心もほっこり温まります。
この記念日は、だし文化を支える老舗・ヤマキ株式会社が制定したもので、寒さの入り口にあたる「立冬」とのタイミングも重なっています。
家庭で手軽に味わえる美味しい鍋つゆの魅力や、鍋料理をめぐるユニークな文化に触れることで、「鍋の日」がもっと好きになる。
この記事では、「鍋の日」の由来から、豆知識、記念日に関わる人物や企業まで、深掘りしてご紹介します。
読めば、きっと今夜は鍋が食べたくなるはずです。
鍋の日(11月7日 記念日)の由来とは?心も体も温まる日
「鍋の日」は、愛媛県伊予市に本社を構えるヤマキ株式会社によって制定された記念日です。
ヤマキといえば、かつお節やだしをはじめ、和食文化の根幹を支える食品メーカーとして知られています。
この記念日が11月7日に設定された理由は、日本の暦の上で「立冬」に当たる日であることが多いためです。
「立冬」は、冬の始まりを告げる季節の節目。
その日を「鍋の日」と定めることで、「そろそろ鍋が美味しい季節ですね」というメッセージを発信し、食卓に季節感と団らんの温もりを届けたいという願いが込められています。
また、11月7日前後は気温がぐっと下がり始める時期でもあるため、自然と鍋が恋しくなる季節。
この絶妙なタイミングを捉えた「鍋の日」は、まさに暮らしに寄り添った記念日だと言えるでしょう。
記念日は、日本記念日協会によって正式に認定・登録されており、今や冬の食卓に欠かせない存在として、広く知られるようになっています。
鍋の日(11月7日 記念日)にまつわる豆知識が面白い!
鍋料理には、ただ「食べる」だけではない、独自の文化やルールが存在します。
そのひとつが「鍋奉行(なべぶぎょう)」という存在。
これは、具材を入れる順序、火加減、つゆの管理などを厳密に仕切る人のことを指します。
さらに、鍋奉行よりもさらに口うるさく、厳格に鍋の進行を仕切る人を「鍋将軍」と呼ぶこともあります。
そして、灰汁(あく)を取り除く役目を担うのが「アク代官」。
こうした言葉からも、日本人の鍋へのこだわりと愛着の深さがうかがえます。
また、鍋料理の種類も非常に多彩です。
「寄せ鍋」「ちゃんこ鍋」「すき焼き」「しゃぶしゃぶ」「おでん」「もつ鍋」「豆乳鍋」「キムチ鍋」「ミルフィーユ鍋」など、地域や家庭によって好みもさまざま。
最近では「闇鍋」と呼ばれる、何が入っているかわからないスリリングな鍋スタイルも話題です。
これらの多様な鍋文化は、「鍋の日」にこそ再発見したい日本の食の魅力。
鍋を囲んで、話題が広がるのも魅力のひとつです。
鍋の日(11月7日 記念日)を作った企業「ヤマキ株式会社」とは?
「鍋の日」を制定したヤマキ株式会社は、1917年創業の老舗企業で、日本のだし文化をけん引する存在です。
中でも人気なのが「だし屋の鍋」シリーズ。
このシリーズは、ヤマキの強みである「だし」の風味を最大限に活かした鍋つゆで、家庭でも本格的な味わいが楽しめると評判です。
ラインナップには、「寄せ鍋つゆ」や「ちゃんこ鍋つゆ」など、魚介や地鶏などの素材を活かしたバリエーションが揃い、どれも塩分控えめで後味すっきり。
「最後まで飲み干したくなる鍋つゆ」として、多くの家庭の食卓に支持されています。
ヤマキは、ただ商品を売るだけでなく、日本の食文化を守り、次世代に継承するという使命感を持っています。
「鍋の日」を通じて、だしの魅力や、家族とのつながりを大切にする時間を提案する姿勢は、まさに食文化企業の鑑。
記念日をきっかけに、ヤマキの商品を手に取ってみるのも、鍋ライフをより豊かにする第一歩となるでしょう。
鍋の日(11月7日 記念日)に関するよくある質問
Q1:なぜ11月7日が「鍋の日」なのですか?
A1:「立冬」にあたる日であり、鍋料理が美味しくなる季節の始まりだからです。
Q2:「鍋の日」は誰が制定したのですか?
A2:だしや鍋つゆを製造するヤマキ株式会社が制定しました。
Q3:「鍋の日」におすすめの鍋料理は何ですか?
A3:人気の「寄せ鍋」や「ちゃんこ鍋」、地域の名物鍋などが定番です。
鍋の日(11月7日 記念日)まとめ:鍋を囲んで心もほっこり
「鍋の日(11月7日)」は、寒くなる季節にぴったりの、心と体を温める記念日です。
だし文化を牽引するヤマキ株式会社が提案するこの日には、家族や友人と鍋を囲む温かな時間を過ごす意味が込められています。
「鍋奉行」や多彩な鍋料理、そして本格的なだしの魅力を再発見することで、いつもの食卓が少し特別になる。
季節の変わり目に、「鍋の日」をきっかけに心を通わせる食事を楽しんでみてはいかがでしょうか。
今日は何の日(11月7日は何の日)
立冬(11月7日頃) | 紀州・山の日 | ロシア革命記念日 | 鍋の日 | もつ鍋の日 | 知恵の日 | 釧路ししゃもの日 | いい女の日 | 鍋と燗の日(11月7日頃) | にかわの日 | ソースの日 | いいおなかの日 | 立冬はとんかつの日(11月7日頃) | 夜なきうどんの日(11月7日頃) | 腸温活の日 | ココアの日(立冬 11月7日頃) | マルちゃん正麺の日 | HEALTHYA・日本製腹巻の日 | 湯たんぽの日(立冬 11月7日頃) | いいレナウンの日 | なまえで未来をつくる日 | いい学びの日 | あられ・おせんべいの日(立冬 11月7日頃) | 感染症に備える日(立冬 11月7日頃) | FPの日(11月6日・7日) | 生パスタの日(7月8日、毎月7日・8日) | Doleバナ活の日(毎月7日) | 読書週間(10月27日~11月9日) | 海と灯台ウィーク(11月1日~8日) | レントゲン週間(11月1日~8日) | 低GI週間(11月1日~7日) | 年金週間(11月6日~12日) | ダブルソフトでワンダブル月間(11月1日~30日)