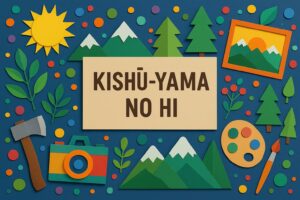紀州・山の日(11月7日 記念日)
✅ 明治期からの山祭りの慣習に基づき、旧暦11月7日に山の神をまつった山村の伝統を顕彰する日。
✅ 和歌山県が1994年(平成6年)に制定し、「山林への理解と関心を深め、人と山が共生する山村づくり」を目的としている。
✅ 関わりの深いのは和歌山県および紀州地域の山村・森林関係団体、フォトコンテスト/絵画コンクール運営団体。
「山に感謝する日」があれば、都会の喧噪を離れて森の深さや静けさを感じるきっかけになる。
そんな日が、紀州の山村にはあります。11月7日は、和歌山県が制定した「紀州・山の日」。
紀州の山々を育み、山の恵みとともに暮らしてきた山村の暮らしや風習から生まれた記念日です。
なぜこの日が選ばれたのか、どんな思いが込められているのか。地元の山林や人々の営みに思いを馳せながら、この記念日の由来や豆知識、深く関わる人物・団体まで、じっくりと掘り下げてみましょう。
この記事を読めば、「紀州・山の日」がどんな意味を持つ日なのか、そして自分も誰かに紹介したくなるような“話のタネ”も手に入ります。
「紀州・山の日」の由来―山と人がともに歩んだ歴史のひとコマ
「紀州・山の日」が生まれた背景には、紀伊(紀州)地域の山村で古くから受け継がれてきた風習があります。
紀州の奥深い山村では、旧暦の11月7日に、山の神を祀り、山仕事の無事や山の恵みに感謝し、山の繁栄を祈願する山祭りが行われていました。
和歌山県はこの伝統に着目し、1994年(平成6年)に「紀州・山の日」を制定しました。
この制定は、ただ地域の行事を記念するだけでなく、「山林に対する理解と関心を深め、人と山が共生する山村づくりを啓発する」ことを目的としています。
旧暦の日付をそのまま採用している点も特徴的で、地域の風土・歴史を色濃く残す記念日であると言えます。
特に和歌山県は、「紀伊木の国(木国)」とも称されたほど森林資源に恵まれた土地で、山村の暮らしが深く根付いてきた地域。
そうした環境・歴史を踏まえて、この記念日が「11月7日」に設定されたことには、地域と山との共生というメッセージが込められています。
こうして、「紀州・山の日」は、単なる記念日という枠を超え、山と人、人と自然が向き合ってきた時間を振り返る機会でもあるのです。
「紀州・山の日」にまつわる豆知識―知っておきたいトリビア
「紀州・山の日」には、地域ならではの興味深いエピソードや取り組みがあります。
まず、フォトコンテストや絵画コンクールが定期的に実施されており、たとえば2009年(平成21年)度のフォトコンテストでは「熊野黎明」という作品が“全国植樹祭賞”を受賞しました。
テーマは「緑の神話 今 そして未来へ 紀州木の国から」。冬の朝、夜明け前の冷たい空気の中、霧が雲海に変わる瞬間を捉えた作品で、山々の美しさと神々しさが表現されています。そんな切り口からも、山への“畏敬”と“感謝”がストレートに伝わってきます。
また、和歌山県が「木の国」と呼ばれた由来にも触れておくと、雨が多く森林が生い茂る様相から「木国(きのくに)」という表記があったという説もあります。
このように地名や文化のルーツまで山・森とのつながりが深い地域です。
さらに、旧暦に基づいたこの日付設定は珍しく、山祭りが旧暦11月7日に行われていたことを尊重しています。
つまり、現代の暦(新暦)では11月7日という形で残されているものの、その背景には旧暦・山村・祭りという複雑な歴史があるわけです。
こうした豆知識を知ることで、この記念日が単なる「山の日」ではなく、「地域の歴史・文化・暮らし」が詰まった日であることがわかり、家族や友達に「こんな背景なんだよ」と話すと興味を引くと思います。
「紀州・山の日」と関わりの深い人・団体・地域―山村の声を聞く
この記念日は、特定の有名人物というよりは、地域に根付く暮らし・文化・団体との関わりが濃厚です。
まず、制定主体であるのは 和歌山県。森林・山村地域の活性化や、人と山との共生のメッセージを発信している自治体です。
また、山村での山林管理・保全に取り組む地元の林業団体・森林組合なども、このような日を通して活動の理解を深めています。
さらに、フォトコンテストや絵画コンクールを運営・支援する地域の文化団体・教育機関も関わっており、子どもから大人までが「山」に目を向ける機会を提供しています。
たとえば、先に触れた「熊野黎明」の写真受賞作品は、地域の木材・山林文化をテーマにしており、まさに「紀州木の国」という地域ブランドともリンクしています。
地域として注目すべきなのは、紀州の山村そのもの。
かつて山林を守り、森の恵みに寄り添って暮らしてきた人々の営みが、今も伝統行事や祭り、そしてこの記念日を通じて継承されています。そうした「山村の暮らし」を支えてきた住民・地域団体が、この日の主役とも言えるでしょう。
「紀州・山の日」に関するよくある質問
Q1:なぜ11月7日が「紀州・山の日」なのですか?
この日は、紀州の山村で旧暦11月7日に山の神を祭る山祭りが行われていた慣習に着目して、和歌山県がその日付けを記念日に制定したためです。
旧暦の日付をそのまま新暦に当てはめる形で「11月7日」となっており、単に暦の上で日付が決まったのではなく、地域の年中行事と結びついたものです。
Q2:この記念日を通じてどんな活動が行われていますか?
和歌山県を中心に、「紀州・山の日」フォトコンテストや絵画コンクールが実施されています。
テーマには「山の恵み」「森と人の共生」「山村の風景」などが掲げられ、参加者が山村や山林、地域の自然に目を向けるきっかけとなっています。これらの活動を通じて、山林保全や山村文化への理解が深まることが目的です。
Q3:この記念日は全国的な「山の日」と同じですか?
いいえ、少し異なります。全国的な祝日としての「山の日」は8月11日にあります。ですが「紀州・山の日」は、和歌山県が地域の山村・山林文化を後世に伝えるために制定したもので、日付も目的も地域性を重視しています。
つまり、山をテーマにした記念日は全国・地域の両方に存在するということです。
まとめ:「紀州・山の日」で思う、山と暮らしのつながり
山や森は、ただ背景として存在する景色以上のものです。地域の暮らし、文化、歴史、人の営みが密に結びついています。
和歌山県が11月7日に制定した「紀州・山の日」は、まさにその関係性を再認識する機会として生まれました。
この記念日を通じて、山林の恵みや、山村に暮らす人々の「山を敬い、守り、共に生きる」という姿勢に思いを巡らせることができます。
フォトコンテストや絵画コンクールなどをきっかけに、普段目にしない山の風景や山村の暮らしが、私たちの日常に“新しい視点”をもたらしてくれるかもしれません。
また、家族や友人との会話でも、この記念日の由来を話題に出せば、「なるほど、そういう背景があったのか」と共感を得られることでしょう。
山に感謝し、人と自然がともに歩む暮らしを思い描く。そんな機会として、ぜひ11月7日「紀州・山の日」を覚えておきたいものです。
今日は何の日(11月7日は何の日)
立冬(11月7日頃) | 紀州・山の日 | ロシア革命記念日 | 鍋の日 | もつ鍋の日 | 知恵の日 | 釧路ししゃもの日 | いい女の日 | 鍋と燗の日(11月7日頃) | にかわの日 | ソースの日 | いいおなかの日 | 立冬はとんかつの日(11月7日頃) | 夜なきうどんの日(11月7日頃) | 腸温活の日 | ココアの日(立冬 11月7日頃) | マルちゃん正麺の日 | HEALTHYA・日本製腹巻の日 | 湯たんぽの日(立冬 11月7日頃) | いいレナウンの日 | なまえで未来をつくる日 | いい学びの日 | あられ・おせんべいの日(立冬 11月7日頃) | 感染症に備える日(立冬 11月7日頃) | FPの日(11月6日・7日) | 生パスタの日(7月8日、毎月7日・8日) | Doleバナ活の日(毎月7日) | 読書週間(10月27日~11月9日) | 海と灯台ウィーク(11月1日~8日) | レントゲン週間(11月1日~8日) | 低GI週間(11月1日~7日) | 年金週間(11月6日~12日) | ダブルソフトでワンダブル月間(11月1日~30日)