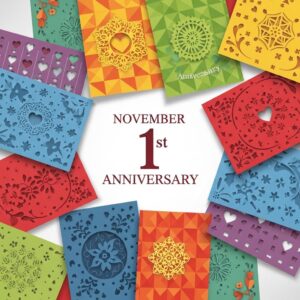「灯台記念日(11月1日)」はどんな日?
✅ 観音埼灯台の起工日であり、洋式灯台の導入を祝う日。
✅ 灯台記念日から8日間は「海と灯台ウィーク」となる。
✅ 海上保安庁が1949年に制定し、観音埼灯台が関わる。
11月1日は「灯台記念日」です。
灯台記念日が制定された背景には、1868年(明治元年)に神奈川県横須賀市の観音崎(観音埼)に日本初の洋式灯台である「観音埼灯台」が起工されたことに由来します。
観音埼灯台は、近代的な洋式灯台として日本における海上安全の象徴的な存在となり、その後の灯台建設に大きな影響を与えました。
観音埼灯台とは?
観音埼灯台は、横須賀市の観音崎に立つ、白色の八角形の灯台です。
初代の観音埼灯台は、煉瓦造りの洋式灯台として1868年に建設が始まりました。
この灯台は、フランスの技術者レオンス・ヴェルニーによって設計され、日本の近代化の先駆けとなりました。
初代の観音埼灯台は、その後大正時代に起きた関東大震災などの地震によって破損し、1923年と1925年に再建されました。現在の観音埼灯台は、三代目にあたります。
観音埼灯台の設計を担当したヴェルニーは、横須賀造兵廠や横須賀海軍施設の建設にも携わり、日本の近代技術の導入に大きな影響を与えた人物です。
灯台記念日の由来
灯台記念日は、観音埼灯台が起工された11月1日を記念して、1949年に海上保安庁によって制定されました。
当初は、洋式灯台の導入が日本文化の近代化を象徴するものとして意義深いとされ、11月3日の文化の日の前日である11月1日に記念日が定められたと言われています。
しかし、1970年に「灯台百年史」の編纂が行われた際に、観音埼灯台の起工日が11月1日であったことが判明し、それが灯台記念日の由来として広まったのです。
記念日の活動とイベント
灯台記念日には、全国の海上保安部などで記念行事が行われるほか、灯台周辺の観光協会などでも特別なイベントが開催されます。
特に、普段は立ち入ることができない灯台が、この日に合わせて公開されることがあり、内部を見学する貴重な機会が提供されることもあります。
観音埼灯台でも、通常では一般公開されない灯台内部を見学するツアーが開催されることがあります。
このようなイベントに参加することで、灯台の構造やその歴史的背景を直接感じることができ、海上保安の大切さを再認識することができます。
また、灯台記念日から8日間は「海と灯台ウィーク」として、灯台や海上保安に関するさまざまなイベントが全国で実施されます。
これは、灯台に関心を持ち、その役割や重要性を広く伝えるための取り組みです。
この期間中には、灯台の展示や海上安全に関する講演、地域での灯台巡りツアーなどが行われ、多くの人々が参加して灯台の魅力を再発見します。
観音崎の魅力
観音埼灯台が立つ観音崎は、自然豊かな場所でもあり、観光地としても人気のスポットです。
周囲には観音崎公園が広がり、散策路や展望台からは美しい海の景色を楽しむことができます。
また、灯台周辺は静かな環境に囲まれており、海の匂いや風を感じながらゆったりとした時間を過ごすことができます。
観音崎周辺の海は、東京湾や浦賀水道に面しており、航海の重要な通り道となっています。
観音埼灯台はその安全を守るために建てられ、今でも多くの船舶を照らし続けています。
そのため、灯台を訪れることは、ただ観光を楽しむだけでなく、海上交通の重要性について考える機会にもなります。
灯台記念日まとめ
11月1日の灯台記念日は、灯台の歴史やその役割を再認識する大切な日です。
観音埼灯台のような灯台は、長年にわたり多くの船舶を守り続け、今も海上交通の安全を支えています。
この記念日をきっかけに、灯台の魅力を感じ、海上保安に対する理解を深めてみてはいかがでしょうか。
灯台記念日を祝うことで、私たちの周りにある海上安全のための施設に感謝し、その大切さを再確認することができるはずです。