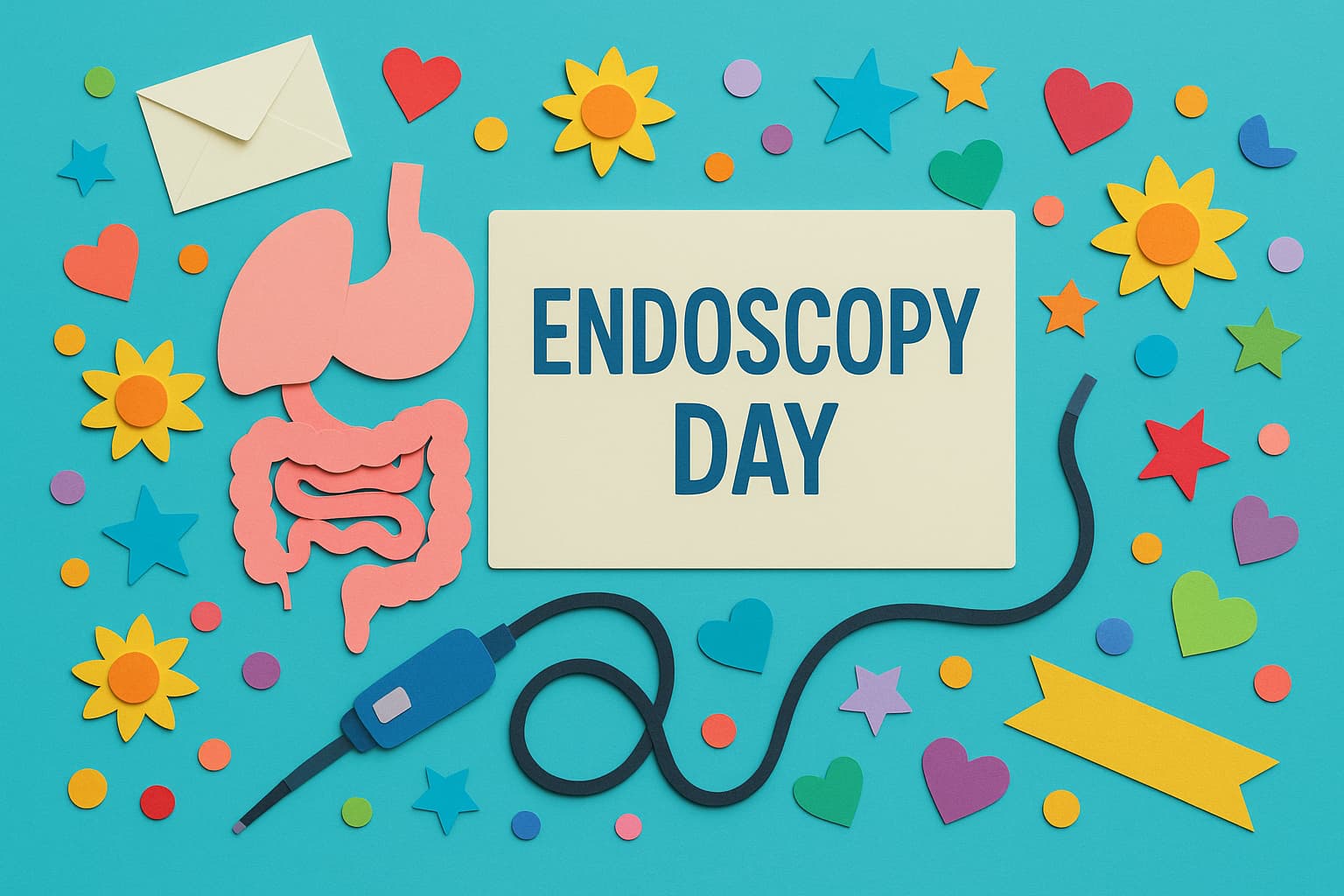内視鏡と聞いて、どんな印象を持ちますか?
「ちょっと苦しそう」「できれば受けたくない」
そんなネガティブなイメージを持つ方も少なくないかもしれません。
でも、内視鏡という医療技術がなければ、私たちは命を救うチャンスを見逃していたかもしれません。
実は、世界で初めて胃カメラによる撮影に成功したのは、日本なんです。
それを記念し、医療の進化と健康意識の向上を願って制定されたのが——
「内視鏡の日(7月14日)」
日付の由来は、「な(7)い(1)し(4)きょう」という語呂合わせ。
でも、そこに込められた意味は軽くありません。
がんの早期発見。
命を守る治療の最前線。
日々進化する医療の技術と現場。
この記念日は、まさに医療における“人類の叡智”を讃える一日なのです。
✅ 世界初の胃カメラ成功を日本が達成
✅ 語呂合わせで「ないしきょう」に由来
✅ 未来の医療と健康意識向上を願って制定
内視鏡の日(7月14日)はどんな日?
「内視鏡の日」は、2006年に公益財団法人 内視鏡医学研究振興財団によって制定されました。
この財団は、東京都渋谷区代々木に事務局を置き、内視鏡医学の研究・普及・教育を支援しています。
なぜ7月14日かというと、「な(7)い(1)し(4)きょう」という語呂合わせ。
このユニークな記念日の背景には、もっと深い医学史のドラマがあります。
1950年、日本の医師である杉浦睦夫博士が、世界で初めて胃カメラによる胃内撮影に成功。
それは、「見えなかった世界が、見えるようになった瞬間」でした。
医療はここから大きく進化を遂げていきます。
がんの早期発見が可能になり、治療方法もより安全に、より的確に。
人の命が救える確率が、ぐんと高くなった。
だからこそ、「内視鏡の日」はただの語呂合わせじゃなく、“日本の医療が世界を変えた日”を記念する象徴的な日でもあるのです。
内視鏡の日(7月14日)に知っておきたい3つの驚き
① 世界初の胃カメラは“鉄の筒”だった
初代の胃カメラは、今のように細くて柔らかいものではありませんでした。
直径1cm以上、全長約70cmの“鉄の筒”。
それでも、杉浦博士たちはこれを使って胃の内部を世界で初めて撮影したのです。
“鉄の筒”が、命を救う未来の扉を開いたのです。
② 現在では“カプセル型”もある
時は流れ、今では口から飲み込むだけのカプセル内視鏡が登場。
手のひらサイズのカプセルの中に、カメラ・照明・通信機能がすべて詰め込まれています。
まるで「医療版の宇宙探査機」。
このカプセルが腸内をゆっくりと旅しながら撮影を行い、体外のモニターで確認できるという、まさにSFのような技術です。
③ “早期発見で9割助かる”という現実
たとえば胃がん。
内視鏡でステージⅠ(初期)で発見された場合、5年生存率は90%以上と言われています。
これは、早期発見さえできれば“命が助かる”可能性が極めて高いという証。
つまり、内視鏡検査は“未来の自分を守る鍵”なのです。
内視鏡の日(7月14日)と深く関わる人物・団体
■ 杉浦睦夫博士
日本で最初に胃カメラを開発し、実用化に成功させた内視鏡技術のパイオニア。
彼の功績なしに、今の医療は存在しませんでした。
彼の挑戦は、「見えないものを見る」という医学の夢を現実に変えたのです。
■ 公益財団法人 内視鏡医学研究振興財団
内視鏡の研究を支援し、若手医師や研究者への奨学金提供、学術講演の開催など、内視鏡医療の普及と進化に大きく貢献しています。
「日本の内視鏡は世界を救う」——そんな信念をもとに、日々活動を続けています。
■ オリンパス株式会社など医療機器メーカー
日本を代表する光学機器メーカーであるオリンパスは、高性能内視鏡の研究・開発に長年取り組んできました。
現在では、世界中の病院でオリンパスの内視鏡が活躍しており、まさに“命をつなぐパートナー”として医療現場に寄り添っています。
内視鏡の日(7月14日)によくある質問
Q1. 内視鏡検査は痛いと聞きますが本当ですか?
A. 昔はそうでしたが、今は鎮静剤を使用するケースが多く、眠っている間に終わる「無痛内視鏡」も主流になっています。
経鼻内視鏡(鼻から挿入)など、苦痛を軽減した方法もあります。
Q2. 胃カメラと大腸カメラ、どちらも必要ですか?
A. 胃と大腸は別々の臓器で、それぞれリスクの高い病気があります。
40歳を過ぎたら、両方の内視鏡検査を定期的に受けることが推奨されます。
Q3. 内視鏡の日に何をすればいいの?
A. 検査を受けるきっかけにしたり、家族や友人と「健康」について語り合うのも素晴らしい過ごし方です。
内視鏡の歴史や感謝の気持ちを知るだけでも、医療への理解が深まります。
内視鏡の日(7月14日)のまとめ
内視鏡の日は、単なる医療技術の記念日ではありません。
1950年、世界に先駆けて胃カメラの実用化に成功した日本。
それは、見えない恐怖と闘い、命を守るための革新的な一歩でした。
その技術は時代とともに進化し、今や「命を救う精密な目」として、私たちの健康を支えています。
7月14日という日付に込められた「ないしきょう」の語呂合わせは、少しのユーモアと、日本人の知恵、そして医学の未来への希望を象徴しているのです。
この日をきっかけに、自分や家族の健康を振り返り、「内視鏡ってすごい」「検査、大事かも」と感じてもらえたら、この記念日は本当の意味で、命を守る記念日になるはずです。