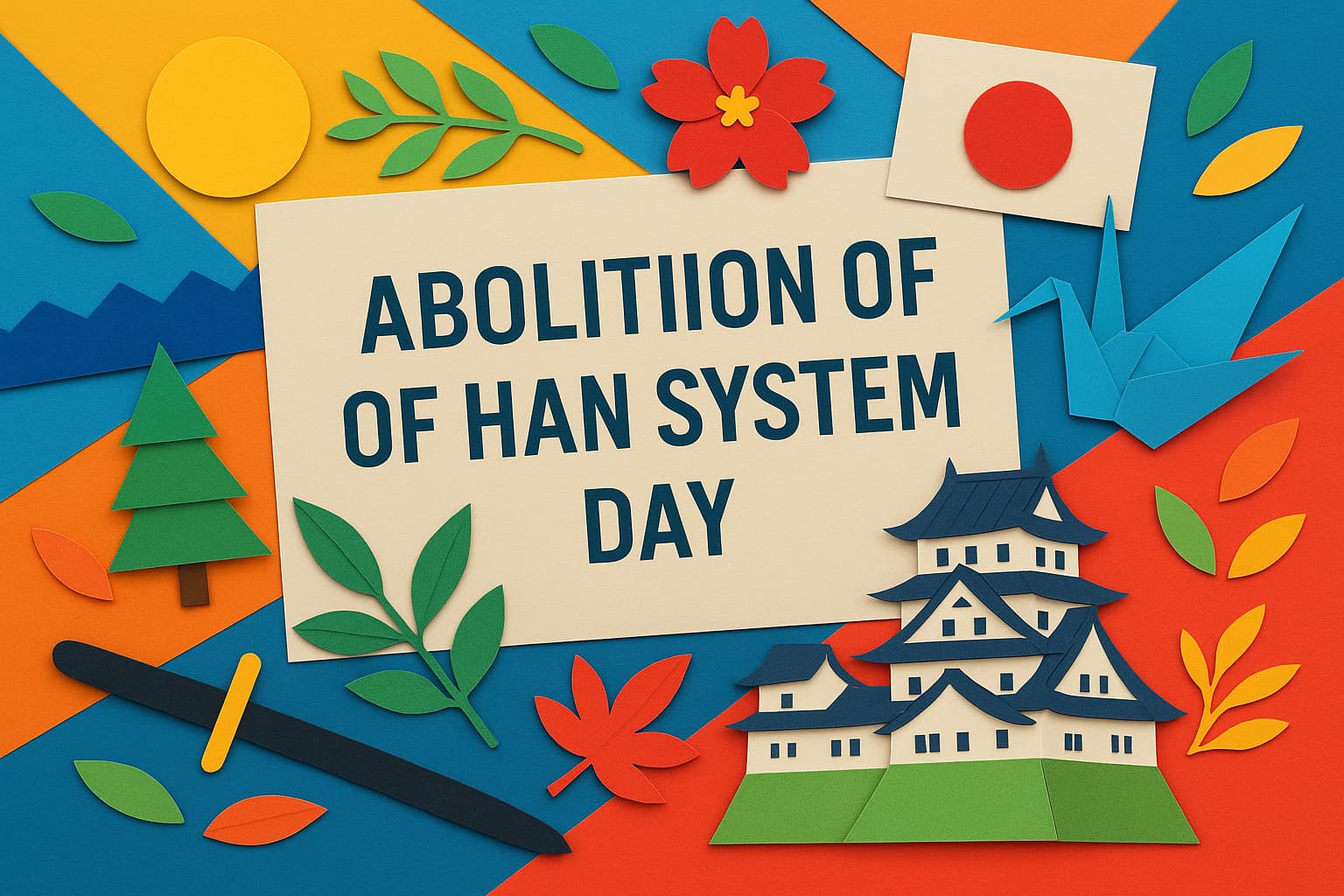あなたの住んでいる場所、○○県はどうして“県”と呼ばれているのか考えたことはありますか?
ふだん何気なく使っている“都道府県”という呼び名。
実はそれが誕生したのは、今から150年以上前、明治時代のある一大改革によってでした。
その名も「廃藩置県(はいはんちけん)」。
この制度改革は、明治政府が日本のすべての藩を廃止して“県”に置き換えた歴史的な大転換です。
つまり、私たちが知っている「○○県」という呼び方は、この“廃藩置県”によって全国に広がったものなんです。
しかもこの変化はただの名前の問題ではありません。
それまで個々の藩がそれぞれに政治を行っていた体制から、国家が一丸となって進む「中央集権国家」への第一歩。
この日がなければ、明治日本の近代化も、その後の経済発展も、今の社会の姿も存在しなかったかもしれません。
では、なぜこの改革が必要だったのか。
どんな人物たちが関わっていたのか。
そして、私たちの暮らしにどうつながっているのか――。
7月14日の「廃藩置県の日」を通して、今一度、日本という国のかたちを見直してみませんか?
廃藩置県の日はどんな日?
✅明治政府が藩を廃止し県を設置
✅中央集権体制の確立を目指す改革
✅都道府県制度の起源と背景を学べる日
廃藩置県の日の由来とは?制度改革の舞台裏に迫る
廃藩置県の日は、明治4年7月14日(新暦1871年8月29日)に発せられた明治政府の詔書に由来しています。
この日、日本全国にあった「藩」が正式に廃止され、新たに「県」が設置されました。
当時の日本は、明治維新によって江戸幕府が倒れ、天皇を中心とする国家体制へと移行したばかり。
しかし、依然として藩ごとに異なる通貨や法制度が存在し、統一国家としての体をなしていませんでした。
実は2年前の明治2年(1869年)には「版籍奉還」が行われており、藩主たちは名目上、領土と人民を天皇に返還していました。
とはいえ、旧藩主が「藩知事」としてそのまま藩を治め続けていたため、中央政府の力は十分に及んでいなかったのです。
このままでは、日本が欧米列強に並ぶ近代国家にはなれない――そう考えた明治政府の中心人物たちは、大胆な決断を下しました。
それが、「廃藩置県」。
全ての藩知事を免職し、中央政府から県知事を派遣。
さらに3府302県という細かすぎる区分を72県に統合し、行政の効率化も図りました。
この改革によって、中央政府ははじめて全国を一体化した統治体制を築き、明治日本の本格的な近代化がスタートしたのです。
廃藩置県の日に知りたい豆知識:「3府302県」はどうなった?
廃藩置県の直後、日本全国にはなんと302もの「県」が存在していました。
それに加えて、東京・京都・大阪の3つの「府」。
「そんなにあったの!?」と驚かれるかもしれませんが、これは各藩をそのまま「県」に置き換えた結果。
ところが、それではあまりに非効率。
たとえば、山口県の前身である長州藩だけでも複数の県に分割されていた時期もあります。
そこで政府は、改革後わずか半年で一気に統廃合を推進。
明治4年末には75県まで整理され、最終的には明治21年(1888年)に現在の「47都道府県」体制が整備されました。
また、当時の「県知事」には中央から派遣された官僚が就任。
その中には薩摩・長州・土佐・肥前といった維新の中心地から出た人材が多く含まれていました。
ちなみに、今の「都道府県」という言葉もこの流れの中で確立されたもの。
東京が「都」、大阪・京都が「府」、北海道が「道」、それ以外が「県」。
これらの呼称も、まさに廃藩置県から続く歴史の一部なのです。
廃藩置県の日に登場する人物たちの決断
この歴史的大改革の中心にいたのが、大久保利通。
維新三傑の一人として知られる彼は、廃藩置県を断行した立役者でした。
「このままでは日本はバラバラのまま。欧米列強に呑まれてしまう」
そんな危機感を抱いた彼は、旧藩主たちに辞職を迫り、自らも鹿児島藩(旧薩摩藩)の知事を辞任。
その行動が他藩に波及し、最終的に全国規模の廃藩置県が成功したのです。
また、木戸孝允(旧・桂小五郎)も長州藩の知事を辞任し、制度改革に尽力しました。
彼らの行動には、「私利私欲を捨てて国のために尽くす」という強い使命感が込められていたのです。
制度を支えたもう一つの要素が「家禄保障と華族制度」です。
中央政府は、旧藩主に対して家禄(生活保障)と華族の身分を与え、東京移住を促進。
これによって旧支配層の反発を抑え、混乱を最小限に抑えることができました。
廃藩置県は、実力と知恵、そして“人の誠意”が形にした制度改革だったのです。
廃藩置県の日に関するよくある質問Q&A
Q1:なぜ明治政府は「藩」をやめさせたの?
A1:各藩が独自の軍や通貨を持っていたため、統一国家として機能しなかったからです。近代化に向けた中央集権体制が必要でした。
Q2:県の数が最初302もあったのはなぜ?
A2:藩をそのまま「県」に置き換えたからです。その後、統合が進められて47都道府県になりました。
Q3:今の「都道府県」という言い方はいつできたの?
A3:明治時代の統合過程で定着しました。特に1888年の府県制整備以降、現在の形になりました。
まとめ:廃藩置県の日は「今の日本」の原点を知る記念日
7月14日の「廃藩置県の日」は、まさに今の日本の行政・地域区分のルーツをたどる記念日です。
この日、日本は藩という封建制度から脱却し、中央主導の国家運営へと生まれ変わったのです。
ただの制度変更ではありません。
その背景には、国家の未来を真剣に考えた志士たちの決断と行動がありました。
普段何気なく「○○県に住んでいます」と言っている私たち。
その“県”という言葉の重みに、少しだけ思いを馳せてみる。
それだけでも、この記念日は大きな意味を持つのではないでしょうか。