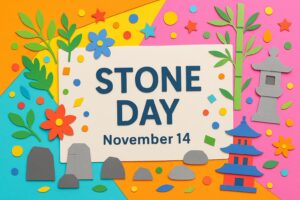いい石の日(11月14日 記念日)はどんな日?
✅ 「いい(11)いし(14)」の語呂と、石工職人が敬う聖徳太子の命日「太子講」に由来する日です。
✅ 石材加工技術や墓石・庭石の文化を広くPRするために設けられた記念日です。
✅ 山梨県石材加工業協同組合が制定し、日本記念日協会に登録された公式な記念日です。
石に宿る想いを、そっと感じる日
日々の暮らしの中で、石の存在を意識することはあまりないかもしれません。
でも、少し目を向けてみてください。
公園の一角に静かに佇む石灯籠。
庭先に置かれた苔むした飛び石。
そして、大切な人を偲ぶ墓石――。
それぞれの石には、誰かの想いや、職人の技、そして静かな時間が宿っています。
そんな石たちに改めて目を向ける記念日が、11月14日「いい石の日」です。
この日は、「いい(11)いし(14)」という語呂合わせに加え、石工たちが守護神として敬う聖徳太子の命日という、ふたつの意味が込められています。
石に込められた文化と技術、そして人の想いを知ることで、あなたの中にもきっと「石ってこんなに深いんだ」と感じる発見があるはずです。
この記事では、「いい石の日」が生まれた背景から、その魅力、私たちの日常とのつながりまで、じっくり丁寧にご紹介していきます。
読み終えるころには、あなたの暮らしの中の“石の風景”が、少し違って見えているかもしれません。
いい石の日の由来とは?〜語呂と伝統がつなぐ記念日〜
「いい石の日」が11月14日であるのは、「いい(11)いし(14)」という語呂合わせがひとつの大きな理由です。
でも、この記念日が“本当にいい日”である理由は、それだけではありません。
石材加工の職人たちの間で、大切にされてきた「太子講(たいしこう)」という行事があります。
これは、聖徳太子の命日にあたる日を、石工・左官・大工などの職能集団が守護神として崇敬し、感謝と研鑽の思いを込めて集う伝統行事です。
つまり、「いい石の日」はただの語呂合わせ記念日ではなく、職人たちの文化や信仰に基づいた“心ある記念日”でもあるのです。
この記念日は、1999年に山梨県石材加工業協同組合によって制定されました。
山梨といえば、長い歴史を持つ石材加工の産地。富士山の火山岩や甲府盆地の石材を使った墓石や庭石は、全国的にも高く評価されています。
制定の目的は次の3つです。
- 墓石を通じて先祖を敬い、供養する文化を守る
- 石を用いて美しい庭園や空間を創出する技術を継承する
- 石材加工の職人技を社会にもっと知ってもらう
この記念日があることで、一般の人々が石に触れる機会が増え、石材業界の魅力や価値が見直されるきっかけにもなっています。
石ってこんなに奥深い!いい石の日に知りたい豆知識
あなたの家の近くにある神社やお寺には、どんな石が使われているか、気にしたことはありますか?
材の種類や色、形にはすべて意味があり、場所や用途によって使い分けられています。
例えば墓石には、雨風に強い御影石(みかげいし)がよく使われます。
日本の御影石は、兵庫県の「庵治石(あじいし)」などが有名で、光沢が美しく、加工しやすいことから高級墓石にも使われています。
また、日本庭園に置かれた「景石(けいいし)」や「飛び石」は、単なる装飾ではありません。
見る角度や周囲の植物、光の入り方まで計算され、まるで自然の一部のように配置されます。
これらを設計・配置するのは「石組(いしぐみ)」と呼ばれる高度な技術。
職人は石の“癖”を読み、その場に最もふさわしい形で石を活かすセンスが求められます。
いい石の日には、こうした技術や文化をもっと身近に感じてもらうため、全国各地で次のようなイベントが行われます。
- 石材店による墓石・庭石の展示会
- 石のアート作品や絵画の展覧会
- 子ども向けの「石の工作教室」
- 石職人による実演イベント
子どもから大人まで楽しめる企画が盛りだくさん。
石に触れることで、その冷たさや重み、質感から「命の重さ」や「自然の力強さ」を感じることができるのです。
石と生きる人々~いい石の日に支える人たち
「いい石の日」があることで注目されるのが、石材加工に関わる人々の存在です。
石を扱う職人は、ただ力任せに石を削るわけではありません。
石の種類ごとに硬さや色味、割れやすさなどが違い、まるで“石と会話”をしながら仕事をしているかのようです。
ある石職人は、こう語ります。
「石には“目”がある。それを見極めて、割る角度を決める。間違えたら全部やり直し。でも、それがまた楽しいんです」
そうした技術と心を込めて、墓石が形作られ、庭石が並べられ、石碑が建てられていきます。
また、石材を製造・販売する企業も、この記念日を機に「石文化をもっと多くの人に届けよう」と情報発信を行っています。
加えて、日本記念日協会がこの記念日を公式に登録しており、記念日の認知を広げる役割を担っています。
そして忘れてはならないのが、太子講に込められた職人たちの“心”。
聖徳太子を敬うこの文化は、技術の継承だけでなく、「仕事をする上での誠実さ」「ものづくりへの敬意」を象徴するものです。
いい石の日は、そんな職人たちの努力と誇りを感じる一日でもあります。
いい石の日に関するよくある質問
Q. なぜ石の記念日が2つもあるの?
A. 実は、1月4日も「石の日」として知られています。
これは「い(1)し(4)」の語呂合わせに由来していて、主に石材業界の新年初仕事のスタートとされます。
11月14日の「いい石の日」は、より文化的・歴史的な意味合いを持ち、技術や職人の想いに焦点を当てた記念日です。
Q. 子どもでも楽しめるイベントはある?
A. はい、全国の石材店や地域団体では、「石に触れて遊ぼう」という趣旨のワークショップや石絵教室が開催されることもあります。
小さな石に絵を描いたり、積み上げて作品を作ったりと、五感で石を楽しむ体験ができます。
Q. 普段の生活で「いい石の日」を意識できることってある?
A. あります。例えば、家の庭に一つだけ“お気に入りの石”を置いてみる、散歩の途中で気になる石を見つけて写真を撮る。
それだけでも、石の魅力や自然の面白さを感じられます。
また、墓参りの際に墓石を少し丁寧に掃除することも、立派な「いい石の日」の過ごし方です。
いい石の日のまとめ~石と向き合うきっかけをくれる一日
「いい石の日」は、私たちが普段あまり意識しない「石」という存在に、あらためて目を向ける日です。
記念日という形を通じて、石に込められた技術、文化、職人の誇り、そして人々の想いを感じ取ることができます。
石は無口ですが、その存在には不思議な力とあたたかさがあります。
そして、それを活かす人の手によって、暮らしの中に静かに、確かに存在しているのです。
11月14日――ぜひ、あなたの身近な「いい石」にそっと触れてみてください。
その冷たさの中に、長い時間と物語が宿っていることに、きっと気づくはずです。