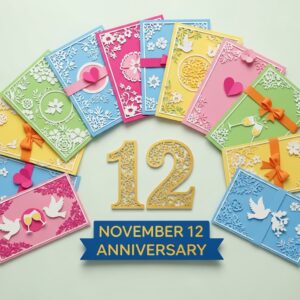「ベビーカーにやさしいまちづくりの日」はどんな日?
✅ 「ベビーカーにやさしいまちづくりの日」の由来は、“いい(11)まちで育児(12)しやすい環境づくり”という語呂合わせから11月12日に定められた記念日です。
✅ 「ベビーカーにやさしいまちづくりの日」の豆知識として、制定は一般社団法人「ベビーカーの利用環境づくり推進協議会」で、2016年(平成28年)に一般社団法人日本記念日協会により認定・登録されました。
✅ 「ベビーカーにやさしいまちづくりの日」と関わりの深い団体として、上述の協議会および日本記念日協会のほか、幼稚園・保育園、公共施設、商業施設などが積極的に環境整備に協力しています。
赤ちゃんをベビーカーに乗せて、初めてお散歩に出かけたあの日。ベビーカーを押しながら歩道の段差に気づき、少しハラハラしたこと、ありませんか?
雨の日に屋根の無いバス停で立ち止まったり、狭い店舗の入口で一度戻ったりした子育て世代は、皆どこかで「もう少しだけ、安心なまちだったら」と感じたことがあるでしょう。
そんな“ちょっとした不便”に気づいた人たちが、「ベビーカーでも安心して移動できるまち」をめざして声をあげ始めました。
そして11月12日は、そんな想いをかたちにした記念日――「ベベーカーにやさしいまちづくりの日」です。
この日をきっかけに、ベビーカー利用に配慮する設備の整備だけでなく、「まちをみんなで子育てしやすくしよう」という温かな動きが少しずつ広がっています。
この記事では、制定の背景から具体的な取り組み、そして地域やあなた自身ができるアクションまで、丁寧にご紹介します。読者が「誰かのため、そして自分自身のため」にこの日を覚えておきたくなるような内容です。
「ベベーカーにやさしいまちづくりの日」の由来・誕生の背景
この記念日を生んだのは、東京都中央区築地に事務局を構える一般社団法人「ベビーカーの利用環境づくり推進協議会」です。
子育て世代が外出する際に感じる“ちょっとした壁”をなくしたいという強い想いから、ベビーカー利用をきっかけにまちを見直す取り組みを推進してきました。
11月12日という日付には、「ベビーカーにやさしい=“いい”まちで育児(12)しやすい環境を」という語呂合わせが用いられています。つまり「いい(11)まちで育児(12)しやすい環境づくり」という思いが込められているのです。
この記念日は、2016年(平成28年)に一般社団法人「日本記念日協会」に認定・登録されました。
では、なぜこの時期に、ベビーカーという視点からまちづくりが注目されたのでしょうか。背景には、少子化の進行、都市部での子育ての複雑化、公共交通機関や商店街がベビーカー利用者にとって必ずしも使いやすくなかったという現実があります。
例えば、エレベーターがなかった地下鉄駅の階段、雨の日に屋根のない路線バス停、狭い歩道……こうした“移動の小さなストレス”が、子育て中の親にとっては日々の負担となっていました。
その一方で「子育てしやすいまち=暮らしやすいまち」という視点は、行政や地域においても重要なテーマとして浮上していました。
こうした社会的な流れと子育て世代の声が重なり、「ベビーカーにやさしいまちづくり」の提案が具体化。まちを設計する側、運営する側、そして利用する側が出会う節目として、この記念日が生まれたのです。
つまり、この記念日は「ベビーカー利用=子育て世代の支援」だけでなく、「誰でも安心して移動・利用できるまちづくり」につながる“入口”でもあります。
「ベベーカーにやさしいまちづくりの日」にまつわる豆知識
3つの目標を知ろう
この記念日を制定した協議会は、以下の3つを目標として掲げています。
- 幼稚園・保育園および公共施設に「ベビーカー置き場」の設置を促進する。
- 「オリジナルベビーマーク」を浸透させる。
- この記念日を啓発し、社会全体での意識を高める。
この3つを通じて、2020年の開催を前にした都心部での移動環境を、ベビーカー利用がしやすいように整備することも視野に入れられていました。
オリジナルベビーマークとは?
耳にしたことがあるかもしれませんが、「オリジナルベビーマーク」とは、ベビーカー利用者がスムーズに配慮を受けられるよう、街中に分かりやすく表示するマークのことです。
例えば、駐輪場ではなくベビーカー置き場として専用スペースがあることを示したり、交通機関や施設でベビーカー利用時の案内があることを知らせたりします。
このマークがあると、「あ、この施設はベビーカー利用でも安心だな」と親子が感じやすくなり、訪れるハードルがグッと下がります。
そして、街を歩くほかの人も「ベビーカー利用中の方がいますね。ちょっと配慮しよう」という気づきを持ちやすくなり、まち全体の雰囲気がやさしく変わっていくのです。
ベビーカー利用環境=子育てしやすさだけじゃない
一般に「ベビーカー利用環境の改善=子育て世代向け」と捉えられがちですが、実は幅広い世代が恩恵を受ける視点でもあります。
例えば、荷物が多い買い物帰りの方、高齢者が手押しカートを使う光景、体調が優れずゆっくり歩きたい方――こうした人たちにも、段差のない歩道、ベビーカー置き場のある施設、ゆったりとした移動動線はありがたいものです。
つまり「ベビーカーにやさしいまち」は「誰にとってもやさしいまち」であり、地域全体の暮らしの質を上げることにつながるのです。
実例:ちょっとした“支え”が安心になる
たとえば、ある保育園の玄関前にベビーカー専用の屋根付き置き場ができたことで、親御さんが雨の日に躊躇せず送迎できるようになったという声があります。
また、商業施設で「ベビーカーから降りずにそのままエレベーターで2階へ上がれます」という案内が掲示されるようになり、「ベビーカーでの移動が億劫でなくなった」と喜ばれた例もあります。
こんな“ちょっとした改善”が積み重なって、「あ、今日はベビーカー押しても気にせず行けそうだな」という安心感を育ちます。
こうした豆知識を知ることで、11月12日という記念日が「ただの語呂合わせの日」ではなく、まち、施設、私たち自身の関わり方を見直す機会であることが、自然に伝わるはずです。
「ベベーカーにやさしいまちづくりの日」と関わる団体・組織・地域の人たち
この記念日の動きを支えるのは、以下のような人・団体・地域の力です。
一般社団法人ベビーカーの利用環境づくり推進協議会
東京都中央区築地に事務局を置くこの協議会が、記念日の制定、目標設定、啓発活動を主導しています。ベビーカー利用者の声を集め、まちづくり関係者と対話を続ける“橋渡し”役も担っています。
日本記念日協会
記念日として制定・登録されたのは2016年(平成28年)で、同協会による認定により社会的な認知を得ることができました。
地域自治体・公共施設・商業施設・交通事業者
例えば自治体では歩道の段差解消、スロープ設置、ベビーカー置き場の整備を推進。交通事業者ではベビーカーのまま乗降できる案内や座席、ベビーカー帯の確保など、取り組みが少しずつ増えています。
商業施設では、「ベビーカー入り口」「授乳・おむつ替え室」「ベビーカー置き場」を明示することで、親子連れの不安を軽減する工夫がなされています。
地域住民・子育て中の親御さん・ボランティア
記念日の啓発活動や、施設利用時の配慮、親同士の情報共有など、現場の“声”が動きを支えています。たとえば、子育てサークルが「ベビーカー立ち寄りマップ」を作成して、地域の散歩コースとして紹介する活動もあります。
こうした“現場の声”があるからこそ、まちが少しずつ変化していくのです。
企業(ベビーカー貸出サービス・設備メーカー等)
最近では、ベビーカーを観光地や商業施設で気軽にレンタルできるサービスが登場し、まちづくりの一環として紹介されるようになりました。こうした新しいサービスも「ベビーカーにやさしい環境」には欠かせません。
このように、「ベビーカーにやさしいまちづくりの日」は、単に“記念日”という枠を超えて、制度・施設・地域・サービス・個人という多様な立場の人たちが連携する“きっかけの日”なのです。
「ベベーカーにやさしいまちづくりの日」に関するよくある質問(FAQ)
Q1.「うちのまちにはベビーカー置き場がないけど、どうすればいい?」
A.まずは、地域の幼稚園、保育園、公共施設(図書館・支援センターなど)の担当窓口に「ベビーカー置き場の設置希望」を伝えてみましょう。
押し出しポイントとしては、「ベビーカー利用の親子の動線がわかる」「雨天時の避難ルートになっている」「ベビーカーで入館する人の声がある」という実例を挙げると説得力が増します。
さらに、記念日11月12日を活用して、地域の子育て支援団体と協力し「ベビーカー利用マップを作ろう」「ベビーカー置き場の写真を集めよう」といったワークショップを開催するのも効果的です。
Q2.ベビーカー利用中に公共交通機関で困った経験があります。どう動けばいい?
A.ベビーカーを使って公共交通を利用する際のポイントとして、以下が挙げられます:
・事前に駅・バス停のベビーカー対応状況を調べる(案内掲示やホームページ)
・混雑時間を避け、余裕のある時間帯に移動する
・ベビーカーを畳むタイミング・荷物を分散させるなど工夫をする
・周囲に「お先に失礼します」と声をかけることで、配慮を受けやすくなる
さらに、「ベビーカーにやさしいまちづくりの日」を機に、交通事業者に「ベビーカー利用者目線」のアンケートをお願いしてみるのも良いでしょう。どこでつまずいたかを可視化することで、改善につながる動きが生まれます。
Q3.この記念日を活用して、地域や家庭でできることは何?
A.この記念日を「きっかけの日」として活用するために、以下のアクションがおすすめです:
・家族や友人と「ベビーカーでお出かけしたときの“ちょっと困った”体験」をシェアする。意外と共感されて話題になります。
・近くの施設(公園・図書館・商店街など)にベビーカー利用しやすいかチェックして、「ここ良かった」「ここもう少し改善欲しい」というレポートを作る。
・地域の子育てグループや自治体に、「11月12日にはベビーカー利用者を歓迎する日」という掲示・イベントを提案する。例えば「ベビーカー置き場増設キャンペーン」「ベビーマーク配布」「ベビーカー利用写真コンテスト」など。
・自宅から出発してベビーカーで散歩する際に、“ベビーカーで安心して歩ける”ポイントを意識してみる。例えば歩道の段差、入口の広さ、エレベーターの場所――“ひとつ気づく”ことが、まちの未来を変える一歩です。
こうした小さなアクションが積み重なれば、地域全体に「ベビーカー利用でも安心だ」という空気が生まれ、子育て世代だけでなく、幅広い住民にとって快適なまちづくりにつながっていきます。
「ベベーカーにやさしいまちづくりの日」のまとめ
「ベベーカーにやさしいまちづくりの日」は、11月12日に定められた記念日で、ベビーカー利用者が安心して移動できる環境を社会全体でつくろうという想いが込められています。
制定したのは、東京都中央区築地に事務局を置く一般社団法人ベビーカーの利用環境づくり推進協議会。語呂合わせ「いい(11)まちで育児(12)しやすい環境づくり」から日付が選ばれ、2016年に日本記念日協会により登録されました。
この記念日は、単にベビーカー利用を支援するという意味だけでなく、「誰もが安心して歩けるまち」「子育てしやすいまち」を実現するためのひとつの“入口”です。幼稚園・保育園、公共施設、商業施設、交通機関、地域住民、企業――多くの人が関わることで、まちの空気や設備が少しずつ変わってきています。
あなたもこの11月12日を機に、「ベビーカー利用でも安心なまちってどんなだろう?」と一歩立ち止まってみると、新たな視点が得られるかもしれません。小さな変化が、大きな安心につながります。
そして、家族と、友人と、地域と、「ベビーカーにやさしいまち」を育てる話題をぜひ共有してみてください。
今日は何の日(11月12日は何の日)
洋服記念日 | 皮膚の日 | 「四季」の日 | コラーゲンペプチドの日 | ベビーカーにやさしいまちづくりの日 | いいにらの日 | パレットの日 | 留学の日 | マイクロニードル化粧品の日 | AI音声活用の日 | 豆腐の日(10月2日・毎月12日) | 育児の日(毎月12日) | パンの日(毎月12日) | わんにゃんの日(毎月12日) | モンテール・スイーツの日(毎月第2水曜日) | 心平忌 | 島尾忌 | 年金週間(11月6日~12日) | 秋季全国火災予防運動(11月9日~15日) | ダブルソフトでワンダブル月間(11月1日~30日)