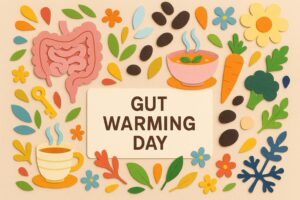腸温活の日はどんな日?
✅ 「腸温活の日」の由来は、二十四節気の「立冬」(11月7日頃)にあたり、昼夜の温度差が大きく腸の働きが低下しやすいため、腸を温めて整える「腸温活」を意識してもらおうと制定された日。
✅ 豆や昆布・食物繊維製品を扱う フジッコ株式会社(兵庫県神戸市)が制定し、2016年(平成28年)に 一般社団法人 日本記念日協会 により認定・登録された記念日。
✅ 「腸温活の日」と深く関わるのは、フジッコ株式会社と、二十四節気「立冬」、および食物繊維を用いた食習慣の普及活動。
冬の足音が近づく頃、朝夕の冷え込みや昼夜の寒暖差が気になりませんか。
そんな時期にこそ注目したいのが「腸温活」です。11月7日は「腸温活の日」。
この日は、腸を温めて整える習慣を見直し、身体の内側から調子を整えるきっかけとして設けられました。
実は、腸は“第二の脳”とも呼ばれ、免疫機能や体調とも深く結びついています。腸が冷えて働きが弱まると、便通の乱れだけでなく、全身の不調にも繋がる可能性があります。
だからこそ、冷えが気になる季節、11月7日というタイミングで「腸を温める活動(腸温活)」を意識してみる価値があります。
ここでは、「腸温活の日」がなぜこの日に決まったのか、どんな豆知識があるのか、また制定に関わった団体や企業などを丁寧にご紹介します。
家族や友人にも「へぇ、そうなんだ!」と話したくなるようなエピソードを交えてお届けします。温かい朝食とともに、腸を温めて元気に冬を迎えましょう。
「腸温活の日」の成り立ちと背景
「腸温活の日」は、まず“11月7日”という日付の選定からユニークです。
これは二十四節気のひとつ「立冬」にあたり、冬の始まりを告げる時期。昼間と夜の気温差が急に大きくなり、身体(特に腸)の調子が乱れやすいタイミングとされています。
こうした気候条件を背景に、腸が冷えることで働きが弱まり、消化・吸収・排泄・免疫などの機能が鈍くなる恐れがあることが指摘されました。そこで「腸を温める活動=腸温活」を広めようという動きが生まれました。
そしてこの活動を企業が起点として展開しています。豆、昆布、食物繊維製品で知られる神戸のフジッコ株式会社が、「朝の食物繊維入り温かい食事で腸を温める」という考えを掲げ、「腸温活プロジェクト」を発足。2016年には、日本記念日協会により「腸温活の日」が正式に認定・登録されました。
このように、気候・体調・食習慣という3つの切り口を掛け合わせ、単なる“語呂合わせ”ではなく「体調を整えるための実践的な日」として策定されています。腸を温める暮らし習慣を、11月7日を機に見直してみる──これが「腸温活の日」の本質です。
「腸温活の日」にまつわるちょっとした話
「腸温活」という言葉自体は比較的新しく、「温活(身体を温める活動)」と「腸活(腸の健康を整える活動)」を融合させた造語的側面があります。
特に「朝食で腸を温める」ことに着目した点がユニークです。フジッコ株式会社のプレスリリースによると、「朝のたべるスープ」シリーズなどを通じて「朝の温活」に着目した商品展開を行っており、腸温活を広めるためのPRを実施しています。
また、「腸温活の日」が11月7日ということもあって、様々な業種がこの日に合わせたキャンペーンや情報発信を行っています。例えば、温かい食事を推奨する飲食店や、腸を整えるヨガ・温活イベントなど。
腸を温めることで、体温が上がりやすくなり、免疫力・代謝・血流・消化力などが活性化するという説もあります。
実際、冷えが続くと便通が悪くなったり、風邪を引きやすくなったりする人もいるため、腸を温める=健康の“内側からの土台づくり”として捉えられています。
また、豆・昆布・食物繊維というキーワードも、この日の背景に深く関わっています。フジッコはこれらを活用して「温かい朝ごはん+食物繊維」で腸を労る生活を提案しているのです。これを知ると、「腸温活の日」が単なる“記念日”以上の意味を持っていることが見えてきます。
「腸温活の日」とつながるキープレイヤー
「腸温活の日」の制定・普及に関して、いくつかの主要な人物・団体が挙げられます。
まず、制定元としてのフジッコ株式会社。本社は兵庫県神戸市中央区にあり、伝統的に豆、昆布、その他食物繊維素材を扱ってきた企業です。
フジッコは「腸温活プロジェクト」を立ち上げ、朝食や腸の健康を意識した商品・情報を発信しています。
次に、登録認定団体である一般社団法人 日本記念日協会。2016年に「腸温活の日」を認定登録し、記念日の公的な基盤を築きました。
これは、多数の企業・団体から提案された記念日の中でも、明確な目的(腸を温めること)と日付の根拠(立冬)を備えていたためです。
さらに、食物繊維・温活・腸活を専門的に取り扱う医療・健康関連のクリニックや施設でも、この記念日を契機に啓発を行うケースがあります。
例えば、腸を温めることによる免疫力向上や冷え対策を紹介する医療機関のブログでも「11月7日=腸温活の日」として記されています。
これらの団体・機関が連携することで、「腸温活」という言葉が一般消費者にも浸透しつつあります。
そして、この日の啓発を通じて「食物繊維入りの温かい朝食をとる」「腸を冷やさない睡眠・入浴環境を整える」など、具体的な生活習慣の改善につながる流れが生まれています。
「腸温活の日」に関するQ&A
なぜ「腸」を“温める”ことが大切なのですか?
昼夜の寒暖差が激しい季節になると、腸の血流が滞ったり、消化・吸収のリズムが乱れたりしやすくなります。
腸が冷えると、その働きが落ちて便通や免疫力に影響が出る可能性があります。腸を温めて、消化・免疫・排泄のリズムを整えることが「腸温活」の目的のひとつです。
「腸温活の日」にはどんなことをするといいですか?
具体的には、朝に温かい食事をとることが推奨されています。特に、食物繊維を豊富に含む豆や昆布、根菜類などを温かいスープや雑炊などで摂ることで、腸が活動を始めやすくなります。朝の一杯の白湯をプラスするのも効果的です。
この記念日はどのような背景でつくられたのですか?
11月7日あたりの立冬時期は、気候の変化が激しく、特に腸の機能が低下しやすい時期という観点から、腸を温める「腸温活」を呼びかけるために設定されました。
食品メーカーであるフジッコ株式会社が「腸温活プロジェクト」を立ち上げ、2016年に日本記念日協会により正式に認定・登録されたことが制定背景です。
「腸温活の日」をきっかけに腸をいたわる習慣を
「腸温活の日(11月7日)」は、寒さが本格化する前夜のようなこの時期に、“腸を温めて整える”という新しい視点を提供してくれます。
腸は体調・免疫・代謝とも密接に関係しており、朝の温かい食事や食物繊維の摂取、腸を冷やさない生活環境は、冬を元気に乗り切るうえで有効です。
紹介したように、単なる記念日にとどまらず、日常生活をちょっと見直すきっかけとして有用です。
腸を温める「腸温活」を意識して、冷えやすい季節だからこそ、内側から調子を整えていきましょう。
今日は何の日(11月7日は何の日)
立冬(11月7日頃) | 紀州・山の日 | ロシア革命記念日 | 鍋の日 | もつ鍋の日 | 知恵の日 | 釧路ししゃもの日 | いい女の日 | 鍋と燗の日(11月7日頃) | にかわの日 | ソースの日 | いいおなかの日 | 立冬はとんかつの日(11月7日頃) | 夜なきうどんの日(11月7日頃) | 腸温活の日 | ココアの日(立冬 11月7日頃) | マルちゃん正麺の日 | HEALTHYA・日本製腹巻の日 | 湯たんぽの日(立冬 11月7日頃) | いいレナウンの日 | なまえで未来をつくる日 | いい学びの日 | あられ・おせんべいの日(立冬 11月7日頃) | 感染症に備える日(立冬 11月7日頃) | FPの日(11月6日・7日) | 生パスタの日(7月8日、毎月7日・8日) | Doleバナ活の日(毎月7日) | 読書週間(10月27日~11月9日) | 海と灯台ウィーク(11月1日~8日) | レントゲン週間(11月1日~8日) | 低GI週間(11月1日~7日) | 年金週間(11月6日~12日) | ダブルソフトでワンダブル月間(11月1日~30日)