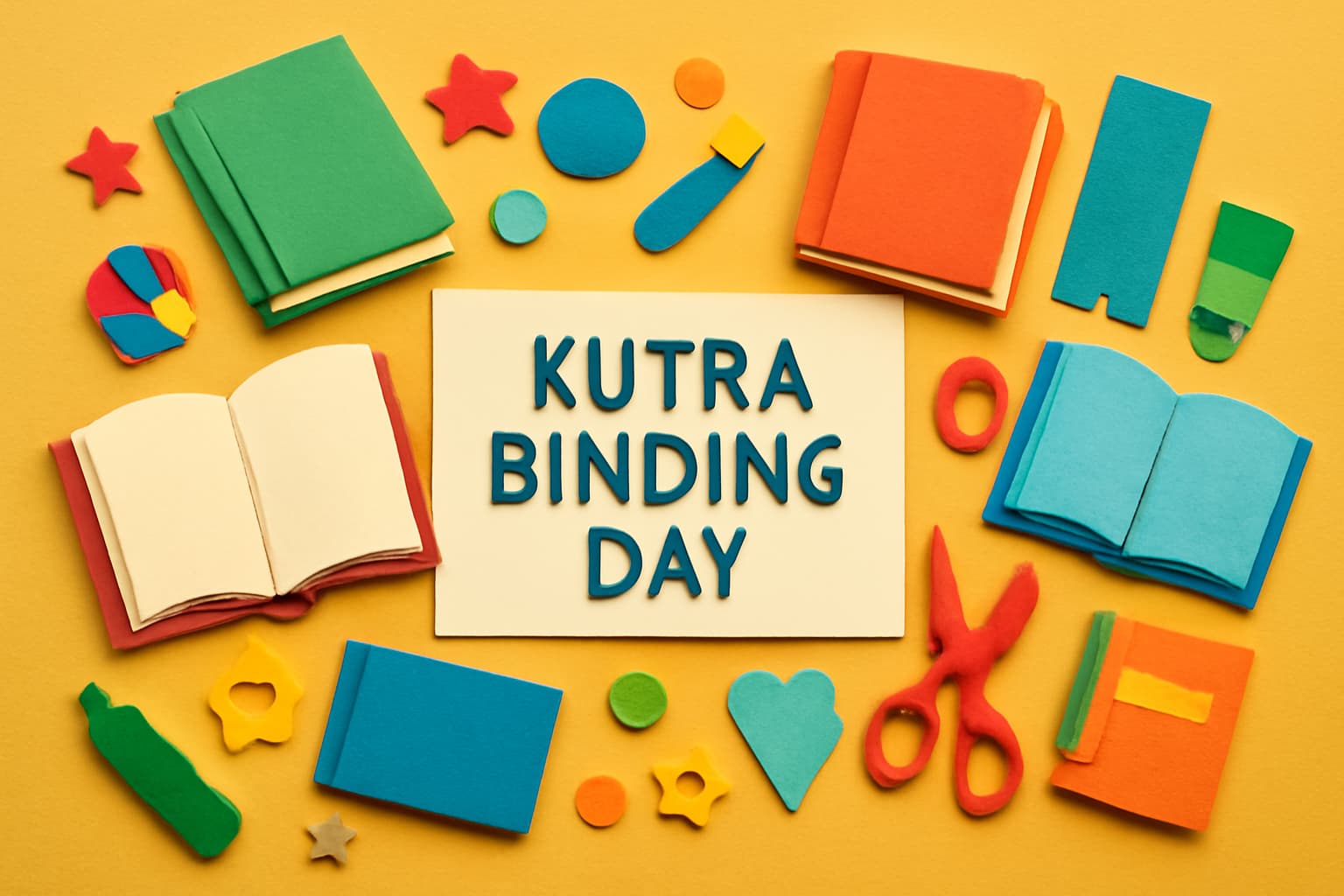クータ・バインディングの日(9月8日 記念日)はどんな日?
✅ クータ・バインディングの日(9月8日)は、株式会社渋谷文泉閣が「閉じない製本法」の普及を目的に制定した記念日
✅ 秋の読書シーズンに合わせ、「ク(9)ータ」と「バ(8)インディング」の語呂合わせにちなんでいる
✅ 開発元の株式会社渋谷文泉閣と、認定団体の日本記念日協会が深く関わっている
料理中にレシピ本が閉じてイライラ…そんな日常に終止符を打った「クータ・バインディング」
「あっ、ページが閉じた!」
料理をしているとき、レシピ本を開いているはずなのに、ふとした拍子にページが勝手に閉じてしまう。
しかも手はベタベタ。
「なんで本って、こんな時に限って閉じるの?」
そう思ったこと、きっと誰にでもあるのではないでしょうか。
そんな悩みを見事に解決したのが、「クータ・バインディング」という製本技術です。
手で押さえなくても本が自然と開いたままキープできるこの仕組みは、まさに“かゆいところに手が届く”ユニバーサルデザイン。
そしてこの素晴らしい技術をもっと多くの人に知ってもらうために、長野県の出版社・株式会社渋谷文泉閣が9月8日を「クータ・バインディングの日」として制定しました。
それは、「読書の秋」にちなんだ季節感と、「ク(9)ータ・バ(8)インディング」の語呂合わせが重なった、記念日にぴったりの1日なのです。
クータ・バインディングの日の由来とは?なぜ9月8日?
この記念日は、渋谷文泉閣が手がけた「閉じない製本」の普及を願って制定されました。
読み手が手を使わずにページを開いたままにできるこの技術は、読書環境を劇的に改善する発明です。
とくに実用書、例えば:
- 料理本
- パソコンや家電の取扱説明書
- 教科書やワークブック
- 作業マニュアル
こうした「両手を使う場面」で読む本において、その価値は計り知れません。
日付の「9月8日」には、以下のような意味が込められています。
- 「クータ・バインディング」の「ク(9)」と「バ(8)」の語呂合わせ
- 読書の秋が始まる季節
- 新学期・新生活で教科書や参考書が必要になるタイミング
まさに“知る人ぞ知る、でも知ったら絶対に話したくなる”ような記念日なのです。
この日は、一般社団法人・日本記念日協会により正式に認定・登録されています。
実はすごい技術!クータ・バインディングの秘密と魅力
クータ・バインディングとは、「本が自然に開いたまま、閉じない」製本方法のこと。
開いた状態で本のページをほぼ水平に保つことができるため、手を使わずに読むことが可能になります。
こんなシーンで活躍します
- キッチンで料理をしながらレシピ本を見るとき
- DIYや工作で、作業工程を本で確認したいとき
- 学生が両手でノートを書きながら、参考書を見るとき
- 病院や介護現場で、マニュアルを開いたまま確認したいとき
これらの用途において、従来の製本方法ではページが閉じてしまうという“当たり前の不便”が存在していました。
でもなぜ、閉じないの?
その秘密は、「背表紙の構造」にあります。
従来の製本では、ページを綴じる部分に強い糊や圧力がかかり、開いた時に反発して閉じようとする力が働きます。
クータ・バインディングでは、糊の使用法や紙の折り方、背表紙の設計に工夫を凝らし、“開く力”が自然に働く構造を作り上げているのです。
この構想・開発には、なんと3年もの歳月がかかりました。
しかも日本だけでなく、台湾・韓国でも特許を取得済み。
つまり、これは単なる「便利な本」ではなく、国際的にも評価されている確かな“技術”なのです。
開発したのは長野県の老舗出版社・渋谷文泉閣
この記念日の中心人物は、長野県長野市に本社を置く老舗出版社・株式会社渋谷文泉閣(しぶやぶんせんかく)。
昭和13年(1938年)創業の歴史ある出版社で、地域に根差した書籍づくりを行ってきました。
「クータ・バインディング」は、その渋谷文泉閣が“現場の声”を丁寧に拾い上げ、長い開発期間を経て完成させた製本技術です。
開発チームは、読者が実際に不便を感じているシーンを何度もヒアリング。
「ページが閉じること」がどれだけストレスになるかを徹底的にリサーチし、構造の見直しを何度も重ねたと言います。
今では、自社出版の書籍だけでなく、他社の出版物や企業のマニュアル、学校教材など、様々な印刷物に応用されています。
渋谷文泉閣の「製本の力で、読書体験をもっと豊かにしたい」という理念が、この記念日には詰まっているのです。
クータ・バインディングの日に関するよくある質問
Q1:クータ・バインディングと普通の製本の違いは?
A: クータ・バインディングは、背表紙に特殊な構造を持ち、ページが自然に開いたままキープされます。
通常の製本(並製本・上製本など)では、背表紙の糊が硬いため、開くと反発して閉じようとします。
クータ・バインディングではこの“反発力”を限りなく小さくし、「まるで重力に逆らわずに開いている」ような自然な状態を作り出しているので
Q2:クータ・バインディングの書籍はどこで買えるの?
A: 渋谷文泉閣のオンラインストアや一部書店、学習教材の販売サイトなどで取り扱いがあります。
また、企業や自治体が発注するマニュアルや案内書に使われることもあります。
Q3:どうして「特許」まで取れる製本技術なの?
A: 一見、シンプルなアイデアに見えますが、その裏には紙の材質、綴じ方、糊の使い方、開閉バランスなど、数十の技術的な工夫が詰まっています。
これらを組み合わせた製本構造は独自性が高く、既存の製本方法と明確に差別化できるため、日本・台湾・韓国での特許取得が実現しました。
クータ・バインディングの日のまとめ
「クータ・バインディングの日」は、手を使わずに本を開いておけるという画期的な製本技術を、もっと多くの人に知ってもらいたい――
そんな想いから、長野県の出版社・渋谷文泉閣が制定した記念日です。
その日付は、「ク(9)ータ・バ(8)インディング」の語呂と、秋の読書シーズンにぴったりな季節感を融合させた9月8日。
開発に3年かかり、日本・台湾・韓国で特許も取得。
日々の生活で感じていた“ちょっとした不便”を、優しく、でも確実に解決してくれる――そんな温かみのある技術です。
誰もが一度は経験した「ページが勝手に閉じるイライラ」。
その“当たり前のストレス”を、製本という目立たない分野から変えてくれた「クータ・バインディング」。
記念日を通じて、そんな見えない技術と努力に、改めて目を向けてみませんか?
今日は何の日(9月8日は何の日)
国際識字デー | 「明治」改元の日 | サンフランシスコ平和条約調印記念日 | ニューヨークの日 | 桑の日 | クータ・バインディングの日 | クーパー靱帯の日 | クレバの日(908DAY) | 新聞折込求人広告の日 | Cook happinessの日 | マスカラの日 | スペインワインの日 | ファイバードラムの日 | 休養の日 | ハヤシの日 | クレバリーホームの日 | いずし時の記念日 | ドンペンの日 | よくばり脱毛の日 | クリープハイプの日 | 信州地酒で乾杯の日(毎月8日) | 歯ブラシ交換デー(毎月8日) | ホールケーキの日(毎月8日) | スッキリ美腸の日(毎月8日) | 果物の日(毎月8日) | 生パスタの日(7月8日、毎月7日・8日) | 帰雁忌 | 薬師縁日(毎月8日) | 歯ヂカラ探究月間(9月1日~30日)