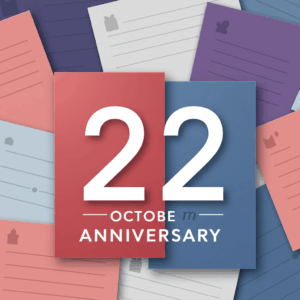国際吃音啓発の日(10月22日)はどんな日?
✅ 吃音(きつおん)に対する理解を深め、偏見をなくし、支援を広めるための記念日。
✅ 緑色のリボンがシンボルで、吃音に関する認識を高める活動が行われる。
✅ 国際吃音者連盟、国際流暢性学会などの団体が設立に関与している。
毎年10月22日は「国際吃音啓発の日」です。
この日は、吃音を持つ人々への理解を深め、社会全体での支援を広めることを目的とした重要な記念日です。
吃音を抱える人々が日々直面している困難に思いを馳せ、この障害を乗り越えるために私たちができることについて一緒に考えていきましょう。
吃音(きつおん)って、どんなもの?
「吃音」と聞いて、どんなイメージが浮かびますか?
「どもり」とも呼ばれるこの障害は、話すときに言葉がつかえる、あるいは言葉がうまく出ない状態を指します。
吃音は、言葉を繰り返したり、長く引き伸ばしたり、または突然言葉が出なくなることがあります。これにより、言いたいことが伝えられず、相手との会話が思うように進まないといった状況が続きます。
吃音は、言葉の障害ですが、それは単なる「話し方」の問題ではありません。心理的にも大きな影響を与えることがあるのです。
例えば、吃音を持つ人は、会話の際に相手に不安を与えるのではないかと心配したり、自己表現に自信を持てなくなったりすることがあります。
これは、単に言葉が詰まるという現象にとどまらず、社会的なつながりや仕事、学校でのコミュニケーションにまで影響を及ぼす可能性があります。
なぜ10月22日? 国際吃音啓発の日ができた理由
1998年、国際吃音者連盟(ISA)と国際流暢性学会(IFA)が中心となり、国際吃音啓発の日が制定されました。
その目的は、吃音に対する理解を広めるとともに、吃音を持つ人々に向けた支援の輪を広げ、社会全体で吃音に対する偏見や誤解をなくしていくことです。
毎年、この日を迎えるにあたり、世界中で様々なイベントやキャンペーンが行われ、吃音に関する情報を広める活動が展開されます。
この日をきっかけに、吃音を持つ人々の困難を理解し、少しでも支援できる方法を考えることが、私たち一人一人に求められています。
「緑色のリボン」って?
国際吃音啓発の日のシンボルは、「緑色のリボン」です。
このリボンは、吃音を持つ人々への理解と支援を示すものです。リボンをつけることで、吃音に対する関心を示し、社会全体で支援の輪を広げていこうというメッセージを発信します。
また、このリボンの存在は、吃音に対する偏見をなくすための第一歩として、大切な意味を持っています。
吃音を持つ人々への支援活動
「吃音啓発の日」を中心に、世界各地では吃音に関する講演会やオンラインイベントが行われています。
これらの活動は、吃音に対する知識を深め、理解を広めるための貴重な機会です。
例えば、専門家や吃音を持つ当事者が経験談を語ったり、吃音に対する支援方法についてのワークショップが開かれたりします。
これにより、参加者が自分たちの生活や仕事でどのように吃音を持つ人を支援できるかを考えることができます。
日本でも、様々な団体や個人が「吃音啓発の日」に合わせてイベントを開催し、吃音を持つ人々の生活をサポートするために活動しています。
支援の方法は、単に会話を聞くことやアドバイスをすることだけではありません。吃音を持つ人々が安心して自分を表現できるような環境を作ることが重要です。
例えば、職場や学校での配慮としては、プレゼンテーションや発表の場で、吃音を持つ人に対して柔軟な対応をすることが挙げられます。
例えば、発言を無理に促すことなく、ゆっくり話す時間を確保することも一つの支援方法です。
私たちができること
「国際吃音啓発の日」に、私たちができることは何でしょうか?
まずは、吃音についての正しい知識を身につけることです。吃音を持つ人々がどのような課題に直面しているのか、その苦しみや不安に共感し、理解を深めましょう。
また、日常生活の中で、吃音を持つ人が安心して会話できる環境を作ることが大切です。
例えば、会話の際に焦らせず、ゆっくりと聞くこと、そして彼らが自信を持って話せるようにサポートすることです。
最も大切なのは、吃音を持つ人々を「特別な存在」として扱うのではなく、ありのままの自分を大切にできる社会を作ることです。
まとめ:共に歩む社会へ
10月22日の「国際吃音啓発の日」は、吃音を持つ人々の理解を深め、彼らを支援するための大切な日です。
この日をきっかけに、私たち一人一人ができることを考え、行動に移すことが、より良い社会を作る第一歩となります。
吃音を持つ人々が安心して自分を表現できる社会を作るために、私たち全員が理解し合い、支え合っていくことが求められています。
この日を通じて、少しでも多くの人々が「吃音に対する理解」を深め、行動に移すきっかけとなることを願っています。