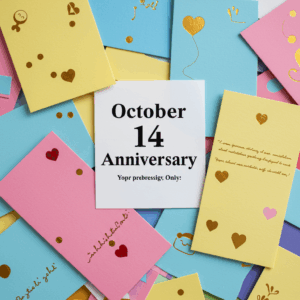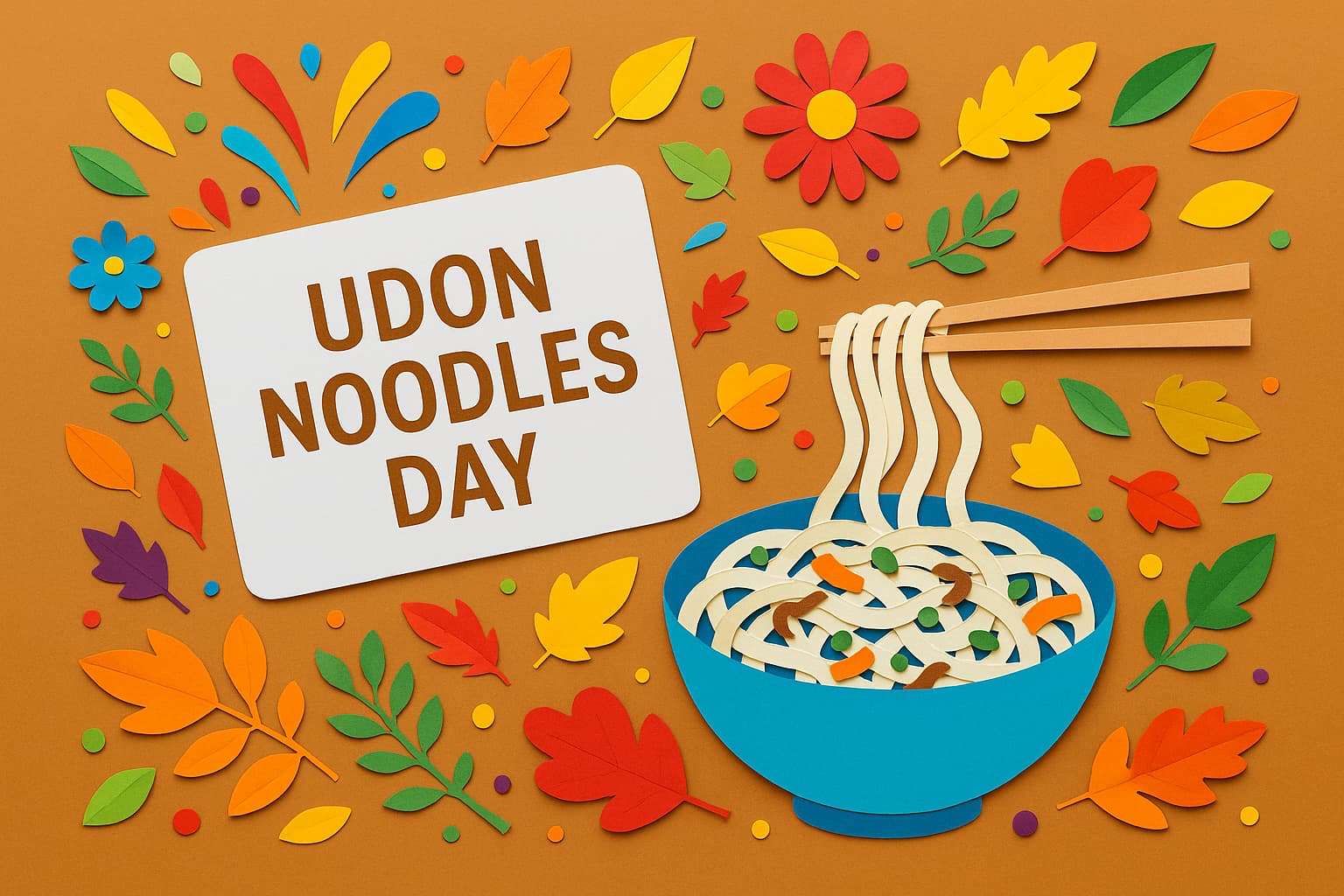焼うどんの日(10月14日 記念日)はどんな日?
✅ 小倉焼うどん研究所が2002年10月14日のご当地グルメ対決を記念して制定した日です。
✅ 焼きそばVS焼うどんの「天下分け麺の戦い」で、小倉の焼うどんが全国的に注目されました。
✅ 小倉焼うどん研究所と日本記念日協会が正式に認定・登録を行いました。
ソースの香りに包まれて──焼うどんの日が教えてくれる、あたたかな記憶と地域の力
ジュウジュウと鉄板の上で立ち上る湯気。
香ばしいソースの匂いとともに、カリっと炒められたうどんに野菜やお肉が絡み合う。
ああ、これはまさしく、焼うどんの魅力です。
「焼うどん」という言葉を聞いたとき、あなたはどんな場面を思い出すでしょうか?
屋台、家庭の食卓、文化祭、給食……きっと、温かくて懐かしい風景が浮かんだはずです。
そんな焼うどんに、実は公式な「記念日」があることをご存じですか?
その名も──「焼うどんの日(10月14日)」。
この記念日は、ただのグルメの日ではありません。
戦後の食文化と、地域の知恵、そしてまちおこしへの情熱が結晶となった、北九州市小倉が全国に誇る記念日なのです。
ではなぜ、焼うどんはこの日を記念日としたのでしょうか?
どんな人たちが関わり、どんな思いで広めてきたのでしょうか?
ここでは、「焼うどんの日」の歴史や豆知識、小倉との深いつながりを、たっぷりとご紹介します。
焼うどんの日(10月14日)の由来は「天下分け麺の戦い」だった!
焼うどんの日のきっかけは、2002年10月14日。
福岡県北九州市の焼うどんと、静岡県富士宮市のやきそばが、グルメ対決イベントで激突しました。
その名も「焼うどんバトル特別編 ~天下分け麺の戦い~」。
ラーメンでも、パスタでもない──
日本を代表するご当地“麺料理”のプライドが火花を散らした一戦です。
この勝負の舞台は、静岡県富士宮市。
地元の「富士宮やきそば学会」と、北九州の「小倉焼うどん研究所」が火花を散らしました。
この時、小倉の焼うどんが「うどんでここまでできるのか!」と大絶賛され、「焼うどんの発祥は小倉だ!」と、全国から注目を集めたのです。
その記念すべき日を忘れないようにと、「小倉焼うどん研究所」が記念日として申請。
一般社団法人 日本記念日協会により正式に認定され、今では10月14日は「焼うどんの日」として定着しています。
この記念日は、小倉のまちづくりにとっても大きな意味を持っています。
観光資源として、
食文化の象徴として、
そして“地域の誇り”として──。
焼うどんは、小倉という街を映す鏡なのです。
焼うどんの日(10月14日)に知ってほしい!香りと歴史が混ざり合う豆知識
焼うどんというと、「うどんを焼いたものね?」と簡単にイメージしがちですが、実はこの料理、奥が深いのです。
焼うどんは、終戦直後の1940年代、小倉の居酒屋「だるま堂」で誕生したと言われています。
当時は物資不足で、焼きそばに使う中華麺が手に入りづらい時代。
そんな中、店主が「干しうどん」をゆがいて代用し、ソースで炒めて提供したのが始まりです。
「苦肉の策」から生まれた焼うどん。
でも、それが驚くほど美味しくて、たちまち評判に。
これが現在の「小倉発祥焼うどん」のルーツとなったのです。
味付けは、ソースベースが主流ですが、醤油風味、塩ダレ仕立てなどもあり、各家庭や店舗で“個性派アレンジ”が楽しめるのも魅力の一つです。
具材も、実にバラエティ豊か。
豚肉、キャベツ、タマネギ、もやし、ピーマン、天かす、小エビ……
トッピングには青のり、かつお節、ネギ、紅しょうがなどが一般的ですが、チーズや温泉卵をのせて「とろける系」に仕上げる人も。
「焼きうどん」とひとことで言っても、その可能性は無限大です。
しかも、地域によっては全く違う焼うどん文化が育っています。
・岩手県岩手町の「いわてまち焼きうどん」
・三重県亀山市の「亀山みそ焼きうどん」
・岡山県津山市の「津山ホルモンうどん」
・群馬県藤岡市の「キムトマ焼きうどん」
これらはすべて、地元の食材と結びついて誕生した「ご当地焼うどん」です。
でも、どの地域の焼うどんにも、共通して流れているものがあります。
それは──「地域の味を残したい」「地元を元気にしたい」という想いです。
焼うどんの日(10月14日)を支える人々と団体の情熱
この記念日を語るうえで、絶対に欠かせない存在があります。
それが「小倉焼うどん研究所」です。
彼らは、焼うどんを通じてまちづくりに貢献するボランティア団体。
「焼うどんは小倉の誇り」だという強い想いを持ち、
普及活動、イベントの企画、グルメフェスへの出店など、様々な形で活動を続けています。
焼うどんのレシピや由来を伝えるパンフレットを作ったり、地元の小学生に「焼うどん教室」を開催したり、その活動の幅は年々広がっています。
また、焼うどんの日の制定を正式に認定・登録したのは、「日本記念日協会」です。
この団体は、日本国内の記念日を認定する唯一の公式機関として知られており、「焼うどんの日」も正式な記念日として登録されています。
「おいしい料理が人を集め、地域を盛り上げる」──
焼うどんには、そんな“まちおこしの力”が宿っています。
焼うどんの日(10月14日)に関するよくある質問
Q1:焼うどんを本場で食べたい!どこに行けばいい?
A:福岡県北九州市小倉北区が本場です。
特に「だるま堂」は、元祖焼うどんの店として知られ、観光客にも人気があります。
Q2:家庭で作るときのコツは?
A:うどんはコシのある「冷凍うどん」が最適です。
先にうどんを軽く焼いてから具材を混ぜると、香ばしさがアップします。
仕上げに「追いソース」を加えると、屋台風の味に近づきます。
Q3:焼うどんと焼きそば、どっちがヘルシー?
A:一概に言えませんが、うどんは中華麺より油分が少なく、
具材次第でよりヘルシーに仕上げやすいです。
野菜多め、油少なめにすればダイエット中でも安心です。
焼うどんの日(10月14日)のまとめ
「焼うどんの日」は、料理の記念日であると同時に、地域の食文化と人々の想いが詰まった日でもあります。
戦後の苦しい時代に、知恵を絞って生まれた“代用メニュー”が、今では立派なご当地グルメに。
そして今も、小倉のまちと人々を支える力となっている。
たった一皿の焼うどんが持つ、あたたかく、力強いエネルギー。
10月14日には、ぜひあなたも焼うどんを味わいながら、そのストーリーに思いを馳せてみてください。
今日は何の日(10月14日は何の日)
世界標準の日 | 鉄道の日 | PTA結成の日 | くまのプーさん原作デビューの日 | 焼うどんの日 | 塩美容の日 | フルタ生クリームチョコの日 | 美味しいすっぽんの日 | ヤマモトヤ・無人売店の日 | 丸大燻製屋・ジューシーの日(毎月14日) | クラシコ・医師の日(毎月14日) | 受信環境クリーン月間(10月1日~31日)