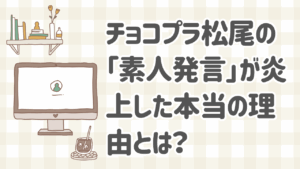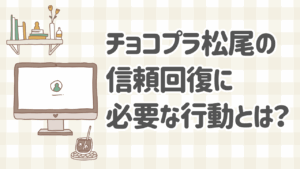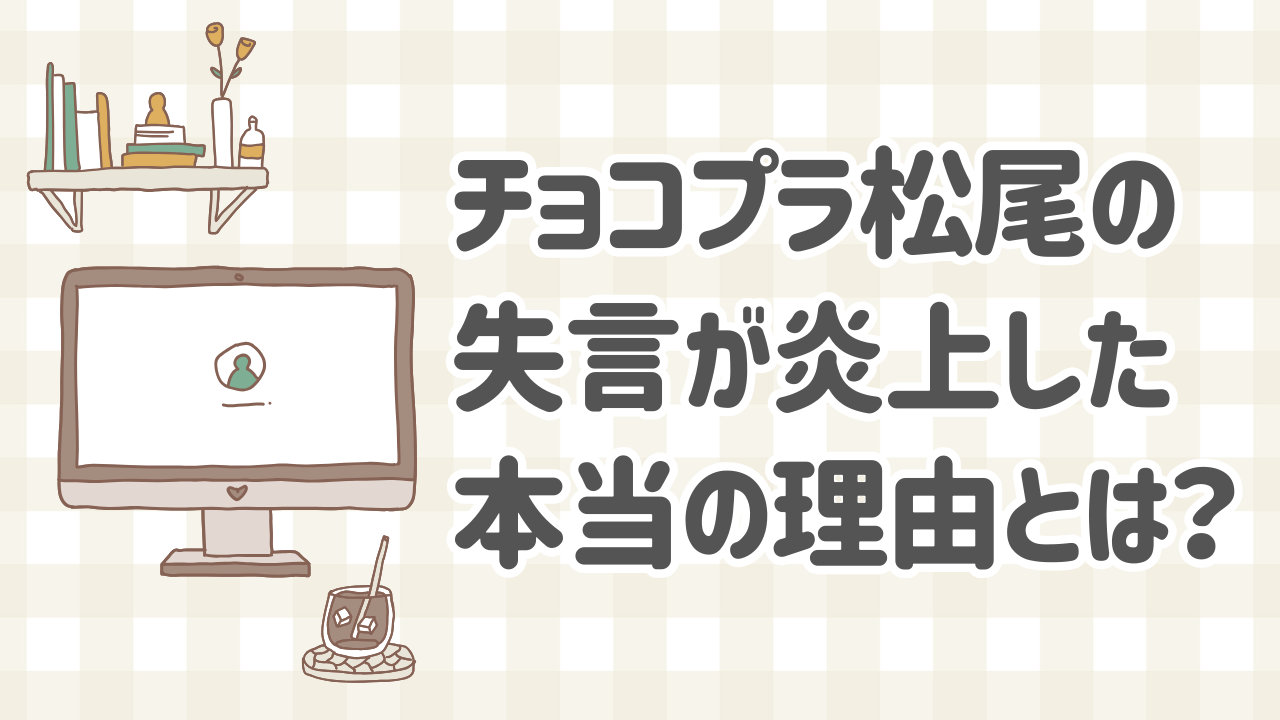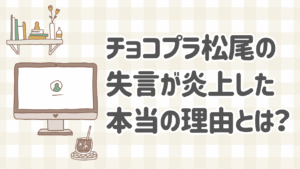この記事のポイント
- 松尾さんの問題発言「素人はSNSをやるな」とは、どんな文脈で語られたのか
- なぜここまで世間の反発を呼んだのか?その背景にある社会構造
- SNSユーザーのリアルな声や反応と、芸能人の立場とのギャップ
- 炎上の経緯、影響、そして今後の論点までを網羅
芸能人と“素人”、SNSは誰のもの?
ある日突然、好きな芸人が「素人はSNSをやるな」と言った。
その瞬間、何かが壊れたような気がした――。
2025年9月、人気お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿さんが、YouTubeの番組で放った一言。
それは「芸能人やアスリート以外はSNSをやるな」「素人が何を発信してんだって、ずっと思ってる」。
炎上の火種は、この言葉だった。
何気ない一言が、なぜここまで多くの人の“導火線”に火をつけたのか?
この記事では、その背景や構造を深掘りし、私たちがなぜ怒り、なぜ裏切られたように感じたのかを紐解いていきます。
チョコプラ松尾の「失言」──発言の経緯を整理する
この発言があったのは、チョコプラのYouTubeチャンネル「チョコプラのウラ」。
2025年9月10日に配信された動画内でのことです。
松尾さんと相方・長田庄平さんは、「アインシュタイン・稲田直樹さんのInstagram乗っ取り事件」について言及していました。
この事件では、乗っ取られたアカウントを使って、不適切なメッセージが送信されたとされ、稲田さんが炎上の的に。
結果的には乗っ取りが確認され、誹謗中傷の原因となったユーザーが逮捕される事態にまで発展しました。
その流れの中で、松尾さんはこう語ったのです。
「俺がずっと提唱している、誹謗中傷に関してだけど」
「芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって」
「素人が何、発信してんだって、ずっと思ってるの」
この一連の発言により、炎上がスタート。
SNS上では、「一般人を見下している」「言論の自由の否定」など、批判の声が瞬く間に広がっていきました。
なぜここまで炎上したのか?──感情の構造と社会のズレ
「素人」という言葉が持つ“棘”
日本のお笑い業界では、今もなお「素人」という言葉が使われます。
賞レースやバラエティ番組では、プロとアマチュアを分けるために、ある意味で“専門用語”としても機能してきました。
しかし、SNSは違います。
SNSの本質は、「誰もが発信者になれる場」。
言い換えれば、そこにはプロも素人もなく、“すべての人の声”が並列で存在している。
そのSNSという自由な場所に対して、「素人はやるな」という発言は、根本的にフィールドのルールを否定することになります。
このギャップこそが、今回の炎上の最大の要因でした。
誰もが“表現者”でありたい時代に──「排除された」と感じた人たち
X(旧Twitter)やInstagram、YouTube。
今や誰もが「自分の考えを発信できる」ことが、当たり前になっています。
だからこそ、その言葉を「見下す」ような発言には、強烈な拒絶反応が生まれました。
特に、チョコプラは「芸能人だけど身近な存在」として人気を集めてきたコンビ。
テレビでの親しみやすいキャラ、YouTubeでの緩いやりとり。
だからこそ、「そんな彼らに見下されていたのか」と感じた人の失望は、怒りへと変わったのです。
SNSユーザーのリアルな声──「発信する自由」は誰のもの?
SNS上では、こんな意見が目立ちました。
「SNSはもともと“素人”のためのものだったはず」
「芸能人も一般人も、同じSNSで発信してるじゃん。なんで線を引くの?」
「素人って、言葉がもうバカにしてる。なんでそんな上からなの?」
中には、松尾さんの意図を汲んで「誹謗中傷を許さない気持ちはわかる」という声もありました。
しかし、それ以上に響いたのは、「発言の言い方」と「価値観のズレ」。
言葉は、意味以上に“温度”が伝わるものです。
そして、その“温度”が冷たかった。
それが、人々の怒りの本質だったのではないでしょうか。
「非公開対応」は火消し?それとも火種?
問題の発言が拡散された後、該当動画はYouTube上で非公開となりました。
公式の説明や謝罪は、少なくともSNSやYouTube内では確認できていません。
この対応に対しても、多くの人が不信感を抱きました。
「しれっと動画を消すのは逆にズルい」
「自分の発言には責任を持ってほしい」
「消せばなかったことになると思ってる?」
説明も釈明もなく、ただ“消す”という行動は、逆に「逃げている」と映ってしまいます。
謝罪か、訂正か、それとも意図の説明か。
何らかの言葉が必要だったのは、言うまでもありません。
「素人」という呼び方がもたらす分断
ここで改めて問いたいのは、「素人」という言葉の使い方です。
芸人やプロスポーツ選手が、“一流”や“プロ”として評価される一方で、「じゃあ、それ以外の人の言葉や発信には価値がないのか?」
そんな問いが、SNS上では無数に交わされました。
本来、素人か玄人かは、“技術的な線引き”に過ぎないはずです。
ところが、それが「発信の権利」や「社会的価値」の線引きに転化してしまうとき、
そこには、非常に危険な“選民意識”が生まれます。
芸能人と一般人、その境界線は曖昧になった
令和の時代において、芸能人と一般人の境界はますます曖昧です。
YouTuberやTikTokerは「一般人」でありながら数十万、数百万人のフォロワーを持ち、インフルエンサーとしてメディアにも登場します。
いわば、かつての「素人」が、プロ顔負けの影響力を持つ時代。
そんな時代に、「プロ以外は黙ってろ」は、もはや通用しない。
そのことに、松尾さんは気づくべきだったのかもしれません。
まとめ:この炎上が私たちに教えてくれたこと
SNSは、誰もが言葉を持ち、声を持てる時代の象徴です。
松尾さんの発言は、「素人」という言葉が想像以上に多くの人の自己肯定感や社会的存在意義を傷つけたことを示しました。
悪意がなかったとしても、言葉は届き方次第で、誰かを深く傷つけます。
そして、信頼は一瞬で崩れ去ることもあるのです。
大切なのは、「自分がどう思っているか」ではなく、
「相手にどう届くか」「どんな影響を与えるか」。
この件を通じて、私たちは改めて“言葉の責任”と“発信の自由”について考えさせられました。