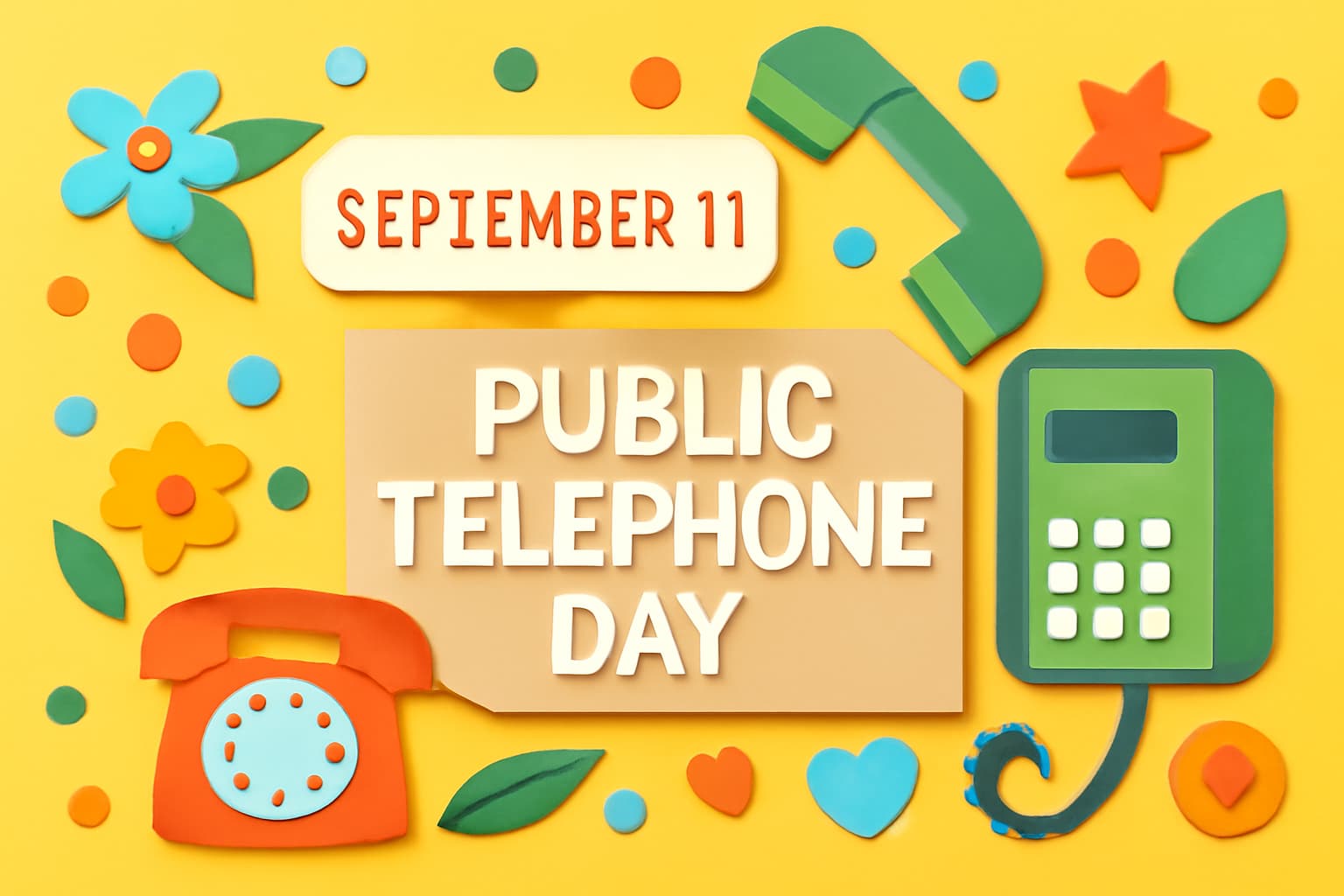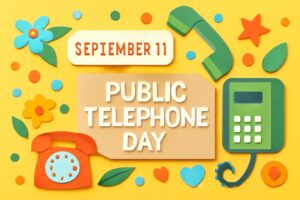「公衆電話の日」(9月11日)はどんな日?
✅ 1900年、東京の新橋駅と上野駅に日本初の自動公衆電話が設置された日。
✅ 公衆電話は、災害時の重要な通信手段として今も存在している。
✅ 日本電信電話株式会社(NTT)と、初期の公衆電話設置を行った関係者が深く関わっている。
9月11日は「公衆電話の日」です。
1900年、明治33年のこの日に、日本初の自動公衆電話が東京の新橋駅と上野駅に設置されたことを記念して、現在に至るまで続いています。
日本で初めての公衆電話の登場は、当時の人々にとって非常に画期的な出来事でした。
それまで、電話と言えば家庭や企業などの専用回線でしか利用できないもので、外出先で電話をかけるには、公共の場に設置された電話ボックスを使うことが一般的でした。
当初、「自動電話」と呼ばれていたものは、交換手を通さずに直接電話をかけられるという点で革命的でした。
今では考えられないかもしれませんが、それまでの電話は、すべてオペレーターが相手の電話番号に繋いでくれていました。
そのため、最初に公衆電話が登場したときは、周囲の人々にとってとても驚きのものであったことは想像に難くありません。
進化する公衆電話
1925年(大正14年)になると、ダイヤル式の電話が登場し、交換手なしで自分で番号をダイヤルして通話できるようになりました。
これにより、当時の公衆電話は一層便利になり、さらに普及していきました。
その後、公衆電話は鉄道駅や街角、商業施設、空港など、公共の場で広く設置されるようになり、誰でも手軽に利用できる通信手段としての役割を果たしました。
しかし、携帯電話やスマートフォンが普及し、私たちのコミュニケーション手段が変化していく中で、公衆電話の利用機会は急速に減少しました。
今やほとんど見かけなくなった公衆電話ですが、依然としてその存在は私たちの生活の中に残っています。
公衆電話の社会的役割
現代において、公衆電話が果たす重要な役割は、災害時における緊急の連絡手段です。
特に、大規模な地震や自然災害が発生した際、携帯電話の回線が混雑し、通信が困難になることがよくあります。
そのような非常時には、公衆電話が頼りになることがあります。
たとえば、2011年の東日本大震災では、携帯電話の回線が大きく混乱し、ほとんどの人が連絡を取ることができませんでした。
その一方で、公衆電話は災害発生直後でも比較的繋がりやすく、多くの人々が緊急連絡を取るために公衆電話を使用しました。
このような事例からも、公衆電話の社会的な価値が再認識されました。
公衆電話の日まとめ
9月11日は、私たちにとって公衆電話が果たした役割を改めて考える良い機会です。
日常生活では、携帯電話が圧倒的に便利で、あまり意識することは少ないかもしれませんが、公衆電話は今でも非常に重要な役割を果たしています。
災害時における公衆電話の重要性や、過去の歴史的な変遷を振り返りながら、私たちはこの記念日を心に留めておくべきだと思います。
公衆電話があったからこそ、私たちが安心して暮らせる社会が成り立っているのです。
こうして、どこか懐かしさと頼もしさを感じさせる公衆電話の存在に思いを馳せることが、私たちの社会や日常生活における「つながり」の大切さを再認識させてくれるのです。
そして、今後もどこかで見かけた公衆電話に、感謝の気持ちを持ち続けていきましょう。
今日は何の日(9月11日は何の日)
警察相談の日|公衆電話の日|愛国者の日(4月第3月曜日・9月11日)|たんぱく質の日|日本骨髄増殖性腫瘍の日(9月第2木曜日)|ロールちゃんの日(毎月11日)|めんの日(毎月11日・11月11日)|ダブルソフトの日(毎月11日)|おかあちゃん同盟の日(毎月11日)|歯ヂカラ探究月間(9月1日~30日)