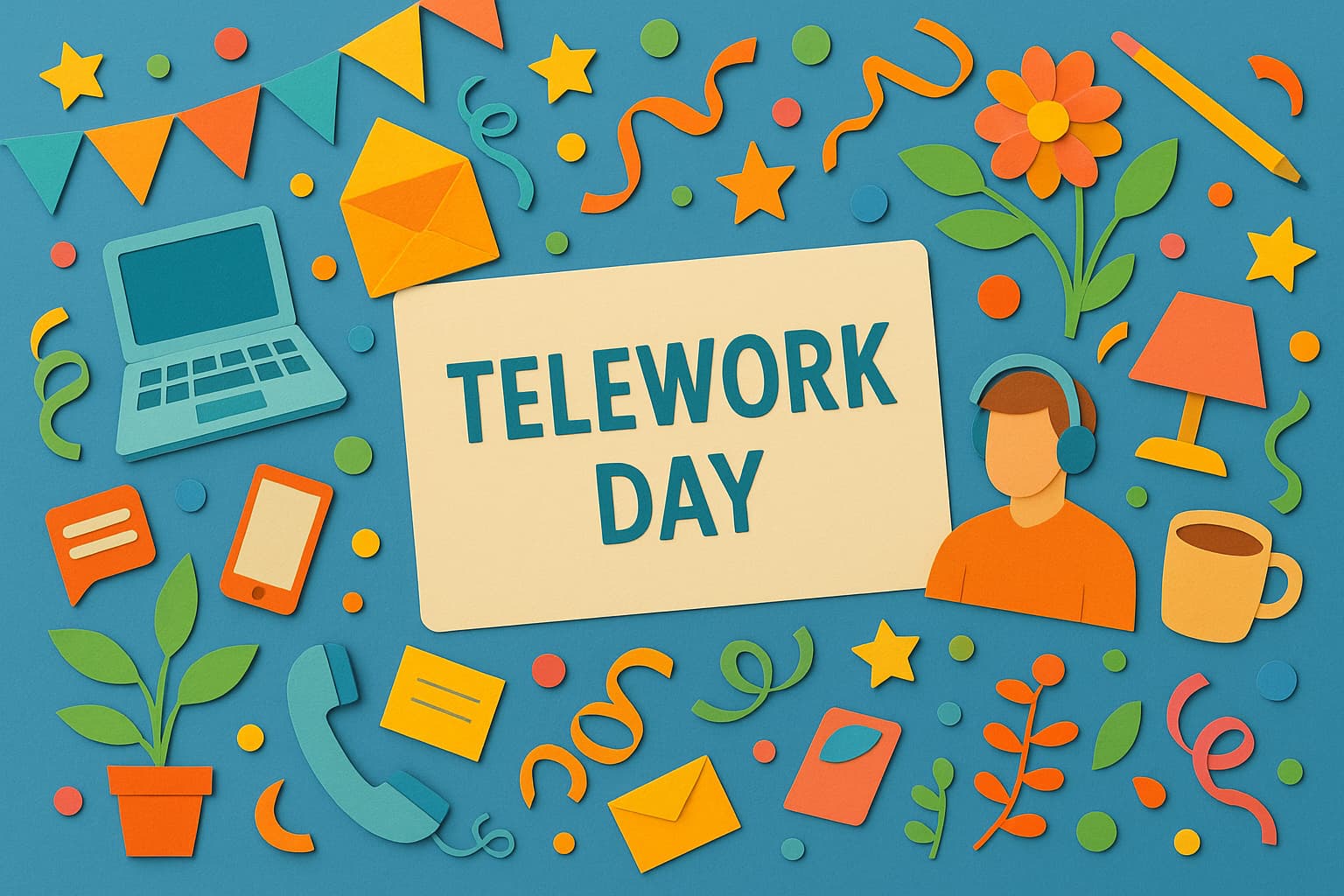「朝、満員電車で押しつぶされそうになった経験、ありますか?」
通勤がしんどい。
でも働かなきゃいけない。
そんな日々に、少しでも「心のゆとり」と「時間の自由」を届けてくれる。
それが、「テレワーク・デイ(7月24日 記念日)」です。
この日は、日本政府が主導して「働く、を変える日」として2017年に始まった記念日。
名前のとおり、「テレワークを一斉に実施して、未来の働き方を体験してみよう!」という日なんです。
きっかけは2020年の東京オリンピック・パラリンピック。
首都圏の交通混雑が予想された中、「じゃあ通勤せずに仕事すればいいじゃないか」と、全国一斉のテレワークが提案されました。
でも、実はこの日はただの「交通対策」ではありません。
本当の目的は、「テレワークって、案外アリかも?」と気づくための“新しい働き方の入り口”。
仕事はもっと自由にできる。
時間の使い方も、人生の選択肢も、変えていける。
そう信じられるきっかけになる、大切な1日です。
テレワーク・デイはどんな日?
✅政府が推進する「働く、を変える日」
✅東京オリンピック開会日が由来
✅テレワークの体験と社会実験を目的
テレワーク・デイの由来と目的:なぜ7月24日?
2017年7月24日――
この日、日本中で一斉にテレワークを実施する試みがスタートしました。
名付けて「テレワーク・デイ」。
発起人は、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、内閣官房、内閣府と、そうそうたる政府機関たち。
さらに、東京都、経済団体連合会(経団連)や、数多くの民間企業も巻き込む形で進められました。
この日が選ばれた理由――それは、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開会日である「7月24日」に由来します。
オリンピック期間中は、首都圏の交通がパンクするほど混雑するのでは?と懸念されたため、政府は一斉テレワークを呼びかけることにしました。
このアイデアの背景には、2012年のロンドンオリンピックがあります。
イギリス政府が大会期間中、企業にテレワークを推奨し、見事に交通混雑を回避することに成功したのです。
この成功をモデルに、日本でも「テレワーク・デイ」という国民運動を展開。
目的は大きく3つあります。
1つ目は、「交通混雑の緩和」
2つ目は、「働き方改革の体験」
3つ目は、「企業や社会全体の意識変革」
1日だけでもテレワークをしてみることで、「働くって、こういう形もあるんだ」と気づける。
その“最初の一歩”として、テレワーク・デイが生まれました。
テレワーク・デイの豆知識:ただの在宅勤務ではない!
「テレワークって、家でパジャマで仕事することでしょ?」
そんなふうに思っていませんか?
実は、テレワークは単なる在宅勤務ではありません。
その定義は、「ICT(情報通信技術)を活用し、時間や場所に縛られずに働くこと」。
つまり、家だけでなく、カフェ、コワーキングスペース、時には旅行先でもOK。
仕事に必要なツールさえ揃っていれば、どこでも“職場”になる。
この自由度こそが、テレワークの魅力です。
また、テレワークには3つの代表的な形態があります。
- 在宅勤務(自宅で仕事)
- モバイルワーク(移動中や外出先で仕事)
- サテライトオフィス勤務(企業が設けた別拠点で仕事)
つまり「働く場所の選択肢を増やす」という考え方なんですね。
さらに、テレワークは社会にも大きなメリットをもたらします。
・通勤ラッシュによる交通負荷の軽減
・ワークライフバランスの向上
・育児・介護との両立支援
・地域の雇用創出と地方創生
このように、テレワークは「個人」「企業」「社会」すべてに恩恵をもたらす、新しい働き方なんです。
テレワーク・デイを支える組織と参加企業
テレワーク・デイのすごいところは、国家レベルの取り組みであること。
主導するのは、総務省や厚労省をはじめとした政府機関。
特に、総務省は「テレワーク推進の中核的存在」として、全国の自治体や企業と連携を強めています。
また、東京都もオリンピック対策としてテレワーク導入に力を入れ、都庁職員自らがテレワークを体験しました。
民間企業の参加も非常に活発です。
たとえば:
- NTTグループ
- 富士通
- サイボウズ
- 楽天グループ
- 日立製作所
など、業界を代表する大手企業がこぞって参加。
「うちの会社では無理」と思われがちな中小企業にも、業務別の導入例を公開するなど、参考事例が豊富に提供されました。
さらに、地方自治体では、サテライトオフィスやワーケーション施設の整備が進められ、都市と地方の新しい関係性も生まれつつあります。
テレワーク・デイに関するよくある質問
Q1. テレワーク・デイって、毎年実施されてるの?
A1. はい。2017年の初回以降、毎年7月24日前後に「テレワーク月間」や関連イベントが行われています。公式運動ではなくなっても、各地で自主的に継続されています。
Q2. どうやって参加すればいいの?
A2. 基本的には「会社単位」での取り組みが一般的ですが、フリーランスや個人事業主として自主的に参加することも可能です。SNSでの発信も推奨されています。
Q3. テレワークに向いてる職種って?
A3. 主にパソコン作業中心の業務(IT・事務・企画・営業支援など)が中心ですが、最近ではVR接客や遠隔医療など、幅広い分野に応用が広がっています。
テレワーク・デイのまとめ:未来を変える1日
「テレワーク・デイ(7月24日 記念日)」は、ただの交通混雑対策ではありません。
それは、日本の未来の働き方を考えるきっかけとなる、大きな第一歩。
この日がきっかけで、通勤しないという選択肢が社会に浸透し、時間と場所に縛られない「新しい働き方」が広まりました。
働き方が変われば、生き方も変わる。
そのきっかけが、あなたの1日になるかもしれません。