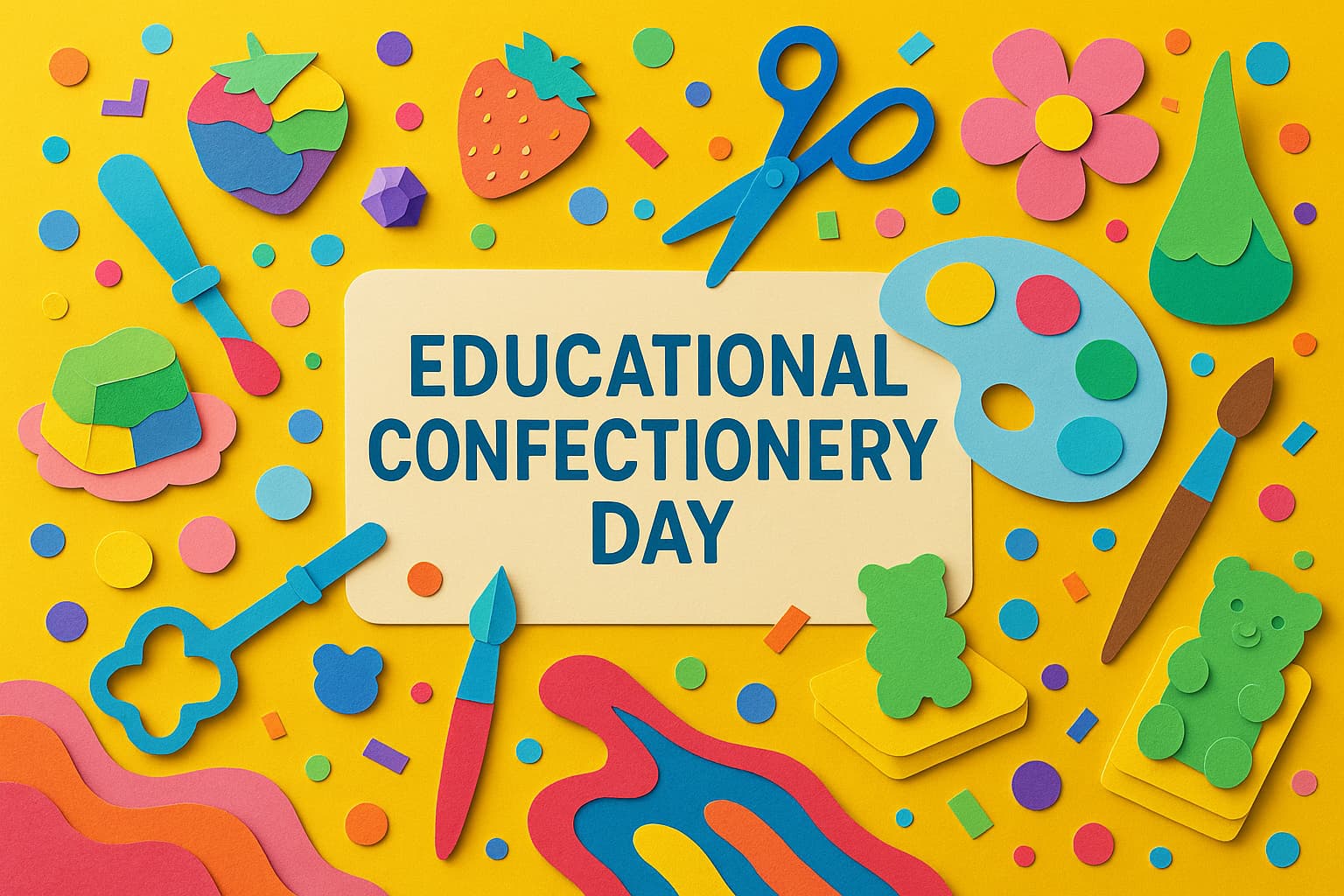「ねえ、お母さん、色が変わったよ!」
クレヨンで描くよりも、口にするお菓子を作っているほうが、わが子の目がキラキラ輝いています。
そんな日常の一コマを彩るのが、クラシエの“知育菓子”。
このブログでは、7月19日に制定された「知育菓子の日」の意味、背景、そしてなにより、そのお菓子がどんな風に子どもの成長を後押ししてくれるかを紐解きます。
親子で手を伸ばして、練り、膨らませ、作り上げて、そして一緒にむしゃむしゃ。
そんな小さな冒険を通じて芽生える好奇心や達成感の瞬間。
それらを、もっと大切にしたい。
今回のテーマ、“知育菓子の日(7月19日)”は、まさにその想いを祝福する記念日なのです。
✅ クラシエが制定した知育重視の記念日
✅ 語呂合わせ「ち(7)いく(19)」で7月19日
✅ 夏休み直前に好奇心と成長を応援
「知育菓子の日」の由来 ~7月19日が選ばれた理由~
知育菓子の日は、2021年6月にクラシエフーズ株式会社が提案し、一般社団法人・日本記念日協会によって正式に登録されました。
“ち(7)いく(19)”という語呂合わせが覚えやすく、さらに夏休み目前のこの時期に、子どもたちにワクワクする学び体験を届けたい——そんな想いが込められています。
クラシエはもともと1986年に「ねるねるねるね」を発売し、“作って食べる楽しさ”を提供してきたパイオニア。
その知育コンセプトは、科学・芸術・味覚・遊びが融合したもので、単なるお菓子ではなく、子どもの五感を総動員する体験そのものでもあります。
この記念日の誕生日には、「子どもの生きる力を育む」がキーワード。
作品を思いつき、工程に取り組み、「おいしい!」と味わう達成感。
そのすべてが、未来の学びに繋がるといえるでしょう。
知育菓子の日にまつわる豆知識 ✨
○ ねるねるねるねの原点(1986年発売)
1980年代当時、スライムや色水実験などを扱った教育番組が人気でした。
クラシエは「家でもできる“科学の楽しさ”をお菓子にしたい」との発想から、魔法みたいに色が変わる「ねるねるねるね」を世に送り出しました。
発売後は、TV CMに魔女風キャラが登場し、“作る”楽しさと“食べる”喜びを融合させ、一躍ヒット。
○ 「知育菓子」で育つ力
- 化学反応:色が変わる、水を加えて反応するなど、科学への第一歩。
- 音や感触:練る・膨らませる工程で“ふわふわ”や“ぼそぼそ”を感じる。
- 造形・創造性:自分でグミを形作ったり、絵柄を選んで焼いたり。
- 味覚の選択:酸っぱい・甘いなど、好きな味を見つける。
- 自己肯定感:「上手にできた」「自分で考えた」という達成感。
○ SNS動画で広がる楽しさ
近年、YouTubeやTikTokで知育菓子の作成動画が人気沸騰。
「#ねるねるねるねチャレンジ」「おえかきグミランドDIY」などSNS映えする工程が共感を呼び、親子で取り組む姿が広がっています。
○ 全国で記念イベントも
記念日周辺には、クラシエ製品を使ったワークショップや、親子参加の体験イベントが全国各地で開催。
夏祭りや児童館、デパート催事などとのコラボも見られます。
クラシエフーズ株式会社と知育菓子の魅力
元々は調味料やゼラチンなどを得意としていたクラシエ。
1986年から「楽しく学ぶお菓子」を目指して、次々とヒット作を生み続けています。
○ “個性を伸ばす”3つの価値
クラシエは、以下の価値を提供するために知育菓子を設計:
- 個性を伸ばす:選べる味、形、装飾—自由に。
- 失敗を楽しむ:膨らみすぎてもOK、色が薄くてもOK。
- 違いを尊重する:兄弟姉妹で仕上がりが違って当然。
○ 人気商品ラインナップ
- ねるねるねるね:色が変わる化学マジック。
- ドキドキスライム:ねばねば?ふわふわ?触感の違いが楽しい。
- つかめる!ふしぎ玉:液体なのに手でつかめる不思議。
- おえかきグミランド:自分だけのイラストグミを作成。
○ 家庭教育と社会性への効果
親と子が一緒に作業をすることで、「手伝って!」「はい、どうぞ」という自然で温かいやり取りが生まれます。
またワークショップ参加で友達と協力し、社会性やコミュニケーション力も育まれます。
知育菓子の日と関わる人物・組織
○ クラシエフーズ株式会社
本社は東京都港区海岸。創業から約100年の老舗で、品質管理や研究体制も万全。
記念日はもちろん、社員やユーザーの声を反映しながら「本当に役立つ遊び体験」づくりを続けています。
○ 開発担当者の声
「うちの子はまず色を混ぜて変化の順番を予測し、次に形をどうするか考えて…その試行錯誤が宝物のように見えました」——そう話すのは、知育菓子プロジェクトリーダーの山本京子(仮名)。
彼女自身も“親”として、“子どもの目線”を大切に企画に携わっています。
○ 日本記念日協会と他団体
2021年登録時点で、日本記念日協会や児童教育団体と意見交換。
「“遊びながら学ぶ”を記念日として社会へ」との呼びかけは、教育現場や子育て支援団体からも注目されました。
よくある質問
Q1:何歳から楽しめるの?
→ 公式対象年齢は5歳以上。
ただし、保護者と一緒であれば3歳程度からOK。
手洗いや片付けをルール化すれば、小さな子どもでも安心して参加できます。
Q2:おうちで用意するものは?
→ 基本的にお菓子のパッケージに必要な粉・水がセット。
台やラップ、スプーン・小皿程度でOK。
後片付けが苦手な人は、使い捨てトレーやエプロン、濡れタオルを準備すると◎。
Q3:安全性やアレルギー対応は?
→ クラシエは食品衛生法準拠の安全基準で製造。
パッケージにはアレルゲン表記あり。
「小麦」「卵」「ゼラチン」など要注意表示を確認しましょう。
誤食・誤飲防止のため、小さい子には保護者監視が大切です。
まとめ —— 知育菓子の日で親子の宝物を刻もう
「知育菓子の日(7月19日)」は、ただのおやつタイムではありません。
色を観察し、手で練り、形を作る。
一連のプロセスを通じて、子どもは「学び」「創造」「共感」を体験します。
クラシエの知育菓子は、個性を伸ばし、失敗を楽しむ場所としての価値を持っています。
また親も一緒に関わることで、「お手伝いありがとう」「できたね、すごいね」と褒め合う優しい時間が流れます。
その体験と記憶が、子どもの“生きる力”を支えてくれるはずです。
ぜひ7月19日、「知育菓子の日」には、近所のスーパーやオンラインで知育菓子を手に入れ、親子でワクワクする夏の冒険をはじめましょう!